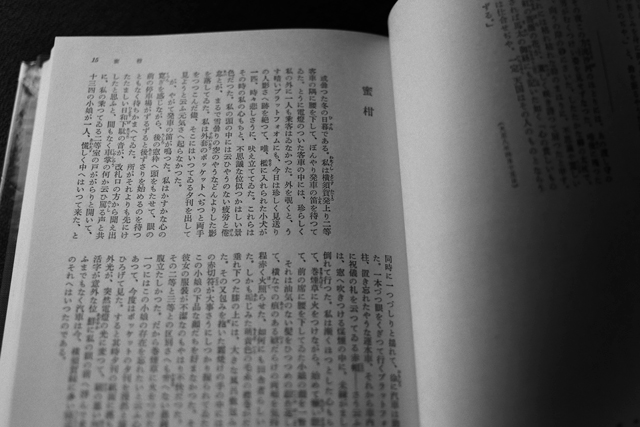 |
| 【筑摩書房の芥川龍之介全集より『蜜柑』】 |
芥川龍之介という人の作品は、それこそ太宰治と同じくこぞって学生に読まれやすい性質がある。この知名度の大きさは、作家にとって、いや作家とその作品を十分に理解する上で、ある種の先入観に侵されやしないか。
近代小説家の著名人であるという点から、芥川や太宰は良くも悪くもスターなのである。そのスターに群がり、その作品とやらを食してみたいと思う若気の好奇心こそが、学生に読まれやすい理由である。ほとんどの場合、先入観に侵されながら。
私も高校時代にそのスター・芥川に出会い、若気の好奇心で『羅生門』を読んでしっぺ返しを食らった一人である。とても読みづらく、難解だった。他の芥川の小説を読みたいとも思わなかった。
近現代の小説を好んでいた私の頭には、あの平安時代の今昔物語の、朱雀大路の羅城門という設定がえらく仰々しく思われ、女の死骸から髪を抜く老婆というインパクトが強すぎたせいか、老婆の着物を剥ぎ取って去って行ってしまう下人の行動性がこの小説の肝であることに気づかなかった。少なくとも高校の国語の授業では、その肝の部分が読解できるか否かが問われた。
尤も、そんなエゴイズムの問題より、芥川が描き出すべき羅城門の荒廃した様子の筆致、その描写の巧拙にも言及すべきだと、私はだいぶ経ってから考えるようになった。
*
さて、高校時代に私が出会った芥川の作品が『羅生門』ではなく、もしも『蜜柑』だったとしたら、私はおそらく何ら先入観に侵されず、その時から猛烈に芥川の小説を読み始めたに違いない――。
12年前のとある雑誌で、評論家・川本三郎氏が横須賀について書いたエッセイがあり、私は最近それを読み返していた。横須賀は軍港のイメージが強い。が、実はトンネルの多い山に囲まれた長閑な町なのだ、と説いている。
そのトンネルの多いJR横須賀線に絡まって、芥川龍之介の『蜜柑』を川本氏は挙げていた。私は急に興味が湧き、書棚の『筑摩全集類聚 芥川龍之介全集』(筑摩書房)を引っ張りだしてきて、その『蜜柑』を読んでみることにした。
大正8年4月発表の短篇作『蜜柑』は、芥川が横須賀の海軍機関学校の教師をしていた頃の作品である。同年3月に学校を辞め、大阪毎日新聞社の嘱託社員として、同社に小説を送っていた。ちなみに『蜜柑』は書き出しが『羅生門』とよく似ている。《ある曇った冬の日暮れである》(『羅生門』の書き出しは《ある日の暮方の事である》)。
おそらく芥川がその頃体験した何らかの事実から着想を得た、と思われる。『蜜柑』はこんな内容である。
横須賀線上りの二等客車に乗った「私」は疲労と倦怠感を伴っていた。この時の「私」は精神と肉体の飽和状態にあった。そこへ十三、四くらいの少女が入ってきて汽車が動き出す。《皸だらけの両頬を気持ちの悪いほど赤く火照らせた、如何にも田舎者らしい娘》。ここは二等客車である。少女は三等の赤切符を握っている。それにも苛立ちを覚えた。《私はこの小娘の下品な顔だちを好まなかった》。
向こう側にいた少女は、何故か私の席の隣に移ってきた。そして少女は重たい硝子戸の窓を必死に開けようとする。まもなく隧道に差し掛かり、いま窓を開けたら、汽車の煤煙が窓から入ってくるにもかかわらず少女は無頓着である。
「私」はひどく苛立ちながら少女の行動を眺めた。しかし一向にその行動をやめない少女は、ついに窓をばたりと開けてしまう。窓から黒い煤煙が入り込んで、「私」は思わず咳き込んでしまう。癇に障った「私」の怒りは沸点に達した。
ところが隧道を抜け、ある貧しい町外れの踏切に差し掛かると、思わぬ光景に出会う。踏切の柵の向こうに、頬を赤らめた背の低い3人の男の子が立っていた。窓から半身を乗り出した少女は、蜜柑を五つか六つ、彼らに投げ飛ばした。おそらくそれは鮮やかな色の蜜柑であった。
「私」は了解する。少女はこれから奉公先へ向かおうとしている。見送りに来た弟たちに少女は蜜柑を投げ、出迎えを労ったのだ。「私」は少女を別人と見るように、気持ちの晴れやかさを感じた。この時「私」は僅かに疲労と倦怠感を忘れることができた――。
読み終わって清涼感溢れる結びに、私も何やら救われた気になった。芥川の、あのおどろおどろしい陰気な『羅生門』とはまったく違う世界が広がっていたせいもあり、絶え間なく変化する汽車の中、「私」の心理と少女の行動とが克明に記録されていた点において、芥川の洗練された描写力を感じた。大正4年の『羅生門』よりも、それが顕著に感じられたことは間違いない。
ただし伊藤整による評論(昭和17年「芥川の描写」)を読むと、違う作品になるが題材とした『山鴫』(大正9年)における芥川の狩猟の描写を、《淡彩と線とで一重にあっさり描かれていて、まことに日本的》と評し、トルストイやツルゲーネフと比較してまだ甘い、ということになる。
私はあの「山鴫」の作品性にその描写力を要求するのは少し違うのではないか、と思ってしまうのだが、伊藤整から見ればそういうことになる。
普段、漱石の小説に読み慣れていると、例えば『吾輩は猫である』(明治38年)から後年の『こゝろ』(『こころ』大正3年)を読み比べても、それぞれの小説の気分的な筆致は変われど、描写力はさして変わっていないと感じるから、芥川の小説における『羅生門』以後に漱石の門下に入った後の描写力というのは、目覚ましく進歩したのではないかと思う。
主情的で抑えきれない芥川の本質を、自身に対する世の中の理知的な作家然とするイメージに合わせようと、必死に藻掻いていたのではないかと思う節がある。作家の売り出しには不運がつきまとう。
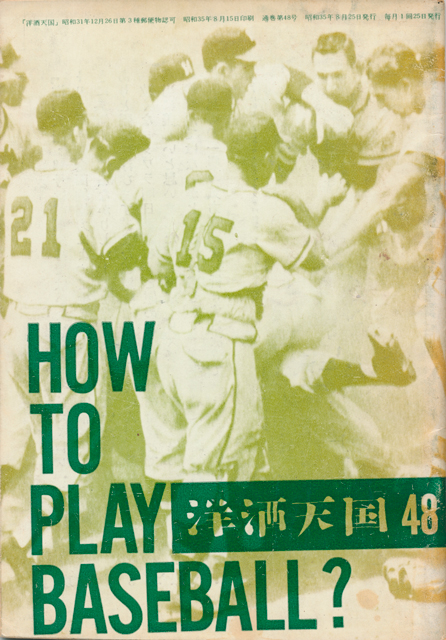
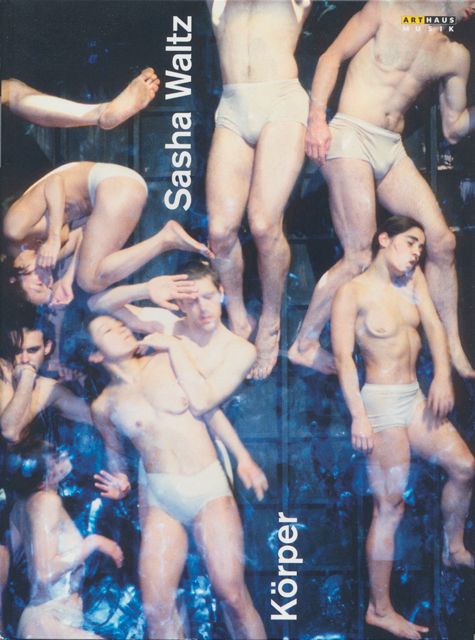
コメント