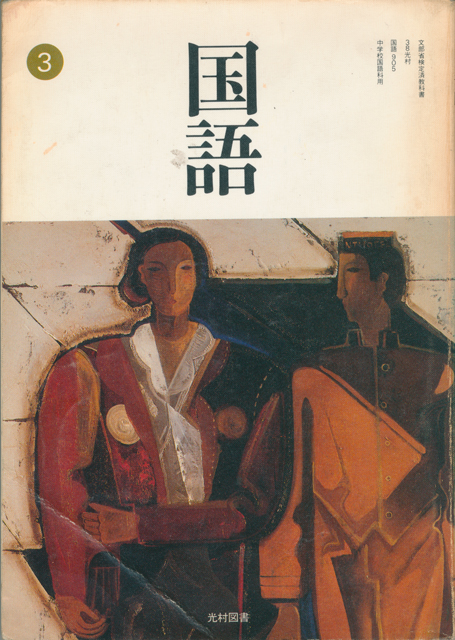 |
| 【魯迅を読むために開いた光村図書の国語教科書】 |
近頃、魯迅を読み始めていて、自宅の書棚にあった古い国語教科書に手が伸びた。
その所作は我ながら電光石火の如きであった。この国語教科書に、魯迅の作品がもしかしてあるのではないかというのは、なんとなくの、勘だった。
その勘は見事に当たった。竹内好訳の「故郷」がそれだ。教科書の口絵あたりには、魯迅の故郷である中国・浙江省紹興の、山と川辺の家々の侘しげなカラー写真が掲載されてもいた。「故郷」はちくま文庫の『魯迅文集』第1巻に拠っている。
そうしてじっくりとこの教科書の中の魯迅――「故郷」を読むことができたのだけれど、そこらへんに附されたふりがなの、小さな手書きの文字にちらちら視線が止まる時、そう言えばあの頃、まだ中学3年だったA子も、魯迅のこれを教室などで読んでいたのだろうなと想像が膨らんでいき、俄に胸の当たりが熱くなっていった。
A子。いまやA子もそれなりにいい歳になっているに違いないのだが、私の心にはまだ高校生だったA子の姿が焼き付いている。
*
そうだったのだ。これはA子の教科書だったのだ。
裏の下隅には、ピンク色の水性ペンで書かれたA子の名前が、消えずにはっきりと残っている。紛れもなくA子の中学校時代の、光村図書の国語教科書(平成6年2月5日発行)であることが分かり、3年分、つまり3冊の国語教科書を彼女からもらったのだった。もらったのは彼女が高校に進学してすぐのことではなかったか。
私が20歳になって間もない頃、自ら結成した小劇団の公演が地元の古びたホールでおこなわれた時、客席にはA子とその友人が座っていた。見知らぬ中学生であった。数少ない観客のうち、最も年少だった彼女らの存在は幾分意外だったし、場違いのようにも思われた。 しかし結局、それが縁となって、それ以降の公演の手伝いをたびたびしてくれたし、しょっちゅう稽古場にも顔を出してくれた。当然、稽古場は明るく賑やかな場となった。およそ3年間そんな状態が続いたのだった。
果たしていつ頃のことだったか、私の心中に〈劇団を辞めたい〉という思いが憂いだしてまもなく、だったと思う。私は何気なくA子に、「A子の持ってる中学の国語の教科書が欲しい」と頼んだ。それが簡単に頼んだことだったのか執拗に懇願したことだったのか、その時の雰囲気をよく憶えていない。いずれにしても私の気持ちには、もうA子と会えなくなるのだから何かもらっておこう、という思惑があったのは否定できない。そうしてA子は、そんなやりとりをした後日、本当に自分の使っていた国語の教科書を3冊持参してくれた。
*
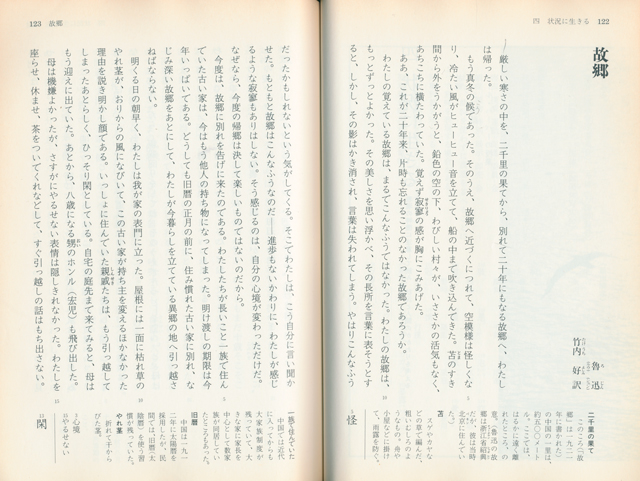 |
| 【教科書に載っていた魯迅「故郷」】 |
私がいま、手に取っている教科書の表紙は洋画家・島田章三氏の油絵で、国語教科書としての凜とした佇まいを自然に醸し出している。多少、古びてきてはいるが、しっかりとした体裁はもらった当初とほとんど変わらない。
本の中は所々、というか部分的には凄まじい量で、A子が記した鉛筆の痕跡が残っている。実によく勉強していたのだなと思った。漢字の学習のページにはきちんと空欄に的確な漢字が埋められており、読み仮名をふるところはほぼすべて、漢字の右脇にひらがながこまかく添えられていた。
その他、テクストに書き込まれた傍線や囲み線、段落番号、重要な箇所の丸囲み線もあちこちあって、益々感心した。にもかかわらず、教科書の後半の古典以後のページには、ほとんど何も附されていないこと――ちょうど3学期で高校受験や卒業準備で忙しく、通常の授業をろくにおこなわなかったのだろう――も逆説的に彼女が残した痕跡であって、この教科書がいまも窺える、実直で生々しい中学生活の記録であることを裏付けている。
魯迅。中国近代文学の父。
彼の作品「故郷」は、主人公が20年ぶりに遠い故郷を訪れた際、懐かしい少年時代の友と再会した挙げ句、変わり果てたそれぞれの立場とその状況に打ち拉がれ、かつての親しい関係にはもう戻れなくなった《現実》の、重苦しい寂寥感が漂う秀作だ。
これに倣えば、私にとっての“故郷”は、小劇団の在りし日の稽古場であろう。仮に、万が一、A子と数十年ぶりに再会することがあるとしても、当然あの時の関係には戻るわけもなく、戻るべきものでもなく、ただただその長い年月を経た《現実》に茫然と向き合うしかないのだけれど、確かにあの時、A子とは――私が劇団を辞めた直後――少しばかりの対話的格闘があった。
特に傷つくのをためらったのは、むしろ私の方であった。その対話の最後の最後の末尾に、当たり前に添えるべきだった私なりのA子への感謝の念すらも、傷つくのを怖れて口に出せなかったことは、今更悔やんでも悔やみきれず、大きな過誤であった。
魯迅を読むために開いた国語教科書は、私の所有物である。しかし、ふわりと宙に浮かんだままの、不完全な所有物である。そんなような気がしてきた。これは魯迅の「故郷」における寂寥感とは、かなり違った意味合いの瑣末であるかと思われる。
関連記事


コメント