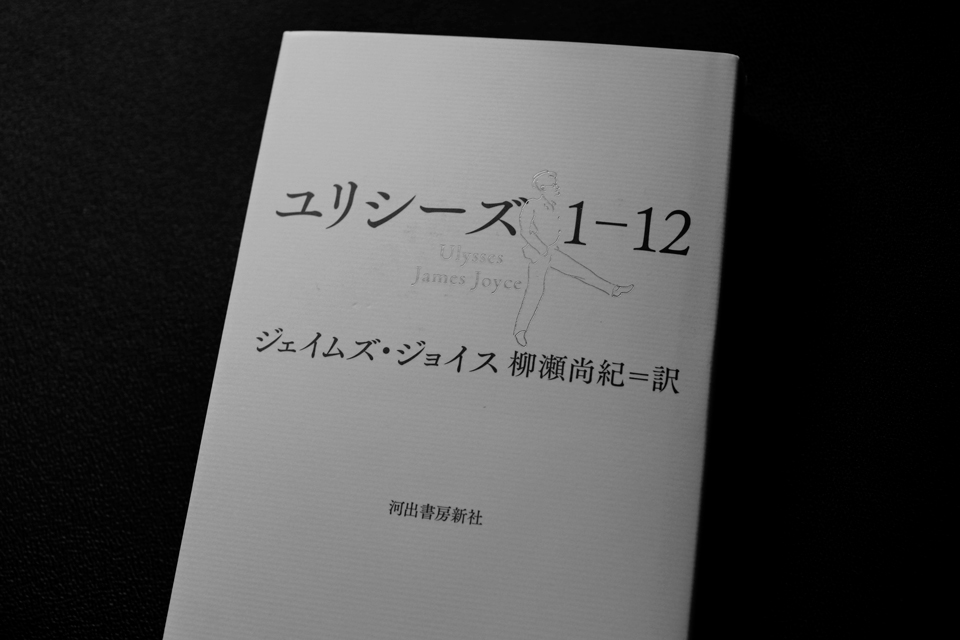 |
| 【柳瀬尚紀訳ジョイス著『ユリシーズ 1-12』】 |
今年の2月、新聞の文化面の書評記事で作家の円城塔氏がこんな書き出しをしていて思わず目に留まった。
《まだまだ小さかった頃、同じ本に複数の翻訳版があることに戸惑いを覚えた記憶がある。言葉を正確に翻訳すれば、訳文は同じになるはずではないかと素朴に信じていたらしい》
(朝日新聞朝刊2月5日付より引用)
《まだまだ小さかった頃》に、《複数の翻訳版があることに戸惑いを覚えた》経験を、私は同じ“小さかった頃”に、していない。それ以前に、「外国の本を日本語に訳している」本の体裁そのものに、私は疎かった――。
自分の住んでいる国の外側に、余所(よそ)の国があるということを概念的に知ったのは、随分後年だったのではないかと思う。幼年時代にほとんど原初と言っていい、大人が読み聞かせてくれた「外国の本」が、私にとってルース・スタイルス・ガネットの名作『エルマーのぼうけん』であった。この『エルマーのぼうけん』か、ヘレン・バンナーマンの『ちびくろ・さんぼ』かどちらかが、私にとって最初の「外国の本」だったのだろう(もちろんそれらは日本語に訳されていた)。少なくともこの幼年時代において、それらが「外国の本を日本語に訳している」本だという認識を、持ち得ていなかったはずだ。
小学校に入ってから、図書室という狂おしくときめきの場所に居座り、翻訳された「外国の本」に多く接する機会があったけれど、やはりそこでも、《複数の翻訳版があることに戸惑いを覚えた》経験はなかった。ましてや翻訳の優劣で文章が変容し、事柄のニュアンスが変わってくるなどとは露程も知らず。まだ幼くて稚拙な日本語しか話せない自分には、訳された内容云々を言及するだけの能力が無かった(他の子供達は、そういうことに気づいていたのだろうか)。図書室に置かれた本に対する、ある種の敬愛心から来る礼儀として、本に対してケチをつけることへの「おこがましさ」があったのかも知れない。
§
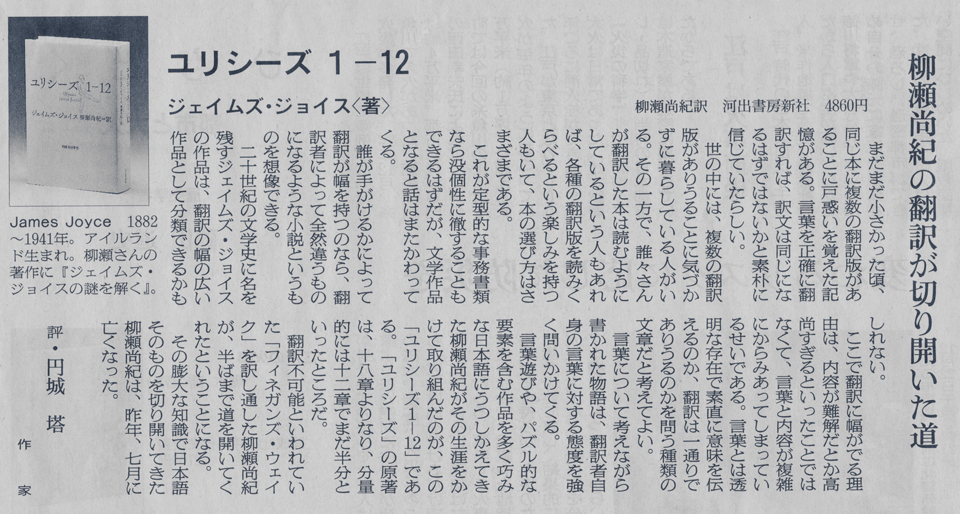 |
| 【朝日新聞朝刊2月5日付、円城塔氏の書評】 |
こんなことを書いたら怒られるかも知れないが、児童書の翻訳版で、例えばその頃読み親しんだジャン・アンリ・ファーブルの『ファーブル昆虫記』を、岩波文庫版で読みたいとは思わない。あるいは『エルマーのぼうけん』が文庫版になっていたとしても、そちらで読み返したいとは、決して思わない。
子供の頃に親しんだ児童書には、思い入れと言うには少し大袈裟であるが、児童書なりの良き体裁というのがあるように思う。画や図柄などで色彩豊か、しかも字が読み易く、手に取った時の感覚がまるでエーテルで酔わされるような気持ちの良いもの。本の中のお伽の世界や夢の世界にどっぷりと入っていける装幀の魅力――。『ファーブル昆虫記』や『エルマーのぼうけん』をたとえ大人になって読み返すにしても、その頃まったく無縁だった岩波文庫のような体裁で読みたいとは、思わない。これは理屈ではないのである。
ジェイムズ・ジョイス(James Joyce)の“ユリシーズ”(Ulysses)で、翻訳版として最も体裁良く、それこそ子供の時分に出合ったような書物に対する興奮を味わえたのが、柳瀬尚紀訳の『ユリシーズ 1-12』(河出書房新社)であった。まことに残念なことに、柳瀬氏は昨年の7月に亡くなられた。だからこの本は12章で終わっている。
彼の翻訳によるジョイスの『フィネガンズ・ウェイク』(河出書房新社)は傑作中の傑作として知られるが、『ダブリナーズ』(新潮文庫)の方もなかなか面白い。アイリッシュ・ウイスキーを時折嗜み、アイルランド好きな私にとってジョイスは、言語を超えた地理的文化的教養的指針であり、また柳瀬氏の翻訳による目眩く日本語の豊かさ、面白さ、アナグラムやパズルのたぐいが鏤められた文体の活き活きとした躍動感、それに鼓動を高鳴らせている私は今、とても充実した読書を経験したと感じている。
そう、一応、『ユリシーズ 1-12』を読み了えたのである。ジョイス文学の読み手としては赤子同然であるが、ジョイスの奥深さを柔らかく親切に説いてくれているのが、柳瀬氏の『ジェイムズ・ジョイスの謎を解く』(岩波新書)だったりもする。ともかく、彼の巧い翻訳の手にかかれば、こなれているはずの日本語が、これほどまでに日本語的でなくなるのかという妙な感動を覚えるのだ。読書の「リア充」というやつである。
翻訳版を照応していてそれなりの発見というのもある。私の発見は、あくまで赤子同然の初心者の愚かな発見なのかも知れないが、丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳の『ユリシーズ』(集英社)の第12章「キュクロプス」にある、
《雛鳩の肉饅頭、鹿肉の薄切り、子牛の鞍下肉、かりかりした豚のベーコンを添えた緋鳥鴨、ピスタチオの実を添えた猪の頭、すばらしいカスタード一鉢、西洋かりん入りのよもぎ菊風味プディングにラインの古葡萄酒を一瓶》
(丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳ジョイス著『ユリシーズ』集英社より引用)
が、柳瀬氏の訳では、
《雛鳩のパイ、鹿肉の薄切り、子牛の鞍下肉、緋鴨に牡豚のかりかりベーコンを添えたもの、猪豚の頭のピスタチオ添え、上等のカスタード一鉢、年代ものライン葡萄酒のだるま瓶一本》
(柳瀬尚紀訳ジョイス著『ユリシーズ 1-12』河出書房新社より引用)
となり、丸谷才一・永川玲二・高松雄一訳にあった“西洋かりん入りのよもぎ菊風味プディング”が、柳瀬訳ではすっかり抜け落ちていることに気づいた。これは一体どういうことなのか。原書を探れば分かることだけれど、ジョイスの小説ほど、翻訳の旨みの違いが出るものもなかろう。とりあえず、このあたりで筆をおろしておく。
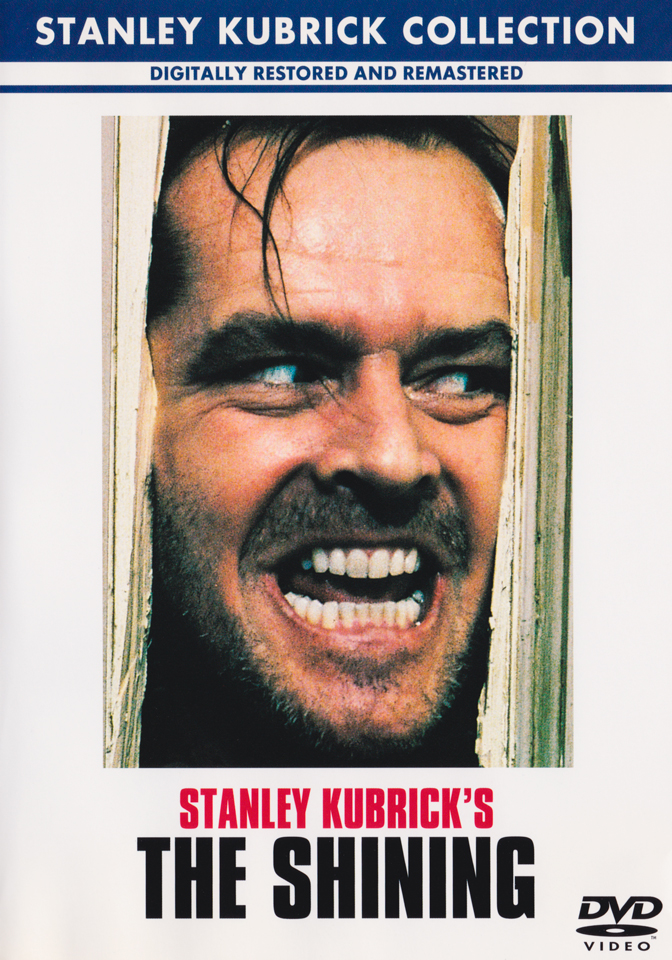

コメント