 |
| 【ロブ・ライナー監督の映画『ミザリー』】 |
若い頃に観たスティーヴン・キング原作物の映画を、何の因果か知らぬが、今頃になって頻りに好んで観ている。キング原作でロブ・ライナー監督の映画『スタンド・バイ・ミー』については既に書いた。その稿で私は映画『ミザリー』についてこう述べている。
《同じロブ・ライナー監督&スティーヴン・キング原作の映画『ミザリー』(Misery)の方が映画としては好きで、その主演のキャシー・ベイツの恐ろしいほどに温和で甘ったるい顔が脳裏に刻まれていて離れない。うっかりすると、まったく毛色の違う『スタンド・バイ・ミー』の原作者が、同じスティーヴン・キングであることを忘れるほどだ。これらの映画は実に対照的である》。
『ミザリー』は、1990年公開のアメリカ映画で、監督ロブ・ライナー、主演はジェームズ・カーン、キャシー・ベイツ、ローレン・バコール、リチャード・ファーンズワース。ちなみに、老齢のバスター保安官役を演じたリチャード・ファーンズワースが実に正義感たっぷりで格好良くジェントルマン。その妻役のフランシス・スターンハーゲンもお淑やかでおちゃめといった感じで愛くるしい。
この映画を一言で言い切るとするならば、観ている側が脂汗を垂らしながら「痛さを堪え」る映画、である。あるいは過去に忘却していた己の「痛み」をしっかりと思い出させてくれる、ありがたき、いやちっともありがたくない迷惑な映画、と言える。
§
『スタンド・バイ・ミー』が季節の夏を描いたなら、『ミザリー』(又は『シャイニング』も)は冬。スクリーンいっぱいに真っ白い雪景色が広がる。――コロラドの田舎町シルヴァー・クリークで吹雪に遭遇し、車ごと、車道に面した小さな谷間に転落してしまった小説家の男ポール・シェルダンは、全身に重症を負ったにもかかわらず、“運良く”地元の一人の中年女性に救い出される。
この映画の“幸いなる”ストーリーは、ここから始まるのだ。ポールは長い冬の間、ずっとその中年女性の家で療養生活を送ることになる。彼は死なずに済んだのだ。ラッキーな男だ。しかもこれはまさしく“運良く”と言っていいだろう、彼女は元看護師で、怪我の手当はお手の物だったのだ。
ポールのヒットセラー小説“ミザリー”シリーズの大ファンである、中年女性の彼女アニー・ウィルクスにとって、思わぬ怪我人の看病を強いられる事態でありながら、彼の来訪は又とない“憧れの有名人”との大接近となった。実にそれは熱心な、手厚い看護であり、脚を大変負傷してベッドの上で身動きの取れないポールに対し、優しく温かく、大作家に対する敬意を払いながら、《対話》という手段で心を和ませていく。ポールはまさに九死に一生、雪で閉ざされしばし病院への搬送が遅れるにしても、この家での怪我の応急処置による療養の専念は、彼にとって少なからず安楽の期間となるはずであった。そう、そうなるはずであった――。
ポールにとってラッキー・デーはここまでだ。はいおしまい。彼はまだ何も知らない。ポールは、小説“ミザリー”の熱烈なファンであり手厚い看病をしてくれているアニーに、ささやかな、とてもキュートなprivilegeを与えた。それは、書き終えたばかりの新作の原稿を、自由に読んでもいい権利。
有頂天になったアニーは興奮冷めやらず、日を追って新作の原稿を読み始める。やがてその原稿を読み終えたアニーは、不満げな様子だった。ポールにとってそれは、まったく新しい予期せぬイベント=アクシデントであった。言うなれば、人生の画期的なアンラッキー・デーだった。
原稿を読んだアニーの感想は、それが下品で言葉が汚らしく、好きになれない作品らしかった。ポールは寝たきりの状態でありながら、真摯な態度で彼女と向き合い、アニーのそのちょっとした“誤解”を解こうと、作品を説明する。しかし、アニーは納得いかない。彼の説明に対し、まもなく熱が上がって逆上発狂する。汚い言葉を発しながら――。こうしてポールが思い描いていた(かも知れない)天真爛漫な中年女性アニー・ウィルクス像は、もろくも崩れ去る。
ポールは思ったはずだ。テンシンランマン? イノセント? とんでもなーい! ちーがーうーだろー! 彼女はショウシンショウメイ、イカレポンチのクレイジーオンナだ! まいったまいった。ニャロメ、こんなところで長逗留していたら、一体何をされるか分かったもんじゃないぞ! うーん…イカレ! ポンチッチー!
これはこれは、大変なことになりました。わたくしは大変なところに来てしまったのでございます。早くここから、アニーの傍から離れなければなりません。さもなくば、わたくしは殺される。アニーに。名評論家アニー・ウィルクス女史に。早くこの家から脱げ出したいのです! どうか神様、お救いを――。
§
さて、このあと何が起こるというのだろうか。何が彼の身に降りかかるというのか。もはやラッキー・ガイではなくなった流行作家ポール・シェルダンの、痛くて痛くて仕方がない両脚を堪えての、文字通り七転八倒の“トライ”が始まっていく。
そう、人生は何事も“トライ”だ。私たち日本人は、昭和の時代から、アメリカ映画を観て育った。アメリカ映画とはなんたるや。それはつまり、人生への“トライ”であり、ある意味におけるフロンティア精神の啓蒙である。個人が積極的に行動し、人民の愛と正義のために戦う。その思想はキリスト教プロテスタント信仰と深いかかわりがあるのかどうか、私はそれに詳しくないから、断言しようとは思わない。だがアメリカ映画の基調は、日頃彼らがたとえ飲んだくれであったり、女たらしであったり、あるいは男(父性というもの)に不信感を抱いている女性であったとしても、事と次第によっては人格が豹変し、そうした思想や精神のもと、喝采を浴びるヒーローやヒロインとなって、人々のために戦ってくれる勇気と希望の象徴の活劇であった。邪悪さや侵犯に対する正義、そして愛という名の包容、ロマンス。物事を良い方向へと変えていこうとする自意識=良心の呵責の働きは、少なからず利力となって第三者を救う。救いの道が開かれる。
ポール・シェルダンにとって脱出への“トライ”は、惨劇の日々の繰り返しと同義であった。アニーは強敵である。なかなか思うようにはいかない。思うようにいかないどころか、よりいっそう、「痛み」が増してくる。敢えてまだこの映画を観ていない人のために、その具体的な内容を書くことは避けるけれども、ポールはこの家で地獄を見つつ、作家として新しい小説作品を書き上げるのである。これは唯一と言っていい、そこでの地獄の生活の中でたった一つ許された(というか強要された)快活的な行為(禁欲的な生活でセックスという自由を突然与えられたかのような快楽)こそが、「書く」ことであった。ポール・シェルダンは「書く」ことで己の未来をつなげた、ベン・ハーである。
いずれにせよ、この映画を観る者は皆、ずっと、「痛さを堪え」なければならない。それは覚悟していただきたい。
不幸中の幸いという慣用句があるが、彼にとってこのアニーの家は結局のところ、生き長らえた先の不幸、それも地獄の底というほかはなかった、にもかかわらず、「書く」ことの意義と、最適な自己顕示手段が新しく導かれ、意志として発露され生まれ変わっていく。作家こそクレイジーではないか――という批評が、この映画には相応しい。スティーヴン・キングしてやったりの作品性が充分に透けて見える、『ミザリー』である。
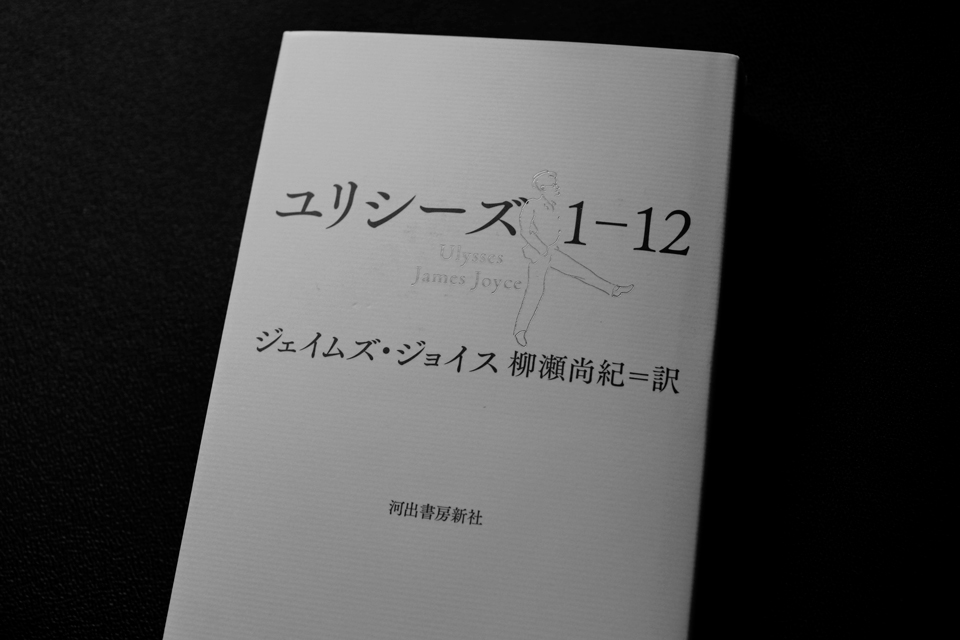
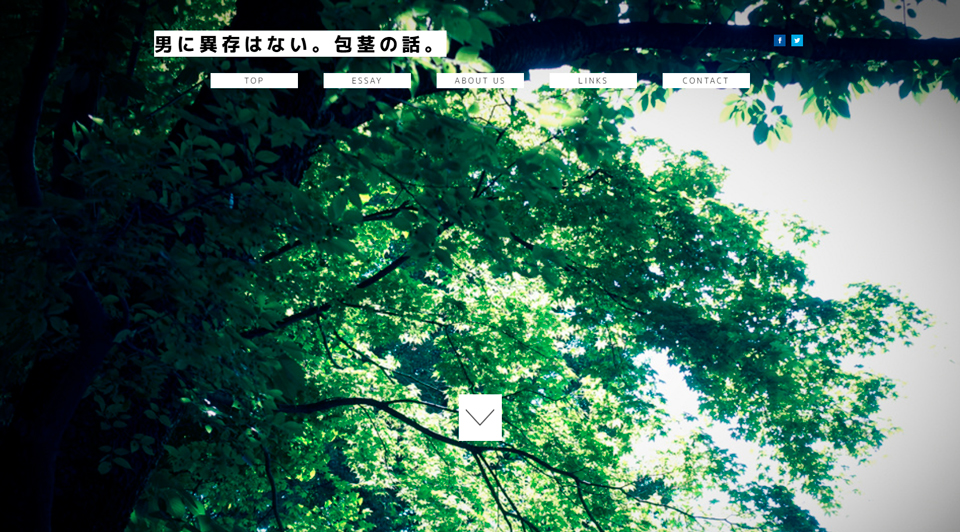
コメント