 |
| 【筑摩書房『唐木順三全集』第十二巻】 |
一つのつまらぬ行動から文学的体臭を嗅ぎ取るに至る偶然に出くわす。
あるスマホのアプリで、カメラで写した文書を画像に起こし、自動的にテクスト化してPDFにするという事務系のたいへん便利なものを試してみた。変換の精度を試すために、偶然手に取った一冊の本が、『唐木順三全集』(筑摩書房)であった。そのうちの随筆「時代相と青年の夢」は見事に画像からテクスト化されPDFとなり、他愛ない試みはここに完了した。
いま私はこれを数ページ分プリントアウトし、眺めている。眺めてから、気になる部分を赤い鉛筆で傍線を書き加える。気づけば、なかなか興味深い内容である。試しの文書が唐木順三でなくてはならなかった理由などいっさいなかったにせよ、文学への邂逅と探求心は偶然にして起床するものであることを実感して已まない。
唐木順三は戦後の思想と哲学の評論、その随筆家として私は記憶に印する。唐木の著作は高校時代の国語教科書の中の随筆「疎外されることば」以外、ほとんど読んだことがなかった(当ブログ「教科書のこと」参照)。書棚に彼の全集がわずか一冊だけ置いてあること自体、不思議なことでありつつ、読まずして彼の存在感は失われずとどめられていた。こうして不条理にして私は、今日まで唐木の本を封印していた禁を破り、偶然ながら、その「時代相と青年の夢」を読むことになったわけである。
§
「時代相と青年の夢」。“青年の夢”などという主題は、戦後文学の研究においては、伊藤整に任しておいた方がいい(当ブログ「伊藤整の『青春について』」)。むろんそれは私個人の独善的主張に過ぎないが、この随筆が昭和26年12月の『學苑』に所収されているという点で、文学における時代相というのはあらかじめ限定される。『學苑』は昭和女子大学発行の学校誌・研究誌のようで、詳しくはよく分からない。
前年の昭和25年(1950年)に、デーヴィッド・ハーバート・ローレンス(David Herbert Lawrence)の『チャタレイ夫人の恋人』の本(小山書店)が伊藤整訳で発行されるも、“猥褻本”であるとして摘発される。出版社社長と訳者を被告とした、いわゆる「チャタレー事件」の裁判(猥褻文書裁判)が、昭和26年5月より始まっている(第1回公判)。やがて昭和32年の最高裁の判決では、上告を棄却し、猥褻の3つの定義を挙げ、有罪が確定する。脇道に逸れるが、第1回公判の中込検事の起訴状がまことに恨めしい。以下、一部引用する。
《…人間の憧憬する美は性交の動態とその愉悦を創造する発情の性器なりと迷信し、蔽もなく恥もなき性欲の遂行に浸り人間の羞恥を性欲の中に殺したる男女の姿態と感応享楽の情態とを露骨詳細に描写…》
《…我国現代の一般読者に対し欲情を連想せしめて性欲を刺戟興奮し且人間の羞恥と嫌悪の感を催さしめるに足る猥褻の文書…》
文学界のみならず通俗において、これが“ワイセツか芸術か”で大きく大衆を揺るがしていた最中にあって唐木は、そうした潮流とは意を別腹にし、あたかも無聊を装い純朴な眼差しで、一つの小さな学校誌に“青年の夢”なる時代評論文を発表していたことに、私はその文学と時代性のほとばしる葉脈の鼓動を知覚するかのようで、興味が絶えない。「時代相と青年の夢」は、《青年は多かれ少なかれ、夢をもつ。或ひは逆に夢をもつ限り、その人は青年である》という文章から綴られる。真っ向から、かの芸術論争のエッセンスを否定しているかのようである。尤もここではチャタレイ夫人も伊藤整も何ら言及はされていない――。
先の書き出しに続き、次の巧みなレトリックによって“青年の夢”が定義される。《この場合、夢とは可能性の世界に情熱をもつということである。青年期に入って初めて現実と可能が分裂する》
(筑摩書房『唐木順三全集』第十二巻より引用)
この随筆の要点を述べれば、青年の夢が時代によってどう変わったか、今のそれはどうなのか、という二点である。まず一つは近代日本の黎明期の、子規と漱石を例に挙げ、彼らの学生時代におかれていた時代相に触れている。彼らは落第しても何でも、いくつかの趣味に没頭し、自由で拘泥がなかったと述べる。また近代日本の黎明期という時代においては、変わり者の彼らという存在を半ば容認し、そういう人達こそがむしろ様々な分野で多様な広がりを有し、功績を残した。
§
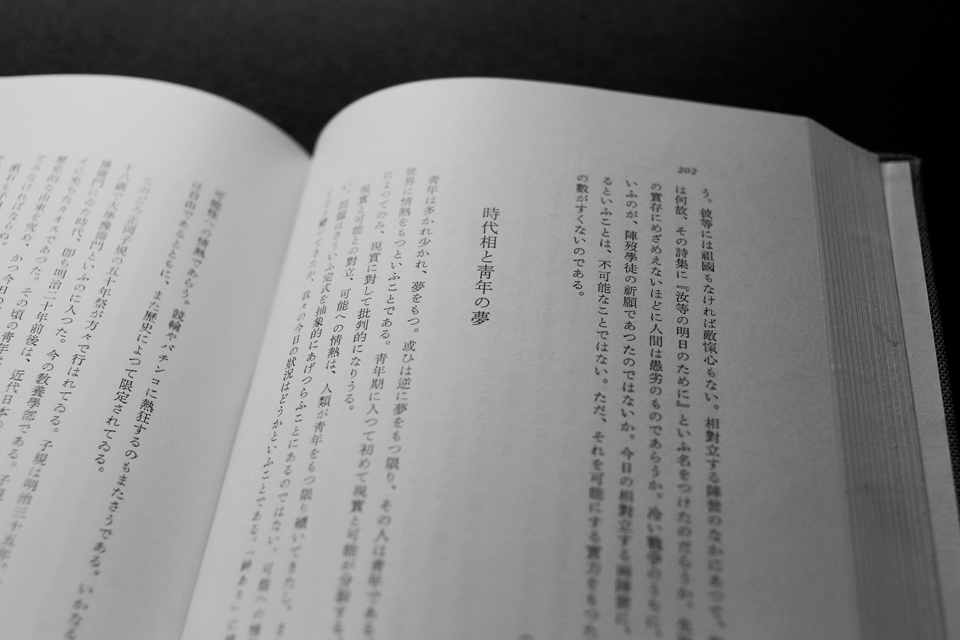 |
| 【唐木順三著「時代相と青年の夢」】 |
東京大学がいつ頃から、官吏養成所的な色彩を帯びてきたか。日露戦争後、日本の資本主義経済の発展は、国家の強権の庇護のもと、それに見合う指導者を存分に求めた。唐木は、こうした時代の推移の背景によって、国家が官僚的機構の確立を促し、その結果、法科工科の“メカニックなサラリーマン”が大量に養成され、いわゆる変わり者の学生を疎外する仕組みが社会に培養された、という意味で、時代の変化を客観的にとらえている。これを固定化した、こうしたことを月並み化した社会機構、とも称している。
しかし若者は、そうしたがんじがらめの社会機構の中においても、自らの変わり者としての発憤の火種を、夜の時間の自由に求め、唐木はその一つとして「肉体の探求」を言い表した。ところがここでは当然のようにこまやかな言及は避け、例として“スポーツにかける夢”という方向を提示し、思想的な身の危険から脱する。健全たる“スポーツへの夢”という論説も決して悪くはないが、いずれにしても唐木は、その「肉体の探求」の本来の意味性から大きく舵を切り、決して伊藤整に倣わない。
“スポーツへの夢”を例に挙げたのち、さらにもう一つの例として挙げているのは――これがこの随筆の結着になっている――「海底探索」である。
カイテイタンサク。“青年の夢”、その溢れんばかりの若者のエネルギーの捌け口である「肉体の探求」の著しい飛躍が、唐木にとって「海底探索」であった。この結着に私はしばし唖然としてしまった。いくらなんでも「海底探索」とは――。
むろん海底の世界は謎であり、その世界を探検することは、昭和26年のあの時代、若者にとってあるいは日本という国家においても、大きな飛び立ちの可能性を秘めていたことを、私は否定したりするつもりはない。しかし、この最後の結着における「肉体の探求」の著しい飛躍=「海底探索」は、何たる無残、いくら格式高い学校誌への随筆とは言いながら、伊藤整の純然たる諍い事に比べれば、屁のような論考ではないかとも思われる。
随筆の結びでは、《人間の内心の自由に無限の信頼をおいたのがキリスト》という言葉をいみじくも投げかけ、まとめている。
他方、幾分危険で破廉恥な、まかり間違うととんでもないことになるという命懸けの変わり者――あの猥褻裁判の当事者――に対する唐木の真心から来る擁護、それがキリストであった。
何度も言うように、この随筆では一言も猥褻裁判について言及しているわけではない。私の穿った見方である。しかしながら、唐木がその時そのような意思によって伊藤整に対して間接的に働きかけたと見る方が、妥当ではないか。――わたくしは美しい浪漫あるカイテイタンサクを今日の“青年の夢”として後押しますが、いかがでしょうか。いいでしょう。いいに決まってるでしょう。あなたはどうか、戦後自由主義における新しい芸術勃興の先駆者として、その「肉体の探求」なる課題を、文学の隅々にわたる美と完全無欠となるまで、頑張ってくださいね、ご健勝を祈ります――といったふうに。


コメント