 |
| 【mas氏のウェブ「中国茶のオルタナティブ」】 |
およそ6年くらい前、私が音楽活動(ソロ・プロジェクト[Dodidn*])をウェブ上で新展開するにあたり、ホームページやブログをlaunchするうえでたいへん参考にした“個人サイト”というのがある。mas氏の「mas camera classica」である。mas氏とはまだお会いしたことはないが、もともとクラシック・カメラ愛好家でサイト・オーサーである彼の多趣味な活動は、むしろ雑然とした部分がなく一貫した信念で築かれた、言葉の流麗さに惚れ惚れとすることが多く、どこか異国情緒を漂わせる方であった。現在、そのサイトはない――。なかでも、彼の趣味の一つである「中国茶のオルタナティブ」は、知的な文章に鏤められたサブ・カルチャーの精神性の襞を感じさせた。
§
mas氏のことと、それら“消えたサイト”については5年前、当ブログ「中国茶とスイーツの主人」で書いた。そのうち、消える直前に密かに私がデジタル・アーカイブしておいたウェブページがあり、それが「中国茶のオルタナティブ」なのだ。
もしその時、アーカイブしていなかったならば、そのアーティクルの中身も、私が熟読玩味した記憶すらも忘れ去っていたであろう。非常に奇跡的なことである。最近、漱石の“ロンドン留学日記”を読み返している時、頻りに漱石が茶(Tea)を嗜んでいるのに感化され、私は今になってmas氏の「中国茶のオルタナティブ」を思い出した。そうしてアーカイブしたアーティクルを5年ぶりに開くことができた。
サブ・タイトルを“日本人として中国茶を楽しむということとは何か?”としたmas氏は、そのウェブページを2000年2月から2001年1月まで更新。12のエッセイによって構成していた。中でも特に、その四の「湯相、新たなる聴覚の快楽へ」が興味深く、ここでその内容を紹介することにする。
「湯相、新たなる聴覚の快楽へ」。サブ・タイトルは「湯相、湯の音を楽しみ、泡の形状を楽しむということ」。
冒頭でmas氏が書き記しているとおり、茶の湯では「湯相」(ゆあい)、煎茶道ではそれを「湯候」(ゆごろ)というのだそうだが、茶を淹れる際、湯の温度を感覚的にとらえるには、湯の音を聞けばいい、という話題である。これが実に奥ゆかしく、風情があって面白い。
ちなみに『日本国語大辞典』(小学館)で「湯相」を引くと、《茶道で、湯加減のこと。釜の煮え音で判断される》とあって、「湯相」は湯の案配を感覚的にとらえる旨ということになろうか。mas氏はそれを、順々に追って解説しているのだ。
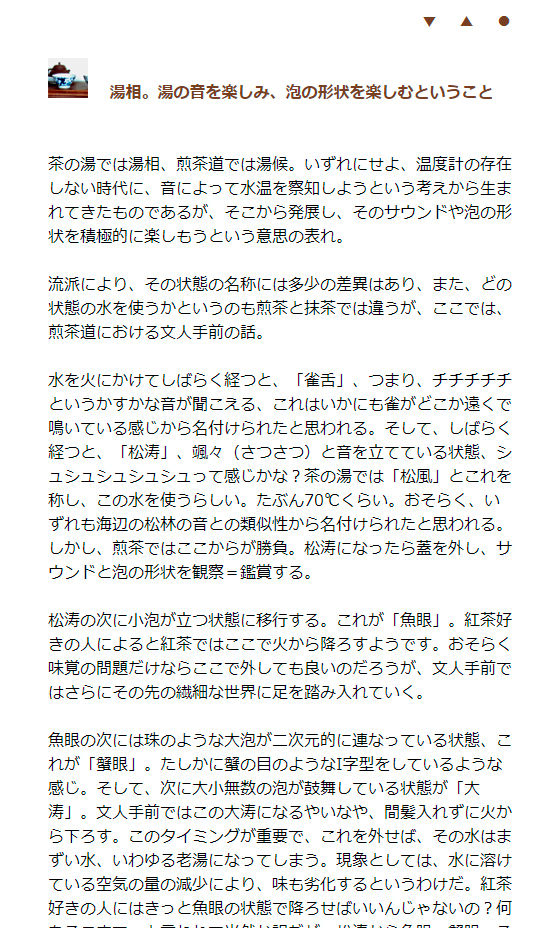 |
| 【「湯相、新たなる聴覚の快楽へ」】 |
《水を火にかけてしばらく経つと、「雀舌」》。チチチチチという音。この時の音に耳を傾けて真剣に聴き入る一般の人は、おそらくほとんどいないであろう。しかし、ここから精神世界が始まるのである(書道における墨を摺って心を落ち着かせるのに似ている)。
それから、温度が上がっていって、シュシュシュシュシュという音。これが「松涛」。茶の湯では「松風」といい70度くらいと称す。どちらも《海辺の松林の音との類似》。私の個人的な知識では、中国茶ではこれくらいの温度は緑茶に適する。mas氏は「松涛」になったら蓋を外してさらに観察せよ、と掻き立てる。
さらに小泡が立った状態を「魚眼」。なるほど。湯から小さな泡が立った状態は、確かに魚の眼に似ている。これくらいの温度というのは、湯は70度以上であるから、中国茶においては青茶か紅茶あたりであろうか。そうして、《珠のような大泡が二次元的に連なっている状態》としているのが、「蟹眼」。もはや言わずもがな。《大小無数の泡が鼓舞している状態》は「大涛」。沸点に達した温度を指すのだろう。mas氏は間髪入れず火から下ろせ、という。
このタイミングを外すと、ここからはまずい水、としているのが「老湯」。水に溶けている空気の量が少なく味も劣化する、とある。実に奥深い話だが、この「老湯」での茶を、経験として一度は口に含んでみるのもいいかもしれない。
§
サウンド・クリエイターの端くれとしての私が、この湯の音の案配の変化を聴いてみたいと思うのは、至極当然のことなのだ。襟を正し、気を引き締めよというのではない、その逆=安楽の精神。簡単に言えば、茶を淹れて楽しむという心。
ややもすると、猫背になってシンセやコンピューターと睨み合う時間が長くなる我々にとって、茶で身体と精神の安らぎを覚えるという心掛けは、忘れてはならないのではないか。何より、mas氏が残してくれたサブ・カルチャーの精神世界に私は酔いしれ、今後も私淑としたいところである。茶の話はまだ続く――。〈二〉はこちら。


コメント