 |
| 【新宿区立漱石山房記念館】 |
東京はうららかな日和だった一昨日、今年9月24日に開館したばかりの――とは言いつつ、それから2ヵ月以上経過しているが――「新宿区立漱石山房記念館」(新宿区早稲田南町)を訪れることができた。
振り返れば2年前の秋、新聞の記事を見て、記念館の整備計画途中で発見された屋敷の礎石が、没後改築された屋敷(1920年)のものであることが分かった云々(当ブログ「漱石山房の香り」参照)をきっかけに、今年秋(漱石生誕150周年)の開館をどれだけ待ち望んでいたことか。この2年の歳月は実に感慨深いものであった。
ところで、津田青楓が大正7年に描いた「漱石先生閑居読書之図」で見るような、木造屋敷及びその庭風景は、ここにはない。いや実際には、館内に漱石山房が復元され、記念館の窓ガラスからその特徴的な和洋折衷の平屋建ての外観がうかがい見ることができるのだけれど、あの山水画風の絵の中の長閑な風景は、あくまで津田青楓の虚構の世界であって、エッセンシャルなセザンヌの濃厚さが色めき立ったものである。しかし、庭には、「猫の墓」が遺されていた。石塚、あるいは猫塚と言いかえていい。
 |
| 【「猫の墓」遺構と没後屋敷の礎石跡】 |
これは、漱石の次男である夏目伸六氏の著書の『猫の墓』(文藝春秋新社)の装幀写真で見られるのと同じものであり、もともとは形として石塔であった。夏目家で飼われていたペットの供養塔(九重塔)は1920(大正9)年に建てられていたものの、昭和20年の空襲で損壊。現在遺っている「猫の墓」は、昭和28年に残石を積み直して再興したものだという。ちなみにもともとの供養塔の台石には、津田青楓の描いた猫と犬と鳥の三尊像が刻まれていたらしい。
§
 |
| 【弁天町に向かう外苑東通り】 |
それはいつの頃だったのか――。正岡子規が漱石と、夏目坂のある早稲田から関口を歩いた“田園風景”を今、ここでそれらしく想像することはひどく難しい。私はこの日、原町一丁目から弁天町に向かう外苑東通りを歩いて記念館を訪れた。この外苑東通りの両側の趣が、今ではすっかり都会的に洗練されてしまっているけれど、それでもなんとか、空間の雰囲気と呼べるものは慎ましやかな感じがあり、決して嫌いではない。
かといって昔ながらの風情があるとか、お洒落なショップが建ち並んでいるという極端さはなく、言うなればかなり地味な通りなのだが、もし、長きにわたって住まいを構える場所として考えてみたら、案外こんなところがいいのではないか。そう、当たり障りのない生活を、ちょうどいい落ち着き感の中で演じられるのでは…と思うのである。無論、このことは漱石山房とは直接関係のない話である。
 |
| 【漱石胸像(富永直樹作)】 |
漱石が1903(明治36)年の1月にロンドン留学を終えて牛込の矢来町の、妻・鏡子の実家で仮住まいをはじめて以来、住居を転々とし、1907(明治40)年40歳の頃の漱石がここ早稲田南町の、いわゆる「漱石山房」に落ち着くまでの煩雑とした略歴について、紹介したいのはやまやまであるが、省く。
ロンドン時代の日記を読めば分かるとおり、漱石の“転居癖”が実に神経衰弱的であったのに対し、帰国して東京着以後、よりいっそうその度合いが増し、引っ越し遍歴のいざこざがかえって複雑廻廊化した経緯などをここで箇条書きにして述べると、とても面白いのだけれど、すっかり字数が埋まってしまうのでやめる。
何はともあれ、1907(明治40)年、そもそも医院だった住居を改築して、文筆の生業の書斎としたいわゆる「漱石山房」の歴史はここから始まる。翌年には次男・伸六が生まれた。「木曜会」と呼ばれる門下生との交流は、前年の千駄木の宅から既に始まっていたが、この早稲田の「漱石山房」でいっそう活発になった。
『三四郎』とヘリオトロープについての随想は、2年前の当ブログ「漱石山房の香り」で既に書いた。今でも私はその香水を、相も変わらず、時折部屋に充満させる。漱石本人が山房にて、執筆の際にヘリオトロープを嗅いだであろうことを想うために。実に辟易とするくらい甘ったるい香りである。漱石…三四郎…いや、“美禰子コロン”と呼びたい。
山房づくしで言えば、橋口五葉作の、1行19字詰めの漱石山房原稿用紙はあまりに有名であろう。この原稿用紙で、絶筆となった『明暗』までが書かれた。記念館で再現された書斎の机には、この原稿用紙が今か今かと主人のインクが落とされるのを待ち焦がれているように据え置かれている。――未完の『明暗』の続きを書くべく、漱石がこの世に舞い降りて、しばし腰をおろしてくれるであろうか。今でもここは、漱石にとっての閑居、安住の地に違いない。多くの人がここに訪れて、漱石の世界観を味わってくれることを私は願う。
さらに漱石の話は、こちら。
さらに漱石の話は、こちら。

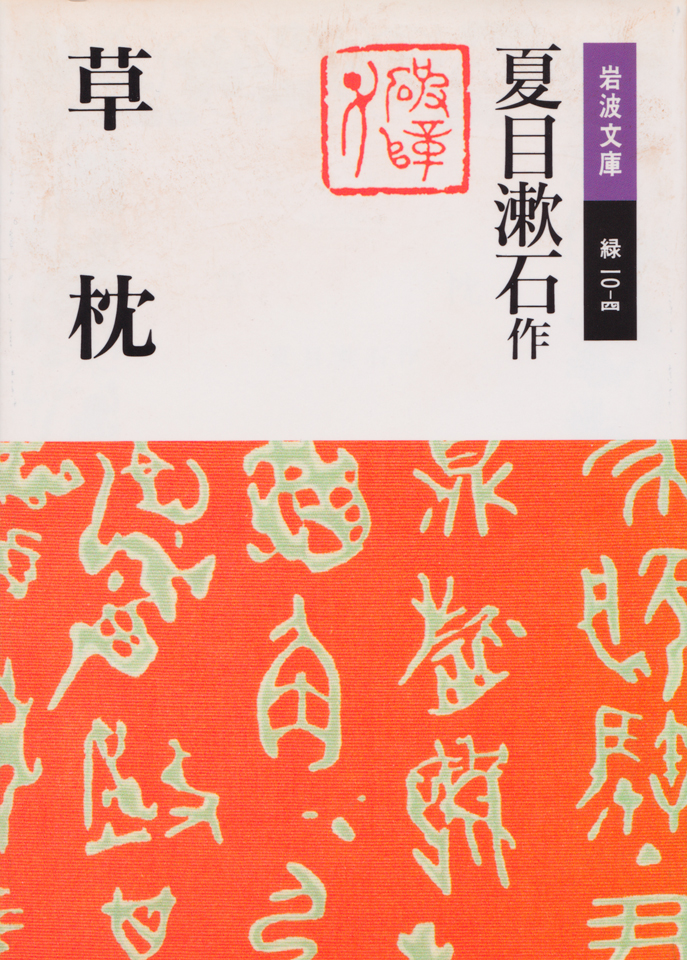
コメント