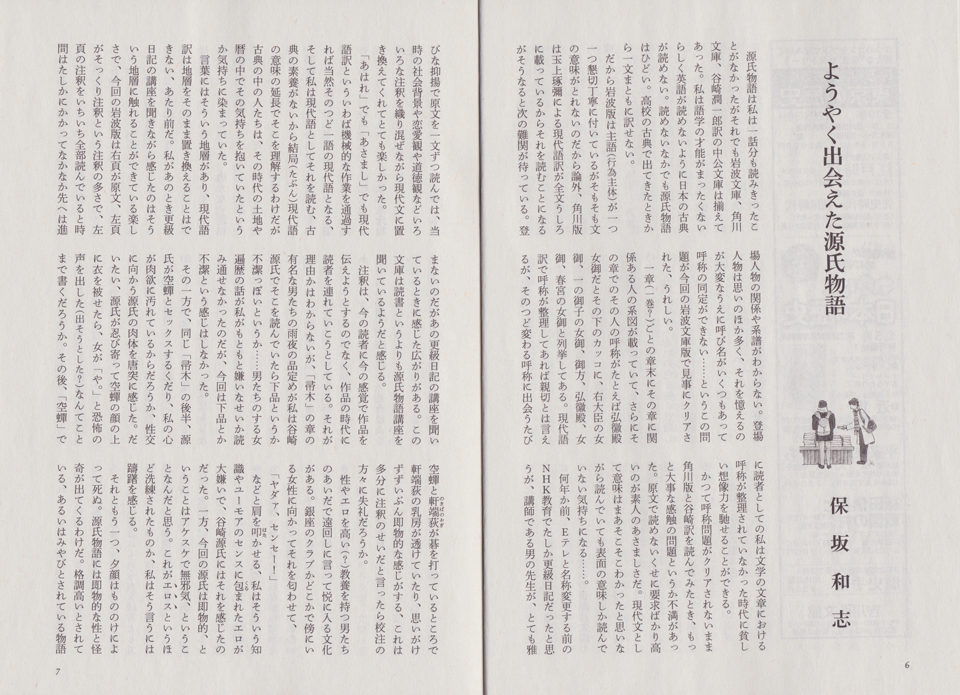 |
| 【12月号『図書』保坂和志「ようやく出会えた源氏物語」】 |
今年はのっけから本が増えて増えてならないのだ。自宅の蔵書が書棚に収まりきれず溢れかえり、あちこち本の塔(まるで卒塔婆のよう)ができて居処を狭くし、煩わしい。しかし、読みたい本が目の前にあるという充足感は格別。諸刃の剣でいずれにしても読書というものは、蔵書が“増書”となり、行き過ぎると“毒書”ともなる。
昨年は春から夏にかけて、ジョイスの『ユリシーズ』をかじった。かじっただけなので、読後の達観した気分にはならなかったが、連夜読み続けていたその頃、1巻だけでも厚みのある『ユリシーズ』が寝床の傍に3巻も並べられ、さらに隣に『フィネガンズ・ウェイク』が2巻置かれていた。そうなると、かなり手狭となって、これまたひどく分厚い柳瀬尚紀訳『ユリシーズ 1-12』(河出書房新社)を読み出したりすれば、もはやジョイスの本に囲まれた私自身の身体は、狭い窮地に追い込まれた小動物である。この点、巨人ジョイスに隷従した身と言っていい。
それほどの長編小説は懲りて、もう読まないようにしている。にもかかわらず、昨年末、保坂和志氏の些細なコラムを読んだのをきっかけに、紫式部の『源氏物語』にすっかりはまってしまった。これがまた言うまでもなく、大長編である。そうして収まりきれない本が、蔵書が、またしても増えてしまったのだ。いかんいかん…。
確かその前、秋だったと思うが、古書で『日本国語大辞典』全10巻を買い込んだ。これはなんとか書棚を整理して全巻押しくるめることに成功したのだけれど、今まさに岩波と角川とポプラ社(児童書)による『源氏物語』数冊と、絵巻関連の本と、それから瀬戸内寂聴版『源氏物語』全10巻(講談社)を揃えてしまった渦中において、私はじっくりと、この長い物語を耽読することにした。平安貴族の幽玄の世界に浸り、悦楽の気分を味わうために。
§
『源氏物語』の文体の、その美しくも儚く、時に性的で艶やかな「言葉」の秘めたる鼓動を、なんと驚きをもって表現すれば良いのか。これがいにしえの、平安朝時代に書かれた読み物ということに対する純粋な感動。そこには、まどろんだ一昼夜の風雅にたたずむ男女らの交錯と、あれやこれやの大人びた人間模様の連鎖が記録されているのであり、私はそのことの発見に何度溜め息をついたことか。
岩波書店のPR誌『図書』12月号の保坂和志著「ようやく出会えた源氏物語」を読むと、新しく刊行された岩波文庫の『源氏物語』(第一巻桐壺―末摘花、第二巻紅葉賀―明石)がすこぶる実用的で、著者が既刊の旧岩波版、角川版、谷崎潤一郎訳の中公文庫版などと比較対照に熱心であって、なおかつ新岩波版における注釈や各々の解説の記述の巧さが、読者を《作品の時代に連れていこうとしている》などと述べられていたりして、私自身も今回初めて『源氏物語』なるものの面白さに気づくことができた。保坂氏のおかげですっかり、その深みに嵌まって抜けられなくなってしまったわけだが、悠久の日本人的情緒のこまやかさに触れ、それが文学となった時の絶大な効果に、あらためて「日本語」の奥深さを知ったのである。
敢えて一つ、保坂氏のコラムでの論点を書き出すとする。
《現代の書き手は心の赴くままに書いているつもりでも読者が平安時代のように限定されていない、それゆえいま書いていることが何なのかを読者に対して「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」という5W1H的に明確にしなければならないという意識がつねに働くのがじつに煩わしい。今回の注釈を見ても主語はいつも敬語によって特定可能なわけでなく文脈から知られるようになっている例も少なくない。客観記述が心内叙述に移行しているという注の指摘に会うと、自在さにうらやましくなる》
(岩波『図書』2017年12月号・保坂和志「ようやく出会えた源氏物語」より引用)
『源氏物語』における主語の省略、あるいは例えば弘徽殿の女御、右大臣の女御、一の御子の女御、御方、弘徽殿、女御、春宮の女御と呼称の表記が変わることに対し、著者は現代の書き手が成立させた「《呼称の不統一》の回避」から解放された自在さがかつてはあった――このような主語の省略は書き言葉よりむしろ話し言葉に近い、ということを述べている。もちろんこれは、かつて読み手が限定されていたことを踏まえなければならない。
こうして今、現代語訳による複数の既刊本によって理解しやすくなった『源氏物語』の、その文学的な中身云々については、ここではこれ以上言及せず、別稿に委ねることにする。あまりにも長くなるから。
 |
| 【子供の頃に読んだ『源氏物語』】 |
思い返せば小学生の頃、ひそかに買い求めた一冊の児童書――ポプラ社の古典文学全集『源氏物語』が私にとって最初の接点であった。その本は現代語訳のうえ、編集者(塩田良平)の文体的脚色が色濃く反映された内容になっているのだが、大人になって読み返してみると、これがじつに味わい深い。ただ、逆に、児童書でありながら小学生だった私がまったく読みきることができずに挫折した理由の一つは、やはり『源氏物語』特有の(あるいは古典特有の)、《呼称の不統一》からくる古語の現代語訳の難解さと、平安貴族に対する根本的な興味の薄さであった。
ポプラ社の古典文学全集は、小学生が噛み砕いて読むのにはかなり難しいけれど、中高生ならなんとかなる、という気がしないでもない内容だ。今になってもう一度この本を読んでみようと思ったのは、長年心の奥底に棄てられていた欲求が脈を打って甦り、大人の魅力としての『源氏物語』を味わってみたいと思ったからである。壮年過ぎ大志を抱く――。『源氏物語』はともかく面白い。


コメント