 |
| 【アイリッシュのタラモア・デューと向き合い束の間の休息】 |
私がウイスキーの酒を好んでいるのを、このブログで何度も書き綴ってきている。枚挙に暇がないくらい。そうして過去に記録してきた箇所を拾い読みし、掻い摘まむと、なんと8年前まではまだ、アイリッシュ・ウイスキーとやらを私は嗜んでいなかったらしい(当ブログ「愛蘭土紀行」参照)。その何気ない客観的な事実に、私は震えた。何故なら、《永遠》に近い時間の中で、アイリッシュとずっと戯れていたかのように錯覚していたからだ。愚かなる自分がそこに佇んでいる。
§
この夏、村上春樹の『アフターダーク』(講談社文庫)を読み始めようかと悩んだ。が、諦めることにした。贅沢を言えば、もう少しゆったりとした時間が欲しい。それが今は叶わぬから、いずれ機会をみて、じっくりと読むことにしよう。
ところがしかし、読みかけの、冒頭での小説のやりとりが色濃く印象に残ってしまい、それがとても謎めいていて、“有り余る好奇心”の捌け口にほとほと困ってしまった。頭の半分が『アフターダーク』に浸かりきってしまっているのである。
結論としては、ここぞとばかりにアイリッシュを飲んで、気分を変えるしかなかった。タラモア・デュー(Tullamore Dew)の救護である。
アイリッシュ・ウイスキーのタラモア・デュー。この酒が誕生した歴史とその寓話なるものをごく微量に簡単に述べるとこうなる。
アイルランドの首都ダブリンから西、オファリー州のタラモアの町の大きな運河の近くに、1829年、ウイスキーの蒸留所が建てられた。その68年後の1897年に、銘柄タラモア・デューが生まれる。酒の開発者ダニエル・エドモンド・ウイリアムス(Daniel Edmond Williams)の名と、タラモアの“露”(=Dew)の意をどうやらもじったらしい。現在そこは、ヘリテージ・センターとなっていて、歴史資料館としての役割を果たしている。
かつてアイリッシュ・ウイスキーは苦境の時代があり、タラモア・デューの生産は1960年頃、アイルランド南部の町コーク(Cork)に程近い、ミドルトン蒸留所に移った。その旧蒸留所の建物も、やはり今はミュージアムとなっていて、最盛期の堅牢な趣を感じさせる。――タラモア・デューの琥珀の液体を口に含めば、実にアイリッシュらしいブレンデッドのまろやかさが口の中に広がり、いにしえの伝統の風雅と気品を想わせる。私の場合、アイリッシュ・ウイスキーの中で最もよく好んで嗜んでいるのが、タラモア・デューなのである。
§
その小説における、深夜のファミレスの描写を、アイルランドの――例えばディングルあたりのパブに見立てる――ことは、荒唐無稽的に無理かと思われるが、『アフターダーク』の冒頭の印象は、私の頭の中でなかなか消えてくれない。
20歳に届くか届かないかくらいの若い女の子がそこに居て、ある“知り合いだった”男と出会う。男はなれなれしく女の子に話しかけてくる。彼はトロンボーンの入った楽器ケースを持っていた。バンドをやっているのだという。何故トロンボーンなのかというと、中学生の時、カーティス・フラーの『ブルースエット』(Blues Ette)のLPをたまたま買い、両方の目からうろこがぼろぼろと落ちるような体験をしたから――。
「Five Spot After Dark」である。中学生くらいならどう考えても、この「Five Spot After Dark」のフラーが奏でるトロンボーンやベニー・ゴルソンのテナーサックスに耳を傾けるに違いないのだ。が、しかし、これは本当の話、私は、かなりひねくれているようで、「Five Spot After Dark」の曲で、トミー・フラナガンのピアノやジミー・ギャリソンのベースの方に集中して聴き取ろうとするのである。
つまり、フラーやベニー・ゴルソンがオモテで悠々と歌い上げ、聴衆がしんみりとそれを聴くであろう、そのウラで、私は、トミー・フラナガンやジミー・ギャリソンがこっそりと何をしているか、何を企ててその一曲を構成せしめんとしているかを、そばだてて聴くのである。嫌味な耳に思えるかも知れないが、音楽を聴くとなると、ほとんどそんなような態度なのであった。
ともかく、『アフターダーク』の冒頭、女の子はファミレスの中でその男と別れるのだけれど、その時店内に流れているのが、バカラックの「The April Fools」なのだ。このちぐはぐさをなんと表現すればよいか。映画表現に喩えると、これ自体がコントラプンクト(Kontrapunkt)である。
アフターダーク――。私は頭を悩まし、蜃気楼のようにぼんやりと漂う地平の境界線やら輪郭線やらを見失ったまま、結局は心理的に落ち着かんとするため、タラモア・デューのそこはかとない伝統の風雅に頼る以外、他に方法はないのであった。
§
 |
| 【村上春樹著『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』】 |
村上春樹とタラモア・デューを直接的に結びつけるもの、と言えば、彼の『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』(新潮文庫)である。スコットランド及びアイルランド紀行であるこの本については、一昨年前、既に書いておいた(「ラフロイグのスコッチ」参照)。
そこではセロニアス・モンクの話ばかりでまったく触れられていなかったけれど、著者である村上氏が当該の旅行で寄ったアイルランド中部のロスクレアの、あるパブにおいて、ブッシュミルズを注文した後の話――つまり、その本の後半部となる「タラモア・デューはロスクレアのパブで、その老人によってどのように飲まれていたか?」――における70歳くらいの白髪男の登場――が謎めいていて非常に面白く、こちらがアイリッシュを飲んでいるとつい、その本を思い出して開きたくなるのである。
些か、村上春樹らしい文章として気に入っている箇所があるので、それを以下、引用してみる。
《パブというのは、なかなか奥が深いところだ。いうなれば『ユリシーズ』的に奥が深い。比喩的に、寓話的に、フラグメンタルに、総合的に、逆説的に、呼応的に、相互参照的に、ケルティックに、ユニバーサルに奥が深い》
(村上春樹著『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』より引用)
そういえばこの本には、ディングルのあるバーの中の写真がいくつかあって、そのバーのシックな壁面にブレンダン・ビーハンと『ユリシーズ』のジョイスと、オスカー・ワイルドの肖像写真が額縁に飾られて貼り付けてあるのを見た。バーに入って酒を飲めば、それらの人物をいやでも擦り込まれるのである。無言の箴言として、『ユリシーズ』を読めと。
それはそうと、70歳くらいの白髪男は、背広を着、ネクタイを締め、清潔感は程々ある。が、衣服がややくたびれている。この老人を想像するには、司馬遼太郎の街道シリーズ『愛蘭土紀行Ⅰ』の中で述べられていた文章が役立つ。
《アイルランドにあるのは、無気力、空元気、天才的な幻想、雄弁。また、家々や谷々にいる妖精、さらに自己を見出すための激しすぎる反英感情。それに過剰で身をほろぼしかねない民族主義。そのうえ、中世のようなカトリシズム、十六世紀のようなプロテスタントぎらい、それにアイリッシュ・ウィスキーとギネスのビール》
(司馬遼太郎著『愛蘭土紀行Ⅰ』より引用)
§
村上氏は、パブの中で見たその白髪男を眼窩にとらえる。そして彼がどんな男であるのかを推理し始める。ちなみにその古老の白髪男は、タラモア・デューを注文するのである。
《彼が何を考えていたのか、もちろん僕にはわからない。コードを刻むバド・パウエルの左手のリズムが、とくに晩年においてときどき遅れ気味になるのは、意識的なものなのか、あるいはただ単にテクニカルな原因によるものなのか》
(村上春樹著『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』より引用)
結局、その古老の白髪男も、またこれを読んでいる私自身も、日々の労苦の慰めのためにアイリッシュを飲んでいるのだった。ディングル半島のガララス礼拝堂とはいったい何であるか、といったことよりも、日々の休息に身を置きたいのである。自分自身にほんの一握りの慎ましやかなご褒美をやりたいと思うのである。
そうして私がいま考えているのは、ここ最近の個人的な“大きな創作物”を片付けた暁には、自己に対し、その慰労という名目で、一本の酒を褒美にやりたいということ。
むろん、その酒はアイリッシュ・ウイスキーである。銘柄は、ミドルトンの“ベリーレア”。
カネマラの12年物が2本買えてしまうぞ――といった野暮な横やりの忠告や手負いの誘惑を抑えてでも、どっぷりと“ベリーレア”に心酔してみたくなっているのだった。アイリッシュ特有の、“身をほろぼしかねない幻想”かも知れない。いや、そんな大したことではないのだ。そういう気分を楽しめるのが、ウイスキーの醍醐味である。まずは当分、手持ちのタラモア・デューを飲み干すことに専念しよう。
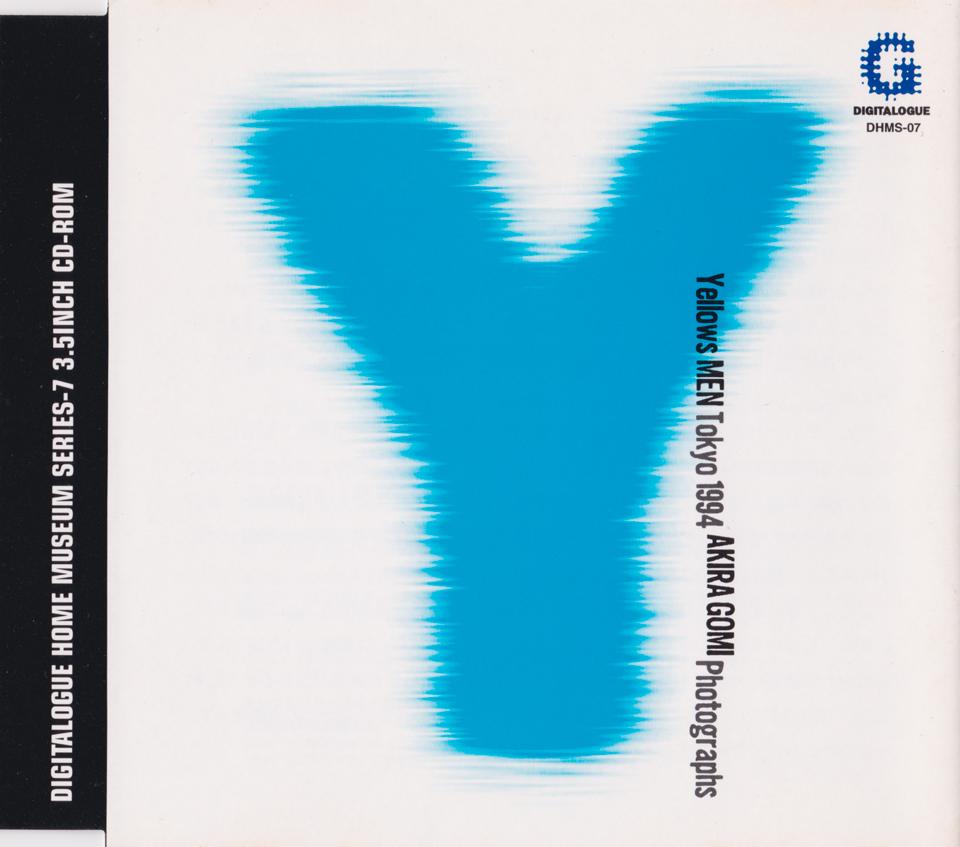

コメント