 |
| 【南雲堂の英会話カセットテープより映画『駅馬車』】 |
酒は映画を誘発し、映画は酒を誘発する――。今、私はジョン・フォード監督の1939年のアメリカ映画『駅馬車』(“Stagecoach”)を観終わったばかりだ。片手には、琥珀色のバーボンの入ったグラスが、ゆらゆらと指の中で踊りながら、室内の灰色の照明光を映し出している。映画の余韻が、この琥珀色の液体の中に、すっかり溶け込んでしまっている。
『駅馬車』。Stagecoach――。子どもの頃は只々、ニヒルなジョン・ウェイン(John Wayne)の格好良さだけに憧れたものである。駅馬車が目的地のローズバーグへ向かう途中、アパッチ族の襲撃に遭い、激走しながら騎馬の群れと壮絶な戦闘を繰り広げるシーンにたいそう興奮したのだった。アパッチのインディアンが撃たれると、激走する馬から転落するスタントがあまりにも見事だった。馬もまたたいへんよく訓練されていて、上手に美しく転げるのである。
今でもその激走シーンの興奮の度合いが劣ることはないが、むしろ今となれば、そうした迫力のシーンとは毛色の違う、大人の男と女の饒舌とつまずきと、そして人生への諦念、あるいは一つの例として、全く頼りがいのない男すなわち酔いどれ医師ブーンの、とうに干涸らびてしまったある種の純粋無垢な心持ちの困惑に――私は惹かれるのであった。そう、私は酔いどれ医師ブーンを、人間として愛してしまっているのだった。
映画を音で愉しんだ少年時代
話をいったん私の少年時代に逆戻しする。
実はこの話は、11年前の当ブログ「STAGECOACH」で既に触れてしまっている。したがって、多少話が重複するけれども、小学校低学年の頃、私は、まだ観ぬジョン・フォード監督の『駅馬車』を、ちっぽけなカセットテープの音声で鑑賞していたのだった。
主人公リンゴ・キッドを演じるジョン・ウェインの声は、どうもか細く、しかもほとんど無口に近いので、聴き込んでいない時点では、なかなかジョン・ウェインの声がはっきりと聴き取れなかった。それよりも、馭者のバックを演じるアンディ・ディヴァイン(Andy Devine)の声がやかましく、こちらの声ははるかに通りがよくて聴き易かった。しかしながらあの頃、そのカセットテープを何度も聴いた。
ストーリーの軸となる駅馬車は、アリゾナ州のトントからニューメキシコ州のローズバーグへ向かう。“訳あり”の男女を乗せた悲喜交々のエピソードを、またはあの映画史上空前絶後の迫力を生んだ激走のシーンを、英語の音声と和訳されたテクストで、何度も愉しんだわけである。確かに私はその時、西部の平原を走る馬たちのいななきを聴き、巻き上がる砂埃を生々しく脳裏に描いて夢見たのだ。
 |
| 【南雲堂の英会話テクスト本から映画のシーン】 |
ところでこの少年時代に私が聴いて愉しんでいた、南雲堂のサントラ・カセット+英和対訳シナリオの“映画&英会話”シリーズは、どうやらたくさんの名画のタイトルを刊行していたようである。むろん当時はそんなことには一切関心がなかった。しかしながら、音声のみで映画とその英会話の醍醐味を味わう、言わば語学教育的側面の濃いシリーズ商品としては、画期的であったと思われる。
その頃、姉が別の英会話の教材セット(カセットテープ十数巻)を買ったのは事実なのだが、この『駅馬車』がそこに付録として含まれていた――というのは、どうやら私の記憶違いらしい。そもそも姉は、この南雲堂の『駅馬車』を、個別に購入して所有していたにすぎなかったのではなかったか。
ともかく、これが姉の部屋の書棚に置いてあり、私はこっそりそれを持ち出して、『駅馬車』を愉しんだことは事実である。そしてまた、こうした特殊な形で『駅馬車』と向き合った少年時代の私にとって、映画を耳で「聴く」というところの味わい方は、映画のシーンを自分の頭で想像するだけに、かなり新鮮な感覚のものであった。私の少年時代の日々は、きわめて貴重な体験を残したと自負する。
英会話の教材から
酒の話は最後に取っておくとして、もう少し、南雲堂の“映画&英会話”のテクスト本について語りたい。
実は『駅馬車』テクスト本の冒頭は、田中小実昌氏の寄稿文「映画と英語と私」から始まっている。あくまでこのテクスト本は、英会話を学ぶためのものである。
この田中氏の寄稿文の中で、いくつか並べられた小見出しの一つに、“ファッキン・プレジデント”というのがある。ロバート・アルドリッチ監督の映画『合衆国最後の日』(1977年、“Twilight’s Last Gleaming”。主演はバート・ランカスター、ジョゼフ・コットン)で、大統領の親友の将軍が、「しかし、おまえはファッキン大統領なんだよ」と言い放ち、そういうふうに日本語訳にされていたセリフについて田中氏が言及しており、短いながらこの寄稿文がなかなか興味深いのだ。
言葉というのは生き物である、ということである。この将軍が放つ“ファッキン”(facking)は、言うまでもなくファック(fack)の形容詞であり、単に大統領を強調しているにすぎない。日本語に直訳すれば、“クソ大統領”ということになる。この場合、それを半熟の状態に訳し、“ファッキン大統領”としたセンスはお見事というしかない。こうした世俗的な日常会話の表現は、汚い俗語が多分に用いられる可能性がある以上に、“生きた言葉”としてたいへん印象に残る――もっと端的に言えば、心の熱量のこもった、人に伝える力を持った表現であるということである。そういった趣旨の内容が、“ファッキン・プレジデント”では論考されていて、私はこれを読んで本当に考えさせられたものである。
つまり、「映画で英会話を学ぶ」というのは、必ずしも学生向けの正統な英語教育とはならない、かも知れない。しかし、こうした日常的な会話に潜む、ある種の俗語に汚染される可能性はじゅうぶんにあるにせよ、それが“生きた言葉”であり、感情を生々しく表現したものであり、それでも尚、こうした英会話を学ぶ実践がことのほか愉しいと思えるのは、映画もしくはその言葉が、人間と共に歴史を刻み、生々しく伝えてきたもの――だからだ。このことは、映画ファンであるならば、既に経験済みだと思われるが、頭の片隅に置いておく必要がある。
 |
| 【テクスト本より平井淳史氏の寄稿「ジョン・フォードと駅馬車」】 |
平井淳史氏の「ジョン・フォードと駅馬車」
テクスト本の中で実に丁寧に、映画評論家の平井淳史氏が『駅馬車』について語り尽くしている。私はこれを、小学生の時に読んだのだった。ジョン・フォード監督の映画手法が、いかに1939年(昭和14年)の『駅馬車』のディテールとなったかについて、明瞭な解説で全体像が炙り出されている。
平井氏は、フォードの映画をこのようにとらえている。
《フォード映画は働く男への哀感がにじみでていて、そのような男への心からの尊敬と優しさをもって撮るのが特徴であり、人生の孤独、人生の道理、働くことの尊厳を十分に知った者だけが作りだせる世界なのである。言い換えれば、それは今でいう、アメリカの郷愁なのである》
(「平井淳史「ジョン・フォードと駅馬車」より引用」)
もう少し平井氏の言葉を引用しておこう。これもフォードの映画の何たるかを言い表した、的確な表現である。
《地道な努力、質実剛健、決しておごらず、弱い者には優しく、敵に対しては勇敢に戦うという、彼ならではの理想を掲げたのである。そのような生き方は誰もがあこがれを抱き、中年の人が見れば「自分にもよくわかる心情」をさりげなく見せる手腕は、フォード一流の演出の冴えである》
(「平井淳史「ジョン・フォードと駅馬車」より引用」)
映画が何かしらの憧れの対象となることを、ジョン・フォード監督は、それ自体を己の映画手法とした。彼の映画が、時折、男性崇拝主義的な偏見で、フェミニストの反感を買う対象となっていることを散見したりするが、彼の映画が表しているのは、平井氏が述べているとおり、働く男に対する哀感である。そもそも男とは、少年思考から抜け出せない、わがままで身勝手で情けないものなのだ、という通念があり、ある種不様な、恰好の悪い様を含めた上での尊敬と優しさという美学の感受である。決して男性が女性よりも抜きんでた生き物だとは、フォードは全く思っていなかったに違いない。
『駅馬車』のブーン医師の魅力
そうしたことが如実に分かるのは、『駅馬車』における酔いどれ開業医ブーンの有様である。映画の始め、西部の開拓町トントで、ブーン医師が家主の女性に家から追い出されるシーンがある。いつも酔いどれで金が無いから、ブーン医師の持ち物が家賃の肩代わりとなってしまうのだ。後に登場するリンゴ・キッド(ジョン・ウェイン)とは対照的な男として描かれており、不様で非力で女性からも蔑まれている人物であることがよく分かる。
ちなみに、彼が日頃飲んでいるのは、ウイスキーである。スコッチかバーボンかはどうでもいい。おそらくどちらも――である。ウイスキー商人のピーコックと酒場で出会うのだが、彼の持参していたサンプルのウイスキーを、ブーン医師はひったくって飲み、“Ah! Rye!”(ああ! ライ酒だ!)と見事にバーボンの中身を言い当てる。ウイスキーに関しては身体的感覚として、目が高い。
そんな酔っ払いの彼が、まったくもって珍しく、無理矢理しらふに戻して一仕事をするシーンがある。彼にとっては、医師として、切実な状況に陥ったためだ。一言付け加えておけば、これもフォード流の“男への哀感”に通ずる手腕――ハイライトシーンである。
同じ駅馬車に乗り合わせていた将校夫人のルーシーが、第二の宿場駅アパッチ・ウェルズで失神して倒れてしまう。旅の途中、ひどく具合が悪かったのだが、ブーン医師はルーシーが身ごもっていることを知り、出産の準備を始める。ブーン医師は濃いコーヒーを大量に飲み干して、自身のびたびた状態の酔いを必死に覚まそうとする。ある意味、酔いどれ医師にとっては、一世一代の大仕事である。今の時代の出産と比較することはできないが、いつの時代の出産も大仕事であり、母子にとっても医師にとってもたいへんな労力がいる。ともかく、乗り合いの者の協力を得て、ルーシーは無事に女の子を出産し、ブーン医師は面目躍如となる。
酒を飲んでいても――働く男としての最低限必要な美学を持ち合わせていること。不様であろうが非力であろうが、医師を生業としていた彼ブーンの、たった一つ尊敬に値するのは、「人間としては落ちぶれていない」ということである。この点においても、フォード監督は貧者に一点の光を与えてくれている。
貧しくとも、あるいは裕福でありながら愚かな行動の人間であっても、たった一つ、まだ「人間としては落ちぶれていない」ということが、心の精神として大事なのである。人とのつながりにおいてもしかり。アイルランド系移民の家に生まれたフォードのあらゆる経験や宗教心が、映画『駅馬車』にはにじみ出ている。
何度も繰り返して言うが、私は酔いどれ医師ブーンを愛して已まない。

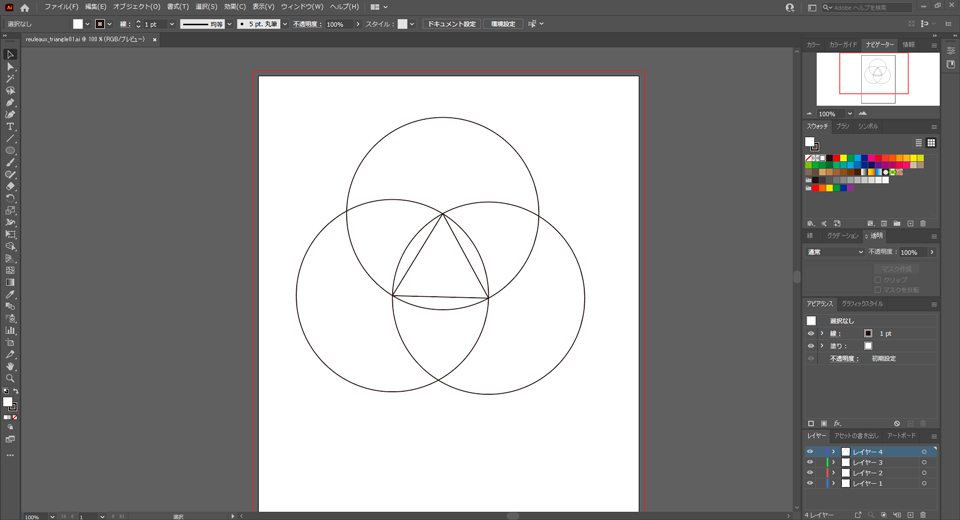
コメント