 |
| 【水中に浮遊する人形。ローリー・シモンズの『ウォーター・バレエ』より】 |
“フェティシズムの化身”たる文筆家・伴田良輔氏の名著『奇妙な本棚』(芸文社/1993年初版)は、私の密やかな愛読書である。この本の中で、写真家ローリー・シモンズ(Laurie Simmons)の写真集『ウォーター・バレエ』(“WATTER BALLET/FAMILY COLLISON”/1987年刊)が、「水の踊り」というタイトルで取り上げられているのだが、数年来、この本を眺めている中、客観的にそれがとても数奇な眼差しであることを自覚しながらも、心の奥底のペダンティックなうごめきを抑えることができなかったのだった。知りもしないローリー・シモンズについて語りたい――と。
そうして難儀な捜索が始まった。『ウォーター・バレエ』を入手したい――。しかしこの写真集が、実はたいへんレアアイテムであることに気づき、ウェブ上の古書店で運良くそれを見つけたとしても、到底廉価とは言えないような価格で販売されているので、私は手が出せなかった。その都度、チェックをしてみたものの、ほとんど気落ちして諦めることが多かったのである。
ところが幸いなことに、ローリー・シモンズのバイオグラフィー的な写真集『LAURIE SIMMONS』(A.R.T. Press/1994年刊)を最近入手することができた。この本の中に、8点の『ウォーター・バレエ』所収のカットを見つけることができた。
とりあえず、これでいい――。万を辞して、ペダンティックな心持ちで伴田氏の『奇妙な本棚』のエッセイ「水の踊り」について取り掛かろう。このフォトグラフについて語ってみたい。ということで、以下、迂闊な文章をご容赦願いたい。
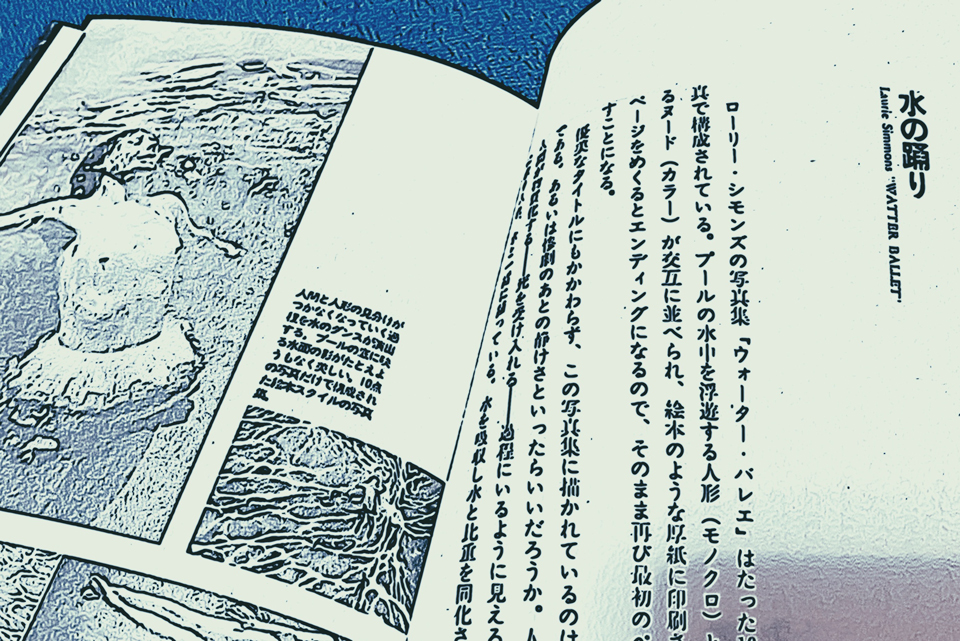 |
| 【伴田良輔のエッセイ集『奇妙な本棚』より「水の踊り」】 |
冷たい人形たちの水中浮遊
伴田氏のエッセイ「水の踊り」。
そこには、上半身裸の女性が、両手を拡げ、水面近くで眼を瞑り、垂直に浮かんでいる写真が掲載されていた。ローリー・シモンズ『ウォーター・バレエ』の1カットである。キャプションにこうある。
《人間と人形の見分けがつかなくなっていく過程を水のダンスが演出する。プールの底に映る水面の影がたとえようもなく美しい。10点の写真だけで構成された絵本スタイルの写真集》
(伴田良輔著『奇妙な本棚』「水の踊り」より引用)
見ればそこには、他に3点のフォトグラフが掲載されており、キャプションにある通り、どれが人形でどれが人間なのか、にわかに判然とせず、またプールの底の水面の反影は、やはり一言で言って美しい。
伴田氏が述べるに、写真集『ウォーター・バレエ』は、たった10点の水中撮影写真であり、水中を浮遊する「人形」の写真はモノクロ、海中を浮遊する「ヌード」はカラーということで、それは絵本のような厚紙に印刷され、交互にそれらの写真が並べられているのだという。わずか4ページほどの絵本的な写真集であるため、4回ページをめくると、再び最初の頁に視線を戻すことになる――と伴田氏は力んだ説明を加えている。
《この写真集に描かれているのは溺死のイメージである》と、伴田氏は批評する。人形たちは人間が溺れて死に、そして物質化する過程にいるのだと――。そして彼らは水を吸収し、比重を同化させ、一体化して踊る。これぞ“水の踊り”。伴田氏はさらにタルコフスキーの映画『惑星ソラリス』の題材を用いて喩え、プールや用水池の水が時に人を“溺れさせる”のは、ある種の自己顕示であり、生きていることの表明なのだと、そこで死者は“水の踊り”を踊っている――のだと主張する。
伴田氏は、少年時代に用水池で溺れかけた自身のエピソードを語り、「水の踊り」のエッセイをこう締め括っている。《死にかけた記憶さえ、人は忘れていくのだ。遠い前世の出来事のように意識の奥にしまいこまれていた記憶、ある夏の水の肌ざわりを、一冊の写真集によって呼び戻された》。
 |
| 【海中を泳ぐのは人。それは溺死のイメージなのか?】 |
私はこうした伴田氏の文章を読んで、ある種のイメージが最初に想起されたことを憶えている。それはつまり、これら水中撮影のカットを絵本化することに成功したローリー・シモンズを、「男性写真家である」と思い込んだのだ。水の中で浮遊する「ヌード」、ぷかぷかと浮かんだ「人形」の《冷たい印象》を写真という形に残したアーティストが、男性ではなく女性であるとは、露程も思わなかったのだった(※一部キャプションに“女性写真家ローリー・シモンズは――”と記してあるにもかかわらず、私はそれを読んでいなかった、あるいは忘れてしまっていたかのいずれか)。
それはそうと私は、エッセイ「水の踊り」に掲載されていた4点の写真のうち、まさに悠々と泳いでいる女性の全裸の、その黒々としたピュービック・ヘアがあまりにも露骨で印象深かったため、伴田氏が述べるほど“死の匂い”を嗅ぎ取ることができないでいた。むしろ水中にいる際の、時を超越するような悦楽、あるいは恍惚とした感覚があるだろうとさえ想起された。
つまり私は、伴田氏の《死相の観念》に今だ及んでいないのである。少年時代に水場で溺れた経験がほとんど無かったからか、水中浮遊の悦楽や恍惚の感覚の紙一重、まさにその隣り合わせが「死」であることを、私自身は体感的に自覚していないのだ。いずれにしても、ローリーは何故このような写真を撮ったのか――という疑問だけが残った。
女性であるローリー・シモンズ
あらためて最近入手した写真集『LAURIE SIMMONS』に目をやろう。
エッセイ「水の踊り」では全てモノクロ写真となってしまっていたが、『LAURIE SIMMONS』に掲載されている8点の“ウォーター・バレエ”は、伴田氏が述べているように、「人形」の写真はモノクロ、海中を浮遊する「ヌード」はカラーとなっており、どのカットのどの被写体が「人形」であり人間かというのは、モノクロかカラーかで一目瞭然であった。
目の前で起こっていることに何も作為を加えぬよう直感のみでシャッターを切る態度が、ローリーの写真の特徴である。海中における「ヌード」は、どれも美的な構図として計算されておらず、ドボンと潜ったモデル達の口から凄まじいバブルが周囲に拡がり、まだ冷静に〈泳いでみよう〉とは行動を移していない「最初の十数秒」を真にとらえているかのようである。むしろこの時、ピントの合わない無数のカットが存在しただろうことを想像する。
一方、モノクロームの「人形」の方は、海中ではなくプールという環境のためか、撮影者にも幾分冷静さが感じられ、底に映った水面のモアレを背景に、規定の構図を固めようとするささやかな対応が感じられる。前者の海中写真は1979年から81年のもので、後者の「人形」写真は全て81年のものである。
 |
| 【印象深いイメージである全裸のピュービック・ヘア】 |
これらのカットを撮影したローリーが、その頃、果たして被写体と「死」あるいは「溺死」を結びつけて想念していたかどうかという点において、私個人はそうとらえていなかったのではないかと推測するのだが、ここはやはりペダンティックな解釈を持ち入らざるを得ない。すなわち、そもそも“人形愛”をかもしだす芸術家は、みな《生と死》といったような逃れることのできない哲学的な死生観を顕著に持ち合わせているのが常で、ローリーもその一人だったと思うのである。
セクシュアリティとジェンダーに関しては、そのポップな発信で先鋭的なアーティスト、レナ・ダナム(Lena Dunham)の方が有名かも知れない。レナはローリー・シモンズの娘である。伴田氏の《死相の観念》ほどではないにせよ、女性はおおむね、生まれることと死することへの思考を体感的に身に纏うものなのだ。
追記:話は大きく変わるが、『奇妙な本棚』に記してある伴田氏の略歴に、《趣味は球技ペタンク、世界大会出場を目指す》とある。ここにきて国内のペタンク(pétanque)愛好者が増えてきたようにも見受けられるので、少々気になっていた。いずれ何らかの機会に、この球技ペタンクについて取り上げられたら、と思う。
追記:「ウォーホル解禁―伴田良輔の『キスの連鎖』」はこちら。

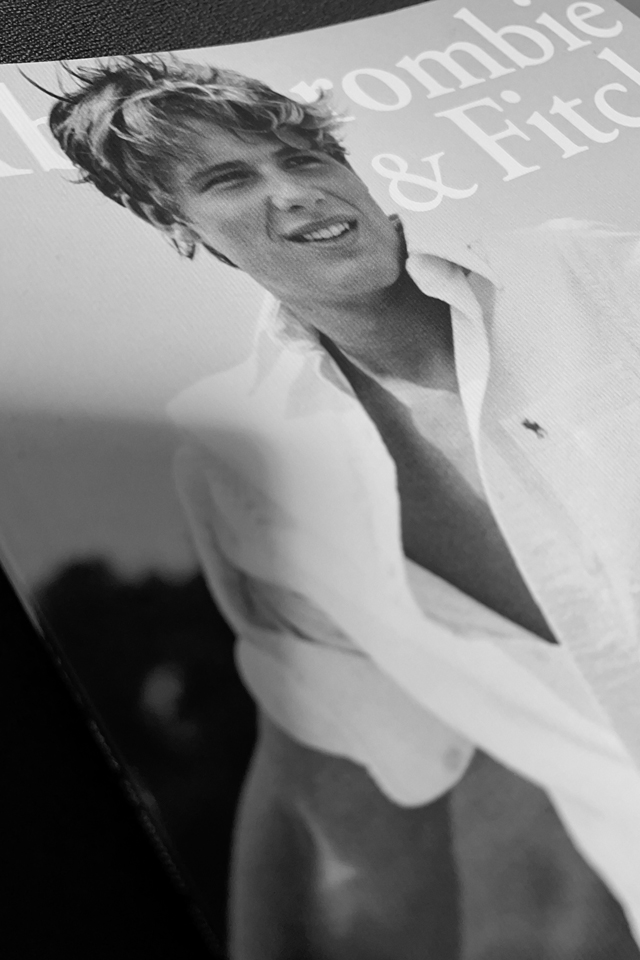
コメント