 |
| 【サブカルを迂回していては生きていけません。伴田良輔著『眼の楽園』】 |
円安が止まらない? 政府・日銀が24年ぶりにドルを売って円を買う為替介入に踏み切った?――。
はい、それがどうかしましたか?――。
そんなふうにきょとんとして、こうした荒れ狂う時代を平然と生き抜くだけの、言わば大人物的な心の余裕は、庶民に多くないのもよくわかる。私もその一人である。
ただ、そうだとしても、意味もなく慌てたり暗い気持ちになるよりも、私はあくまでこぢんまりと、古今東西のサブカルを追い求め続けていたいと思うのである。例えば、〈えらいこっちゃ。マタ・ハリってべっぴんやなあ〉と心の中でつぶやくことがある。なぜかそういう時は関西弁なのだけれど、全体としてのサブカルに対する優雅なこころざしと安寧だけは、祈願せずにはいられないのだ。
マタ・ハリを見よ。
彼女ほど、賛否両論うずまく女性はいなかった。ゆえに、この世の刹那に溺れ死んでしまうおそれのあることへの人生訓や処世術があるとすれば、オランダ生まれのダンサー、マタ・ハリ(Margaretha Geertruida Zelle)の妖艶なる豊満な肉体を直視すればいい。官能は理知を超越し、迫り来る興奮のさざ波に身をさらし、宇宙のちっぽけな存在である「私」を想像すればいいのだ。もし一途に、その豊満な肉体への惑溺を覚えるのであれば、それもよかろう。美と官能を包み込むサブカルの世界は、そこはかとなく心の救済を取り計らってくれるのだ。
ちなみに私は美しいマタ・ハリをどこで見たかというと、サブカルの宝庫――ヴィジュアリズム文芸の稀少本『眼の楽園』(河出書房新社/1992年初版)であった。日々、ほとんど無意識にこの本を開いてしまうことがある。単純にいって、私はこの本が大好きだ。言うまでもなく、著者は伴田良輔氏である。
ということで前回(「伴田良輔『眼の楽園』―インコと女の子」)に引き続き、今回も懲りずにこの本の中のトピックを刮目していきたい。
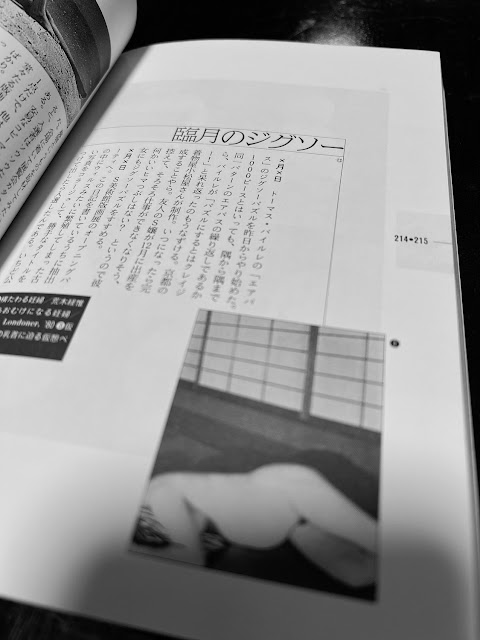 |
| 【トーマス・バイルレのジグソーの話。「臨月のジグソー」】 |
臨月のジグソー
しかしながらここで私が、女スパイ?=マタ・ハリの話をしだしたら、あまりに芸がないではないか――。
マタ・ハリについては、後日別稿でたっぷりと書くことにする。おもわずマタ・ハリに期待してしまった方は、どうかお許しを。その身をさざ波にさらしたまま、しばらくのあいだお待ちいただけたらと思う。
さてここでは、“臨月の女”の話に転ずる――。
ここでいう“臨月の女”とは、すなわち『眼の楽園』の中の小稿「臨月のジグソー」を指す。私はここで美しい「妊婦のヌード」を見たのだった。
実はその「妊婦のヌード」は、「臨月のジグソー」の話になんとなく辻褄を合わせた、構成上の一種のめくらまし的“挿絵”にすぎなかった。つまり、“臨月の女”の話とは直接関係ないのだ。ただし、じっと眺めていると、まるでその被写体の妊婦が臨月に達したかのような、錯覚を味わえたのは事実である。
これを撮影したのは、写真家ハンク・ロンドナー(Hank Londoner)氏で、1980年の作品だそうである。海をバックに、真夏の砂浜で程よく日焼けした女が、全裸で横たわっている。腹が少しこんもりとうわずり、バックの海に突き出た感じが幸福感を表しているような気がして、見ているだけでハッピーな気持ちになれる。
それはそうと、“臨月の女”の話はこうである。
×月×日、伴田氏は、ドイツの美術家トーマス・バイルレ(Thomas Bayrle)の「エアバス」のジグソーパズルを“昨日”からやり始めたらしい。1000ピースもあるそのジグソーは、なんとエアバスの画がパターン化されたモザイク画らしいのだ。
トーマス・バイルレの作品を調べてみると、あるモチーフを微小サイズでひたすら反復し、その厖大なパターンでグリッド化し、さらなる別の造形を描いてみせるという手法が多いようだ。もともと織物工をやっていた経験があるというだけあって、ある種、そうした造形物のイメージが活かされているわけである。
伴田氏はその日、バイルレの作品――グリッド化されたエアバスの複写版ジグソーパズル――を楽しんだ(ちなみにこのジグソーを製作したのは京都の着物屋さん)。そして、友人のS嬢が出産を控えていると聞き、彼女にもジグソーパズルをやるようすすめた。
やがてS嬢から電話があって、“金髪の赤ちゃん”の画のジグソーをやり始めたと、伴田氏は聞いた。ジグソーの初心者である彼女は、ピースとピースが合うごとに歓声を上げたという。伴田氏はこんなふうにつぶやく。
《お腹の中の赤ん坊が『完成』して外に出て来るのと、どっちが早いやら。最後の1ピースをはめ込んだとたんにポロンと出て来るんじゃないの》
それに対し、彼女はこう答えた。「他人事だと思って」――。
 |
| 【仮想妊婦の乳首に迫る仮想ベビー?】 |
クラリオンガールだった黒川ゆり
私はぞっこんロンドナー氏の「妊婦のヌード」に惚れた。
――イスラエル出身の商業写真家で、ロサンゼルスで写真について学び、ニューヨークのマンハッタンにスタジオをかまえ、ファッション系の広告写真などを手掛けてきた。現在はロスに滞在――。
ただ残念なことに、写真集のたぐいはほとんど出てこなかった。ただひとつ、こればかりなのだが、“黒川ゆりの写真集”(1984年)だけは何点も上がってくるのだった。
黒川ゆり。当時彼女は、10代目クラリオンガールであった。彼女が歌ったクラリオンの“イメージソング”、「愛を告げて」(作詞・作曲:荒井由実、編曲:松任谷正隆)を興味本位で聴いてみた。
ポテンシャルの高い褐色のFカップとは裏腹に、彼女の声はあまりにもかぼそく、喩えていうなれば、大正から昭和初期にかけ、カフェーで女給をしていたモガ(モダンガール)の古風な日本人女性の声――。その声からは、はち切れんばかりの南国の女の子――といったような印象は、少なくとも感じられないのである。
それにしても、“クラリオンガール”とは、なんと久しぶりな響きか。
カーオーディオメーカーのクラリオンが、かつて70年代以降(2006年まで)、キャンペーンガールを輩出し、全盛期においてはグラビアアイドルとして一世を風靡した時代があった。
そう、初代クラリオンガール(1975年)は、伝説のアグネス・ラムである――。
歴代のクラリオンガールを追っていくと、なかなかすごい。80年には烏丸せつこ、88年には蓮舫、90年はかとうれいこ、95年は原千晶。
そう言えば私は、アグネス・ラムのプロモーションムービーとなっている8mmフィルムを入手できたら、好みの合う連中を集めて、ちょっとした“ラム上映会”を催したいなどと夢見ていたことがあった。むろん、今でもその夢は残滓としてある。
 |
| 【こちらがロンドナー氏の幻の「妊婦のヌード」】 |
ロンドナー氏の『PENTHOUSE』
閑話休題。“黒川ゆりの写真集”を手掛けたのは、ロンドナー氏。しかし、肝心な“妊婦のヌード”を収録した写真集のひとかけらも検索できなかったのはたいへん残念である。
尤も、日本語圏に限らず、グーグル検索で“Hank Londoner pregnant woman”とやっても結果は変わらなかった。したがって、伴田氏の本に掲載されていた、あの“妊婦のヌード”画像は、今のところ貴重な1カットということになる。
ただし、ロンドナー氏は雑誌『PENTHOUSE』の仕事が比較的多かった。だから80年代くらいの古い『PENTHOUSE』をほじくり返せば、彼の作品は見つかるはずである。しかし、そんな悠長な、気の遠くなるような作業はしたくない。
たまたま検索でひっかかってくれたのが、アンジェラ・ヒューストン主演の『PENTHOUSE』のビデオ版(「ザ・メイク・オブ・ザ・センターフィールド」)である。むろん撮影者はロンドナー氏だ。このビデオ作品では、アンジェラの褐色のヌードが存分に味わえそうだ(日本版なので露出度は期待できそうもないが)。『PENTHOUSE』のビデオ版というアイテムは、今となってはなかなかレアものといえるのではないか。
そのビデオのパッケージには、古めかしいキャビネットの上に、上半身裸のアンジェラが尻と背中をつけ、あの妊婦と同じポーズをとって天に顔を向けている写真があった。よほどロンドナー氏はあのポーズがお気に入りだったようである。
とは言え、あの砂浜の妊婦の心地良い雰囲気には到底及ばない――。
被写体の妊婦の彼女が、どことなくニューヨークの女神像に似ていて、もし「自由の女神」像が、腹がでんと突き出た妊婦であったならば、どんなにニューヨーカー、いやアメリカ国民はハッピーな気持ちでいられただろう。現実は真逆にして、そうではないのだから。
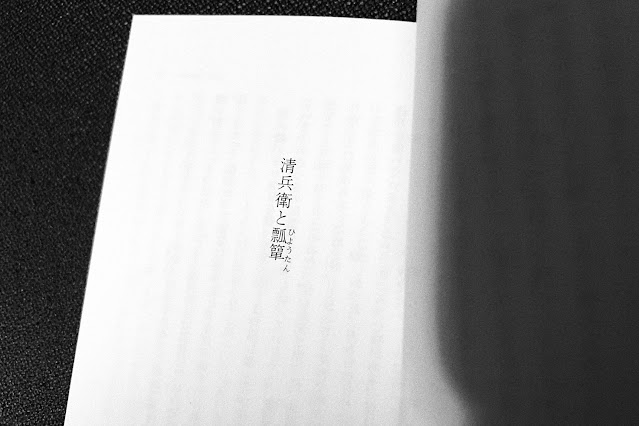
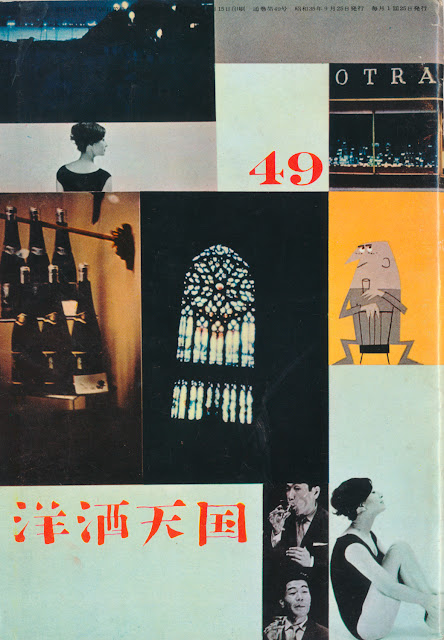
コメント