 |
| 【『ベルサイユのばら』のオスカルに扮装した女性。しかし心霊が…】 |
昭和が遠くなりにけり――。平成時代ですら、もはやその“体験の記憶”を留めておくことができなくなってきた感がある。昭和は、さらに古く、遠い怨念に満ちた過去という印象が拭えない。
なぜいま、そうした漠然たる思いに駆られるかといえば、テクノロジー――とりわけ生活に密着したIoT(Internet of Things)――の急激な変化をここ数年感じているからである。パソコン以外のあらゆる装置やモノに内在した“人工知能システム”が、人々の日常生活のこまやかな情報伝達に扶助教授し、今日における格差社会の弊害性を軽減してくれる画期的な時代に突入したといえばいいのかどうか。今後、さらに生活と文化そのものの規範や活用性が劇的に変化するのではないか。皮肉にも、社会に禍をもたらした“新型コロナウイルス”の存在が、新時代における試金石を著しく押し上げた面があるのだ。
さて、昭和の和みと不穏に満ちた、その“神秘なる世界”の魔窟に、一歩足を踏み込んでみようではないか。
心霊研究家・中岡俊哉先生の“恐怖の心霊写真集”は、どっぷりと昭和の臭みが感じられる、科学と非科学の境界線が曖昧な、まことに興味深い教養本であった。
前回の「真昼の心霊写真」に続き、二見書房“サラブレッド・ブックス231”の中岡俊哉編著『地縛霊 恐怖の心霊写真集』(1982年初版)の中から、再びここで、これはと思う2点の心霊写真を紹介することにする。
 |
| 【修学旅行で厳島神社。しかし誰かの手が…】 |
それは亡くなった父の手なのか
《この写真は、修学旅行で広島の厳島神社に行ったときに撮影したものです。撮影日は昭和五十五年十月十二日、午前七時ごろです》
(中岡俊哉編著『地縛霊 恐怖の心霊写真集』より引用)
千葉県長生郡の高校生(当時)・石渡修さんから鑑定依頼された、厳島神社での集合写真を見てみよう。
午前7時というきわめて早い朝方に、記念写真を撮らなければならない修学旅行の過酷な日程って、いったい? と思わず首をひねってしまったのだけれど、そもそも厳島神社は、“日の出が最も美しい観光スポット”のようである。生徒ら一行は、いつ朝食を食べ、旅館を出発し、神社に到着したのだろうか。きわめて昭和らしいハードスケジュールになってしまっていたかと思われる。
そんなことはさておき、肝心の、白い丸で囲まれたところを見てみよう。
なんと――確かに、女子生徒の左腕の奥から、別の人の手が伸びて写っており、その手の主が集合写真の中にいない。これは典型的な心霊写真ではないか。
石渡さんによると、この女子生徒さんの父親は亡くなっており、そのお父さんの手なのではないか――と推測している。お父さんの手にしては、ずいぶん細い気もするが――。
これについて中岡先生は、《鑑定にあたっては、“不思議な写真”としかいいようのない場合が多い》。実に奇妙な言い回しである。
我々は心霊写真そのものをすべて“不思議な写真”と思っているわけだが、先生にとっては、真性の心霊写真と“不思議な写真”とは、全く別個なもの、ということになっている。
現に先生は、こう続けている。
写した場所や被写体の人物のことなどを考え合わせても、《なかなか心霊写真であるという形での鑑定がしにくい》――。このニュアンスは実に微妙である。《しにくい》という言い回しは、むしろ微妙というより、ある厳格な実態を捉える上で、絶妙ということになるであろうか。
霊気が強くなく、心霊写真とは鑑定しかねる、したがって、これは“不思議な写真”だという理屈である。《霊的な意味あいのものなのかもしれないが、写真そのものの霊波動からみても、この女生徒の父との関係は考えられない。また、写真は供養してあるので、霊障の心配はいらない》。女子生徒さんのお父さんの手かどうかは別にしても、霊的な意味合いがあるかどうかも鑑定《しにくい》ということなのだろうか。
これは私の個人的見解なのだが、いちばん左に座っている女子生徒さんの、その後ろに立っている男子生徒さん。ちょっと前屈み気味の体勢になっている彼の視線は、どこを見ているだろうか。
なぜ彼は、正面のカメラのレンズを見ずに、囲みの中の、“手が伸びているあたり”を見ているのだろうか。その瞬間、そこに何かあったのだろうか。
私はこの彼が、中岡先生に鑑定依頼した本人ではないかと思っている。
中岡先生は、こうした鑑定依頼における海千山千の経験上、誰かがこっそり、そこに隠れているだろうこと、誰かが心霊写真的なものをこしらえようとしている作為なる不穏を、直観的に感じ取ったのだろう。作為であることのエビデンスもないゆえに、鑑定が《しにくい》というような言葉のニュアンスになったのではないか。
オスカルになりたかった女
私の小学校時代の同級生に、“アンドレ”というあだ名をつけられた身長の高い女の子がいた。正直いって、私はその子が好きだった。
確かに身長が高かった――。小学6年生の時、その子の身長は170センチ弱に達していたかと思われる。
なぜ、“アンドレ”というあだ名がつけられたかというと、大巨人プロレスラー、アンドレ・ザ・ジャイアントをだぶらせていたからだ(身長223センチ)。女の子のほうからすれば、これほど不本意な、失礼なあだ名はない。ただし、プロレスラーのアンドレは、その巨体をビッグマネーに変えた世界でも稀にみる大天才のスターである。
とはいえ、私も、自分の好きな子が、大巨人の“アンドレ”といわれるのは癪に障った。
なので、マンガ「ベルサイユのばら」(原作者は池田理代子)のアンドレとオスカル、そのアンドレ・グランディエと思えばいいのではないかと腹をくくったのだった。それもまた失礼ではないか――といわれればそうであるが。
実際、その子の外見の雰囲気は、どことなくアンドレ・グランディエを演じるタカラヅカの女優さん――といえなくもなかった。昭和50年代後半、女の子はおおむね、「ベルサイユのばら」=ベルばらのマリー・アントワネットとオスカル、そしてアンドレといった登場人物に特別な夢想を求め、敬意を表していたはずである。
男装の麗人オスカルに扮装してみた女の子が、その晴れやかな記念の写真が、心霊写真に成り下がってしまったときのショックは大きい。少々長くなるが、鑑定依頼をした八王子市の山口ちかさんの手紙を以下、記しておく。
《同封の写真は、新宿のデパートで“ベルサイユのバラ”のオスカルという主人公の姿をして撮ったものです。私のうしろに霊体らしきものが写っていたので、先生に鑑定していただきたく、手紙を書きました。
母や祖母にこれを見せたところ、おじいさんに似ているというのですが、そのほかにも何人か写っているような気がするのです。
母(母はキリスト教で、私といっしょには住んでいません)が、この写真を飾って拝みなさいといったので、私はつい最近、そのことばを思い出し、写真を飾ってお水を供えています。
私は昔から霊の存在を強く信じています。違うかもしれませんが、その姿らしいものを見たり、声は二度ほど聞いたことがあるのです。
中岡先生の著書である『守護霊の秘密』という本を読み、般若心経を毎日一回唱え、写仏を少しずつしています。
今日の私があるのは、私の守護霊さまのおかげと、これからもずっと感謝していきたいと思います。鑑定のほう、よろしくお願いいたします》
母や祖母にこれを見せたところ、おじいさんに似ているというのですが、そのほかにも何人か写っているような気がするのです。
母(母はキリスト教で、私といっしょには住んでいません)が、この写真を飾って拝みなさいといったので、私はつい最近、そのことばを思い出し、写真を飾ってお水を供えています。
私は昔から霊の存在を強く信じています。違うかもしれませんが、その姿らしいものを見たり、声は二度ほど聞いたことがあるのです。
中岡先生の著書である『守護霊の秘密』という本を読み、般若心経を毎日一回唱え、写仏を少しずつしています。
今日の私があるのは、私の守護霊さまのおかげと、これからもずっと感謝していきたいと思います。鑑定のほう、よろしくお願いいたします》
(中岡俊哉編著『地縛霊 恐怖の心霊写真集』より引用)
私はオスカルの扮装の方がはるかに脳裏に刻み込まれてしまい、ここに霊体が写っている云々など気分的に飛んでしまったのだけれど、中岡先生は、ずばりこの写真を心霊写真と鑑定した。
男の老人の霊体であるとのこと――私には白い煙にしか見えないが――。地縛霊ではなく、浮遊霊に近いという。
亡くなられた祖父の霊が、もしまだ浄化されていないのであれば、このような形で出てくることも考えられるとのこと。手紙に書いてあるようなことを、ご自身の力で克服していくことが大切とのこと。
守護霊に対する山口さんの取り組みは、素晴らしいとのこと。したがって、あなた自身がこの写真を大切に扱い、あなたの手で供養した方がよかろうとのこと。写真からの霊障の心配はまったくない――とのこと。とのこと。とのこと…。
この写真のオスカルの衣裳が、どうも原作のオスカルの着ている軍服と似つかわしくない――こまかい部分でだが――ので、ちょっと調べてみたところ、どうやら1979年に公開されたジャック・ドゥミ監督の日仏合作映画『ベルサイユのばら』に登場するオスカルが、ほぼこれと同じ衣裳なのである。
もしかすると、山口さんが新宿のデパートに出かけていった“ベルサイユのバラ”の催しは、映画版のプロモーション・イベントだったのではないか。そう考えると、写真に写っている背景が、映画のフィルムの1コマから借用されたものではないかという想像ができる。
さすがに私もこの歳で、ベルばらのマンガやアニメ版を全て鑑賞していく時間的余裕はないけれど、このジャック・ドゥミの映画なら、ぜひ観てみたいと思う。むろんそのことは、心霊写真とはなんら関係がない。
山口さんのオスカルへの憧れは、自身の心が、マリー・アントワネットの立場であることを物語っている。ご先祖様への感謝の気持ちは、人を愛する心と同根ではないだろうか。立派な信心に肖りたいものである。
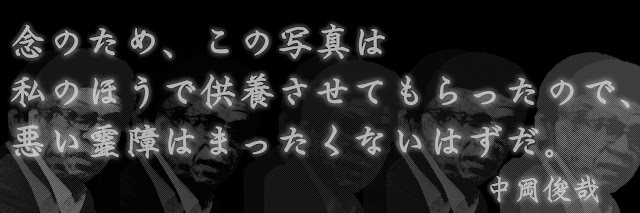


コメント