
黒のレース地に驕奢な蔓草模様がふちどられたランジェリーへの夢は、肉体を艷やかに彩り、昼夜の境界なく当て所もない愛と欲望の路地裏に彷徨うだろう。下着とは、人生の受容性と果敢な冒険心とをくすぐる、社会的シンパシーの中で培養される政治的特権の装置なのだ。
かつてその装置は、女性は女性たらんとし、男性は男性たらんと君臨した。しかしそれは、時代的なファシズムにすぎず、今、その観念は緩やかに駆逐されつつあるようだ。いや、そうでもあるまいか――。ならば、この特権は誰のものとなるのだろうか。
いみじくも私は、密やかな空間の中で、パンツ論を展開している。前回は、旧時代の女性週刊誌の企画記事をもとに、様々なメーカーの男性下着のパンツを詳察したのだった。
私個人の結論を申せば、もはや昭和の古いパンツだといって馬鹿にできるものではなく、今も昔もその清々しさはなんら変わらない――ということだった。奇天烈かつ時代錯誤的な違和は、ほとんど感じられなかったのである。
パンツは「軽く小さく」そして究極へ
1930年代にアメリカのJOCKEYのブリーフ(「Yフロント」)誕生以来、男性下着のショーツ化は、多少の形状の変遷や快適さの追求の日進月歩はあったにせよ、普遍的なスタイルとして支持された。その機能美のみならず、「見せる」(不可抗力的に他人に「見られてしまう」ことも含める)ための要諦――すなわち視覚に耐えうる「デザインの標準化」という工業製品的価値は、今日の21世紀2020年代においても、何ら企図は変わらず保全されているのである。
「Yフロント」をはじめとする男性下着のブリーフは、女性下着よりもいち早く定着化し、ショーツ化を果たした。すなわちそれは、“眠れる坊や”にあてがわれた、自己同一性と家族的社会的連帯の象徴としての、ユニオンスーツからの脱却を意味していた。いうなれば、個人自由主義時代のアップデートだ。
しかもそのショーツ化は、確たるトラディショナル・スタイルとなり、クラシックとなり、オールド・スタイルとも評されて、俯瞰してみれば、人新世のファッショナブルなレガシーとなったのである。
その反面、ブリーフがトラディショナル・スタイルとなったがゆえに、いかなる時代においても、成熟した精神の覚束ないうちは、常に誰かの策略によって、あるいは何らかの集団的価値観に起因する要請によって、許容申し立てる範囲内においてのそれがあてがわれ、場合によっては配給され、個人の主体的な価値観とは無縁の「パッチ化」を具現してしまったことに、驚きを隠せないのである。下着というものは…いや、下着を個人に選ばせないということは、常に精神の抑圧の対象=アイコンとなりうるのだった。
個人自由主義時代においても、不可抗力的に半ば下着(パンツ)に対して無頓着でありうるのは、そのような政治的な意図の服従と抑圧によるものである。本来的には、下着(パンツ)は、「自ら選び取る」意志(=表明)が大事であって、「人新世のパンツ論」における未来志向的な、文化人類学の成熟を意味するものとしての究極は、まさにそれに尽きるのであった。
話は各論に移る。
今日のパンツ――。「自ら選び取る」意志の具現…。産業革命以降、せっせと人類は、個人自由主義の拡張に喘ぎ戸惑いながら、パンツの標準化とその量産に励み続けた。“パンツ革命”というほどのことではないが、ついに20世紀以来の夢を勝ち取ったのだ。
それは何?
パンツのジェンダーレスである。男性も、好んでパンツをラグジュアリー化させていく機運に恵まれつつある。驕奢な下着への夢は、今日において、「女性たらん」ではなくなり、「男性たらん」でもない。あらゆる連帯の抑圧から解放された、個人自由主義の象徴としての至宝。いうなれば、パンツの特権的自我。それが、ラグジュアリーなランジェリーである。これについての夢想を、今回はとくと語ってゆきたい。

WACOAL MENのブランド
近年、ワコール(WACOAL)では、男性のラグジュアリーな下着の商品化にも力を入れているようだ。そのブランド「WACOAL MEN」のレースボクサーなどは、私の“お気に入りパンツ”の仲間入りを果たしたのだった。
これ幸い、一つ試しに穿いてみたわけである。
「WACOAL MEN」の、BROS by WACOAL MEN。
チョイスしたカラーは、イエロー。このBROS by WACOAL MENの特性を公式ホームページより紹介すると、第一に、《男性部を快適に包みこみ、グラマーに魅せる設計》であること。第二に、透け感のあるペイズリー柄及び迷彩柄のオリジナルデザインであること。第三に、ストレッチ性のあるレースを使用していること。
穿き心地は、実に快適である。締め付け感が無いというよりは、程よい――といったほうがいい。それはストレッチ性のあるレース生地によるものなのだが、《男性部》すなわち陰茎及び陰嚢の収まり感が、実に快適なのだということを率直に申し上げておきたい。
透け感については、《男性部》に当たる生地が重層になっているため、ほとんど透けている感が無い。この点では安心していい。ただし臀部、すなわちお尻に関しては、その肌が見えるくらいに透ける。
大人が穿くパンツである。
いや、ちょっとニュアンスが違う。おとなになった自分を惚れ惚れとした気分で味わうパンツである。
「WACOAL MEN」の革新性は、その特徴的なレース生地を用いることによって、快適な穿き心地を獲得し、かつ「魅せる」下着として、透け感を「見えているが、見えていない」くらいに設定している点だ。肝心な部分は見せないが、プライベートゾーン全体としては、“見えているように見せている”デザインの勝利である。勝利というのは、このブランドの売れ行きがかなりヒットしている、という意に違いない。
さらに付け加えて申し上げておく。このBROS by WACOAL MENを一度穿いてみれば、「自身の身体とパンツとが一体となる」感覚を、すぐさま認知することができるだろう。
全く個人的な感想を述べれば、本当に穿くのが楽しいパンツなのである。「WACOAL MEN」のラインナップを見ていただくとわかるのだが、レースボクサーに限らず、様々なスタイルのパンツが用意されていて、パンツを「自ら選び取る」意志の先覚を、じゅうぶんに練磨することができるのではないかと私は思う。

こうした透け感のあるレースボクサーを男性が穿くことの意味合いは、単にジェンダーレスの進化を指しているだけではなく、その性差にかかわらず、「自身の身体とパンツとが一体となる」ことへの、夢見る理想や憧れといった前衛的観念によるものであり、その実現の魂がこの時代にあるのだ。
パンツを穿き、それと一体となる喜びとは、どういうことなのか? おそらくそれは、「なにものか」に変異しようとする、無意識の欲望なのではないだろうか。
私は今、男性下着が近代のユニオンスーツ(確かにあれは、赤ん坊が着る肌着だ)から脱却して、ショーツ化(=ブリーフの標準化)への革新的な変遷が、女性のビキニ誕生(1940年代後半)よりもわずかに先鞭性をもたらした作用点として、当時のストリップティーズのための衣装から派生した、女性が身にまとう「ラグジュアリーなランジェリー」への強い願望があったのではないかという仮説を展開しようとしている。
女性下着の近現代史的な考察を再確認できる、伴田良輔氏の『UNDER WEARS』(作品社/1990年刊)を参照しつつ、「ラグジュアリーなランジェリー」への願望が男性の心理とその下着に与えた連鎖について考えてみよう。

ディートリヒの「脱ぎ」の妖艶
先日、ジョセフ・フォン・スタンバーグ(Josef von Sternberg)監督の映画『嘆きの天使』(“Der blaue Engel”/1930年ドイツ)を観た。主演のマレーネ・ディートリヒ(Marlene Dietrich)が場末のショーガールを演じ、楽屋で下着姿をちらつかせるシーンが印象的であった。
伴田氏は『UNDER WEARS』の中で、この映画についてまず、こう述べる。
下着と映画を語る時、必ずとりあげられる。黒のガーターベルトとストッキング、ヒラヒラしたフリルのついたランジェリー姿のディートリヒが、ステージで歌いながらストリップ・ショーを思わせる妖しい動きを披露するシーンは絶品だ。
伴田良輔『UNDER WEARS』より引用
私もこの映画を観て、ひどく感心した。
ディートリヒ演じるローラというショーガールは、いわば悪女で、善と悪の見境がない。ステージ上で高慢な内容の詩を歌っている彼女からは、その境遇の俗悪さを思わせる。ただし、美貌は天下一品で、ある学徒らと高名な教師が、彼女の魅力に取り憑かれてしまうのだった。
ステージでローラがストリップ・ショーを演じるシーンがあるかといえば、それはごく限られたショットのうちに、暗喩としてあるというだけで、厳密なストリップティーズとはいえない。しかし、楽屋で彼女が下着姿になり、ラグジュアリーなガーターベルトとストッキングの隙間から、やや肉厚のある太腿を露出させるシーンは、それを直接的に象徴している。
スクリーンに現れた、白い太腿。ドイツ語に訳すと、weiße Oberschenkel――。おそらく当時、観客はこれを見て驚いたに違いない。マレーネ・ディートリヒとは、いったいどんな女性なのかと――。

女性下着がストリップ・ショーを駆逐した
伴田氏は、映画における下着の「脱ぎ」の登場について、以下のように考察する。
ストリップ・ショー自体は男のために今世紀に入って考え出された見せ物だが、日常的な女性の脱衣の光景に憧れる男性のために、19世紀末ころから、工夫をこらしたイラストや写真が雑誌に登場していた。「隠す」ための下着と、「見せる」ための下着が同一化していく過程は、ストリップ・ショーの人気とパラレルに進行していくのである。そしてその二者が同一化を果たした時、ストリップ・ショーの沈滞がはじまった。現実の女性のセクシャル・アピールに、ストリップ・ショー的な虚構のパワーは追いつかなくなっていくのである。
伴田良輔『UNDER WEARS』より引用
鋭い指摘である。
そのページには、19世紀に描かれたという「女性の脱衣風景」の連続コマがある。ドレスを着た後ろ姿の女性が、下着姿となり、一つ一つのパーツを脱衣し、ネグリジェに着替えるというイラスト。
これと同様、映画の『嘆きの天使』でのディートリヒにおいても、《現実の女性のセクシャル・アピール》――すなわち実写として、19世紀の「女性の脱衣風景」を彷彿とさせ、そのエロティックな欲望にかられる男性観客が、ディートリヒの虜となったに違いないのだ。
ちなみに、別のページでの伴田氏の言説によると、1920年代には、コルセットとブラジャーによるコンビネーションで、より軽く、より動きやすく改良されたデザインのランジェリーの広告が見られ、それ以外ではガーターベルトとストッキングを組み合わせたズロース・ファッション(とくにフリンジ加工のズロースが人気だった)が流行していたようである。
しかし、「女性の脱衣風景」は、トーキーの先達となった映画『嘆きの天使』にとって、ある意味狙い撃ちされる、場合によっては死に体となりうる毒牙でもあった。
映画は、芸術か、猥褻か。
あるいは、子どもらがそれを観た場合にどうなのか――。国家が芸術の範囲に及んで映画メディアを統制していく前に、業界内での倫理上の自主規制が必要だと考えたのだ。アメリカにおける映画製作の現場では、30年代以降、映画配給業者間で定められた自主規制の条項が存在した。ヘイズ・コード(Hays Code)である。
性差のアイコンだった下着からの脱却
1894年にオスカー・ワイルドの戯曲『サロメ』が出版され、これがストリップ・ショーの起点とされて名高い(→7つのヴェールの踊り“Dance of the Seven Veils”)。翌年には、パリのバーレスクの見せ物で、実際的にストリップティーズが演じられた。
これ以降、各都市の劇場のバーレスクの見せ物では、妖艶かつ過激な構成にショーアップしていき、ストリップティーズは世界的にもその名が知られるようになり、確固たる“低俗な”、定番の出し物として、その意義が確立されていった。
過激なファッションと踊りで観客を魅了したことで知られる、アメリカのサイレント映画時代の女優セダ・バラ(Theda Bara)は、もともとブロードウェイの女優であり、映画では『愚者ありき』(A Fool There Was/1915年)でデビューを果たした。彼女の容姿の過激さが、のちのヘイズ・コード導入を牽引した因果の一つとして考えてもおかしくない。
時代の風潮――個人自由主義の謳歌――が彼女を突き動かし、よくも悪くも、女性は男性に「見られる」対象として、そうしたショー・ビジネスが跋扈した。ちなみにセダ・バラは、1918年に映画『サロメ』にも出演している。
20世紀初頭は、芸術とファッションが花開いた。
女性は男性に「見られる」対象である。バーレスクでの女優の過激な衣装とその出で立ちやパフォーマンスが瞬く間に評判となって、アメリカでは、ジーグフェルド・フォリーズやブロードウェイでのヴァニティーズにおける、露骨な肢体を強調した“女性ショー”が人気を博した。そうした時代に、“黒いヴィーナス”だとか“黒い稲妻”といわれたジョセフィン・ベーカー(Josephine Baker)も台頭してくるのであった。
そう、ジャズ。
ジャズの存在を忘れてはならないだろう。その流行は、50年代に向けて黄金時代へと突入するのだが、そうした酒場での力強い演奏のムードもまた、堅固に縛られた社会規範や道徳をほんの二つ三つほど振りほどき、魂の自由が誘発され、男女の身体表現が露骨な方へ傾いていく。
こうした風体が写実著しいメディアである映画にも登場してくるとなると、いわば“女性ショー”における女性下着の「見せる」要素の一面は、ファッションの主流とも錯覚され、ついにラグジュアリーなランジェリーへの追求に加担していくことになるのだ。
1946年に水着のビキニスタイルが登場(※伴田氏の先の著書の言説によると、既に3世紀頃のシチリア島のモザイク画に、ビキニスタイルとそっくりな競技ウェアが描かれていたということも付記しておく)し、もはや水着はおろか、下着も超ハイスペックでツーピースでショーツ化していったわけである。
下着は19世紀以来の夢、すなわち、男性にとって「女性美」なるものへの大いなる幻想を抱かせるアイテムに変貌を遂げた。一方で下着のショーツ化は、「脱ぎ」の所作の時間を大幅に短縮した。「穿きやすく脱ぎやすい」は、男性がその幻想を抱く“官能の時間”及び空間性までも最小化した。なるほど、下着がこの方面で果敢に進化すれば、ストリップ・ショーが沈滞するのも無理はない。
しかし、あくまでそれは、ショー自体の沈滞であって、日常的なプライベートにおけるストリップティーズの幻想は、より深みを増していったことになる。
どういうことか?
つまり、それが女性のみの特権的領域ではなくなったのである。男性も自ら、「脱ぎ」の官能を疑似体験することが叶うようになったのだ。下着は既に性差のアイコンではなくなり、それぞれの性の解放へ漸進し、個人の美意識の高まりから、古い固定観念に楔を打ちつけられた。画期的な自己肯定感のアップデートの時代が到来したのである。
§
最後に個人的な余話を――。
ワコールの、レース生地を用いた下着の透け感――「見えているが、見えていない」は、実に素晴らしい進化だと思う。
その昔、私がまだ中学生だった頃、ある女性週刊誌に、ラグジュアリーなランジェリーの通販カタログが掲載されていたのを、母親が買ってきたその本を隠れて“盗み読み”して、見たのだった。よく憶えていないが、アメリカかヨーロッパのブランドのランジェリーだったのではないか。
そのカタログのラグジュアリーなランジェリーは、外国人女性のモデルさんの下腹部が、かなり透けて見えていた。露骨にいってしまえば、ピュービック・ヘア(陰毛)がほとんど見えていたのである。思春期少年の私には、それがひどくショックだった――。ショックというのは、興奮したという意味だ。あまりにも刺激的なビジュアルで、驚いたのである。
そうして考えると、確かにレース生地は、「透ける」のが常識だったはずだ。むろん、そうした類いの下着の需要は今でもあることを知っている。しかし、完全に透けてしまうと、それは特別なランジェリーというカテゴリーに括られ、日常的には恥ずかしいと思ってしまってなかなか穿くことはできない。
ところが、ワコールのレースボクサーの透け感は、何度もいうように、「見えているが、見えていない」のだ。
レースボクサーを頻繁に穿くには、多少の、意識改革が必要かもしれない。ジェンダーレスもさることながら、驕奢に対する拒絶感の源泉を半ば断ち切る必要がある。いずれにしても、この時代、大したことではないのだ。《男性部》が全く「透ける」わけではないので、それほど羞恥心が乱されることもないだろう。
ワコールは、2008年に「男性の心理と下着に関する意識調査」を公表している。今となっては少々古い資料となってしまうが、それによると、どの年齢層の男性にしても、下着は「自分で選びたい」と考える人が多いのだ。
そのうち、3割以上も、下着の「こだわり派」がいる…。などと、こうした消費者の貴重なリサーチから、今日の「WACOAL MEN」のポジティブなデザインが誕生していったのだと思う。「見えているが、見えていない」はこのブランドの真骨頂ととらえていい。
ということで、今回はここまで。
次回の「人新世のパンツ論」は、ほんのちょっと間をおいてから、新たに展開する予定である。せっかくなのでこの間、みなさんも大いにパンツをいろいろ穿いてみて、自身の意識改革に目覚めていただければ幸いである。自分なりの「パンツ主義」を開拓することは、とても楽しいことだと思う。
身だしなみとしての下着。そして、おしゃれとしての下着。この両面を開化することが何よりも大事だ。
では、ほんのちょっとだけ、間をおきますので。次回をお楽しみに。


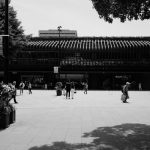
コメント