※以下は、拙著旧ホームページのテクスト再録([ウェブ茶房Utaro]2004年2月6日付「東北縦断・函館の旅」より)。
東北縦断・函館の旅|2004年2月5日~6日
新幹線に乗ったのは、高校の修学旅行以来で、あの時は山陽を回った。既に十数年が経過している。当時私は、新幹線についてこう思った。
〈こんなに速いと、景色がぶれて目が疲れるなあ…〉
旅先での移動中の景色を見ることが好きな私にとって、新幹線はどこか縁遠い乗り物になってしまっていた。というより、1泊以上の旅行自体が縁遠くなっており、前回のプライベートな旅行は、もう10年も前の群馬県の赤城山への旅である。今回、北海道へは、東北新幹線を乗り継いだ。空の旅もいいが、わざわざ羽田へ向かうために逆方向の東京へ上るより、そのまま北へ向かいたいと思い、列車の旅を選んだ。
小山駅から東北新幹線「やまびこ155号」に乗り、仙台へ。仙台で昼食をとった後、東北新幹線「はやて11号」で八戸へ向かう。八戸から函館までは、特急「白鳥11号」。だからつまり、東北を縦断し、青函トンネルを通過して、北海道の地へ下るのである。
初めて乗る東北新幹線及び特急で乗り継ぎがあるため、結構忙しい旅になるかなと思ったが、それほどでもなかった。むしろ、始まってしまえば、ゆるゆる旅である。私は、車窓からの景色を眺めるのが好きだ。まして、初めての東北である。そこは一面の銀世界、と思いきや、トンネルを越えると青空が広がり、またトンネルを越えると、今度は雪がしんしんと降り積もっている。その繰り返しがしばらく続く。
かくもこの日は、単調な車窓にはならなかった。ゆるゆると冬景色を堪能している自分が、贅沢に思えた。東北の景色、それも厳冬の景色は美しい。日常とは切り離された空間、と言えばいいのだろうか。山と山が点在し、新幹線の高架から、その山の中腹にある古道が見える。景色自体は一瞬で切り替わるのだが、私の脳裏にその古道が焼き付いてしばし離れない。
――幼い頃に見た古道の風景を思い出す。私の住んでいる町は、ここ20年の間に方々で宅地開発が進んだ。その結果、今となっては和めるような緑が著しく減少してしまった。昔は、田畑を挟んで深い原野が散らばっていて、日が落ちると、沼地に棲むカエルどもが声を荒げ、辺り一帯が暗闇に包まれたのである。およそ数百メートル先に、原野が広がっている。その奥に向かって延びた古道を、幼い頃歩いた記憶がある。古道が原野に差し掛かった処には、1軒の小さなパン屋があった。今思い出すと、ひどく寂しい風景である。パン屋に入ると、中学生くらいの女の子があとから入ってきて、茶髪に染めたパン屋のおばさんにこう訊いた。
「コッペパンください」
おばさんは答えた。
「今あいにく、ないの」
「…そうですか」
「食パンにしますか?」
その時の“コッペパン”という言葉の響きと、快活な雰囲気のあった女の子が、会話を遂げてにわかに暗く沈んだ落差は、忘れることができない。小さなパン屋の営み…朝食を楽しみにしていた女の子…そこに出くわした自分――。私がその古道を歩いたのは、おそらくその一度きりであったと思う。
東北という風景
私にとって旅とは、「自分と向き合う」こと。ほとんど鉄則に近い。長い時間をかけて自分と向き合う。そうすることによって、その旅は自分にとってかけがえのないものになるのではないだろうか。
午後2時過ぎ、八戸を出発。やがて浅虫温泉~青森を通過。冬の下北半島もまた、やけに霊性を帯びているように感じられ、近寄りがたい。
雪景色というのは――あるいは東北に限った雪景色かもしれないが――風に吹かれる降雪と、行き場を失った霧とが乱雑にぶつかり合って、視覚的に見えるものと見えないものとができる。津軽海峡が目の前に見えつつ、その遙か遠い先の半島は見えぬ。南には八甲田がそびえている。しかしこれも見えぬ。見えぬものを想像しつつ、その想像の限界を感じる。
雪景色とは、常に消え去るものの風景だ。結局のところ、津軽海峡を頼りに進路を掌握するしかないのだが、その底冷えするような海峡を、畏怖の念を抱きながら道しるべとするには、いささか身を委ねられぬ不穏さがつきまとう。トンネルを越え、北海道の地が顕れる頃には、私の内面の何かがはぎ取られてしまうのではないかという不穏さ。ゆるゆるではありながら、これほど官能的な途上もない。
東北といえば、高校時代の国語の教科書で学習した、柳田国男の「清光館哀史」(「定本柳田國男集」第2巻『雪國の春』所収)を思い出す。九戸・小子内にあった清光館という宿が没落したという話である。
授業では、地方の祭事(踊り)に関するプリントが配られ、柳田国男の民俗学について触れた。女ばかりの盆踊りが、男に向かって呼びかける恋歌と伴って、一夜の快楽への求愛の儀式であったことを遠回しに教えられた。
実にそれが遠回しで、私自身困惑したのを覚えている。柳田国男の民俗学的感性が、その文章の随所にちりばめられているのだが、そういった部分の理解には到底及ばない。「一夜の快楽」とは何か――そのことに力点を置かれて遠回しに授業が進められたので、前半の清光館の没落が、なんの味わいもなく薄弱な印象しか持たれなかったのである。しかし、その時のプリントと教科書は、今でも残っている。私にとっての強い関心は、むしろ「清光館とは一体どこにあるのか」、ということだった。
青森を抜け、青函トンネルを越えて北海道の地を踏む。午後5時を過ぎる。厳冬の山並みと海岸を列車が走り、日が沈む。この日の旅も終わりに近づいた。夜の函館は、散る雪と共に更けていった。いくつかの不穏さは、強烈に焼き付いた光景的記憶となって昇華され、旅のモチーフとなった。これが冬でなかったならば、このようなモチーフは生まれなかったであろう。 もう既に過去の記憶となりつつある、旅の車窓を、じっくりと思い返しながら、私は眠りに就いた。眠りは深く、深夜に目覚めることはなかった。
函館の町の銀世界
函館での朝。朝市へと向かい、土産物のカニとエビを買う。味は昨夜の夕食で堪能済み。カニの脚の天ぷらはうまかった。降雪は、写真を撮るのに厄介だが、今回はそれが目的。
ちなみに今回持参したカメラは、Panasonic Lumix DMC-LC5。小ぶりとはとても言えないボディだが、レンズがいいので重宝している。ともかく、被写体を探し歩いているから、寒さはほとんど感じなかった。コートの内側に着ているフリースがありがたい。
末広町を抜け、大三坂を過ぎたあたりで、さらに坂を登ろうとしたが、やはり雪で滑る。3歩ほど進んで戻ろうと思った瞬間、本当に滑って転んだ。受け身の達人(!)なので、しりもちを付いただけで済んだ。が、やはり危なかった。幸いにもカメラは無事。何があってもカメラだけは守る。カメラが壊れたら、何しにここへ来たのかわからないからだ。
「金森赤レンガ倉庫」まで歩いて戻り、また土産物を買う。操り人形式のオルゴールが欲しかったが、少々値がはるので諦めた(でも欲しい…)。その他のアンティークなオルゴールもいくつか買いたかったのだが、今回はやめにしておいた。函館よ、また来ます!



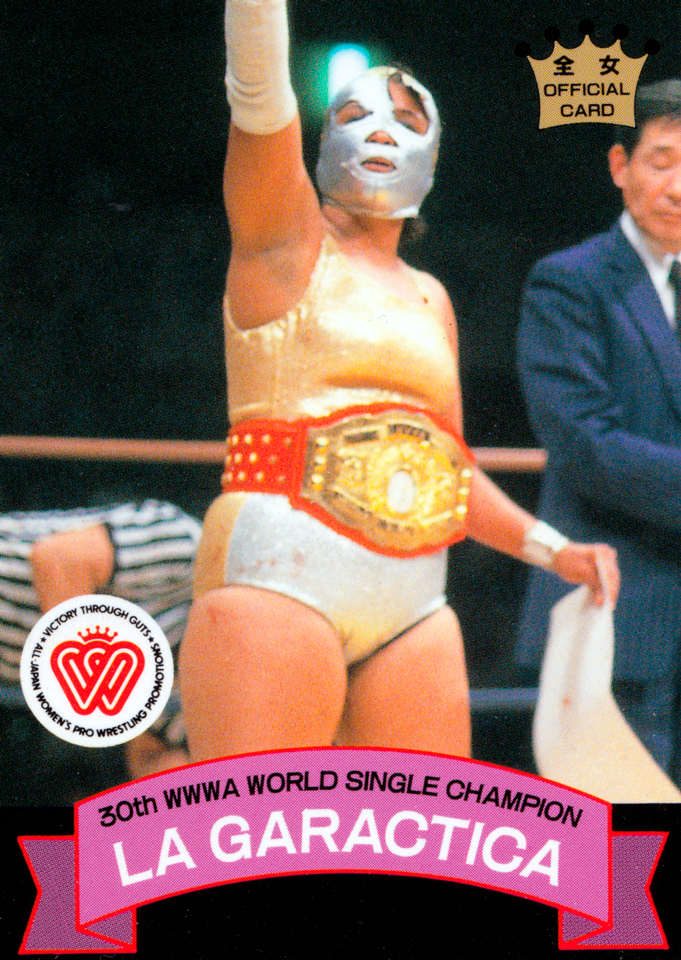

コメント