 |
| 【庭に咲いていた紫の花】 |
ちょうど『星の王子さま』(サン=テグジュペリ著、岩波書店)を読み終えた後、岩波の『図書』4月号を開いてみた。すると、詩人の伊藤比呂美さんのエッセイ「バオバブの夢」というのがあったので読んでみた。やはり“星の王子さま”という言葉が出てきた。
“バオバブ”と言えば“星の王子さま”であり、またその逆もしかり。5番目の節で出てくるバオバブのおそろしい話では、王子さまが知っているなまけものの星に生えた、3本のバオバブの画が登場する。それはそれは衝撃的な画で、まさにおそろしいのである。
そんなおそろしいバオバブの大株を、つい衝動買いしてしまった伊藤比呂美さんは、それがもしかするとバオバブではないかも知れないが「バオバブ」と呼んで、家族の一員と化しているところが面白い。植物に詳しい伊藤さんでさえも、《路傍で見つけた草ひとつ、姿を見きわめて名前を知るのが容易じゃない》と書いているし、植物の素人の私は尚のこと、本当にそう思う。てんで名前が分からない。
花の美しさが分かるか――ということを自己に問うて、私はそうしたことを肝に銘じて庭先の花などを写真に収めたりする。一眼レフカメラを独学で修練し始めた際、いちばん難しいと思ったのが花を撮ることであった。今でも難しい。
ただ、なんとなく、花と会話をするのが良いということを学んだ。花はただ風に揺られているのではない、花自身の気分で揺れているのだ、と思うと、写真の構図がけっこう固まる。枯れきった花も美しいし、まだ蕾のままの花も美しい。しかし、その美しい花の名前が分からないのだから、とても困る。
『赤毛のアン』の作者ルーシー・M・モンゴメリは、その著書の中に花々の名前をつらつらと並べて、その風景のディテールを見事に描写している。例えばこんなふうに。
《外の大きなさくらの木があまり近くにあるので、大枝が家にあたった。それには花がびっしりで葉っぱは一つも見えない。家の両側は大きな果樹園で、一方がりんご、一方がさくらんぼだが、そこもまた花ざかりだ。そうしてその下草というと、いちめんにたんぽぽであった。下の庭はライラックの花。その甘くつよい香りが朝風にのって、窓までただよってくる》
(ルーシー・M・モンゴメリ著『赤毛のアン』中村佐喜子訳・角川文庫より引用)
モンゴメリのように次から次へと花の名前が出てくるのは、さぞかし気持ちいいだろう。ちなみに、高柳佐知子著の『「赤毛のアン」ノート』(ちくま文庫)では、これらの繊細な描写をもとに、赤毛のアンの世界がイラスト化されて見ることができる。こちらもまた秀でた描写力だ。
*
転じて、テグジュペリのバオバブの話は、作家ジョナサン・スウィフトの創作から起因する宮崎駿監督の映画『天空の城ラピュタ』でも見受けられる。あまりにも有名なこの映画のストーリーを述べるのは避けるが、人間の住処はほったらかしにするといとも簡単に植物によって駆逐されていく。
 |
| 【鉢植えで咲いた花々】 |
伊藤比呂美さんが「バオバブの夢」の中でこのように書いている。植物というのは動物と違って、《死んでも死なない。死ぬは生きる。生きるは死なない》。このことの幸福と悲劇が、人間風刺あるいは社会風刺となって、バオバブのおそろしい話やスウィフトの創作に表れる。そして植物の顔とも言える花冠は、美しさと恐ろしさの表裏一体の顔でもあるのだろう。
――気がつけば、目と鼻の先に、ある一軒の廃屋があることを私は思い出した(これは前々回に書いた少女の家ではない)。
家の主を失ってもう数年が経過した。かつて、その家の子供達は元気に外で遊び回って、賑やかな夏を過ごしていた。やがて破滅の日がやってきた。彼ら家族はばらばらとなり、そこに誰も棲まなくなった。
家の庭には無数の雑草が繁茂している。無論、私はその雑草の一つ一つの名前すら知らない。《死んでも死なない。死ぬは生きる。生きるは死なない》。凄い名言である。

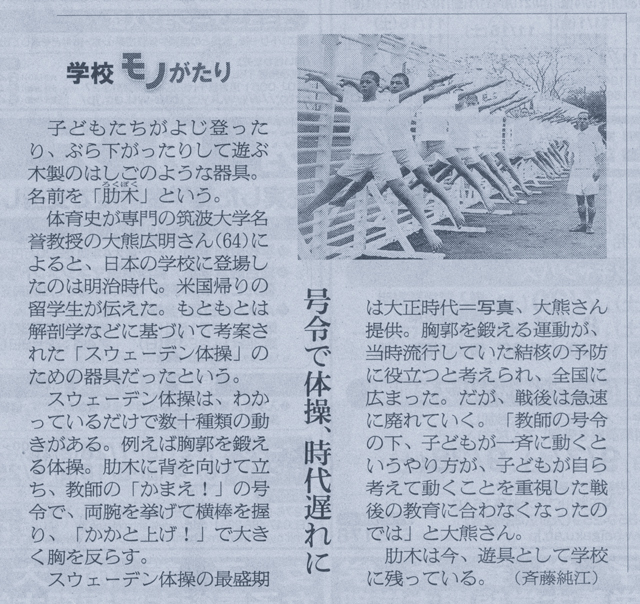
コメント