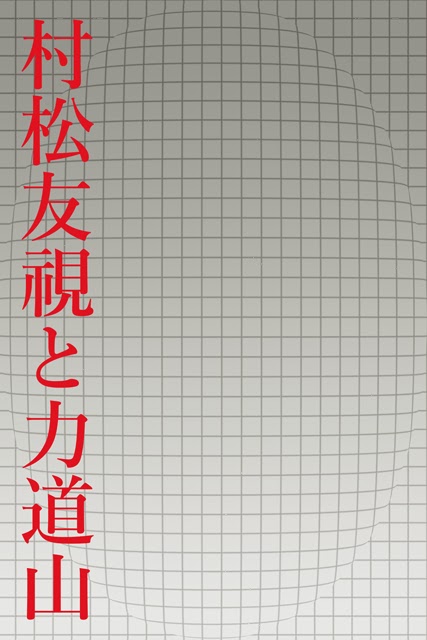 |
| 【これは本の装幀ではありません】 |
ふと、文庫本に目を通すと、2月19日の今日は、昭和29年蔵前国技館で力道山と柔道王・木村政彦が、対する〈王者組〉シャープ兄弟との世界選手権を行った日であることに気づいた。こんな寒い時期に“力道山プロレス”が幕を開けたということ、そしてこの時始まったテレビジョンのプロレス実況中継によって、ラジオの時代からテレビという新しいメディアの黄金時代へと時代が変化していったのだということを、思った。
あの時代、“怒濤の男”と称された力道山(百田光浩)のプロレス人生、加えてそのあたりの昭和史を絡めたノンフィクション本。それが、村松友視著『力道山がいた』(2000年朝日新聞社)である(※「視」ではなく〔示〕偏に見が正しい)。
私は何年か前にこの本を買って、読んだ。読んでいるうちにさらに詳しく知りたくなって、村松氏が昔プロデュースした映画『ザ・力道山』(高橋伴明監督・1983年松竹富士)も観たりした。明らかにそれは力道山に対する何度目かの改まった個人的興味であったが、次第に私はその興味が力道山から外れていき、村松氏本人へと転移してしまったのを覚えている。作家としての村松友視はとても不思議な人だ。
映画『ザ・力道山』では、山下洋輔トリオのジャズがBGMとなって、ぎこちなく歩き回る村松氏の後ろ姿や横顔が印象的である。映画の始めの方で村松氏が、かつて赤坂に在ったニューラテンクォーターの店内を歩き回るシーンがあるが、なんとも言えない風情を感じた。作家でありながらその枠に収まらない。映画の主人公は力道山なのか村松氏なのか、観ていて分からなくなってしまった。
その後のシーンで、松竹大船撮影所の倉庫でフィルムを取り出すショットが出てくる。大船撮影所と言えば――むろん松竹映画の撮影所なのだが――昭和の“巌流島の決闘”力道山対木村政彦戦の調印式が行われた所でもある。
改めて、力道山対木村政彦戦(昭和29年12月22日蔵前国技館で行われたプロ・レスリング日本選手権試合)の映像を観てみた。ここからは少し、専門的なプロレスの話をしたい(拙著ブログより「映画『力道山』」や「木村さん」も参照)。
*
 |
| 【ベルトを腰に巻いた力道山フィギュア】 |
映画『ザ・力道山』の中で村松氏も語っている。この力道山対木村戦に関して、いかなる政治的な経緯や内幕があったとしても、力道山が木村政彦を最後の数十秒でノックアウトする、あの容赦なく力強い猛烈な攻撃は、誰が見ても圧倒するものであり、有無を言わせない凄みがある。
ああいったものを観客の前で見せた力道山は、それがたとえ自制心を失ったものであったとしても、プロ・レスラーとして抜群のセンスと運動能力を持ち合わせていた。
力道山はシャープ兄弟の招聘から1年も経たずして、タブーであったメインイベンター同士の日本人対決をやって見せた。相手が最強の柔道王だからこその大勝負である。おそらく、早い段階で昭和の“巌流島の決闘”をやると、心に決めていたのだろう。それは、新しいテレビ時代の、ある意味テレビ的な、レスリング・ショー興行としての伏線、仕掛け、シナリオであり、最大級の切り札でもあった。
プロのレスラーとしてリングに上がるのだから、当然木村政彦も、そうしたレスリング・ショーのシナリオは百も承知である。元大相撲出身の人気者がプロ・レスという新しい格闘技をやる、それをテレビで中継する、全国的に有名になる。そして“力道山プロレス”(日本プロレス)と提携協力することで自分自身も、所属プロレス団体の興行や柔道界の宣伝になるという旨み。商業プロとして考えれば、当然の論理だろう。
さて、力道山対木村戦の話である。
この場合、お互いの勝ち負けについての折り合いは事前に済ませておいたはずであった。あれから60年経った今でも、その中身についての情報というか議論が錯綜し、偏った情報も少なくなく、実際のところはよく分からない。
しかし、私が映像を観て思ったのは、明らかに試合の中盤以降、力道山と木村政彦の動きがぎくしゃくしていて、事前の打ち合わせは既にこの時、空中分解していたのではないかということだ。
試合の後半、ロックアップの状態から木村が得意の一本背負いを狙う。力道山は「投げられて受け身を取る」プロレスのセオリーをこの瞬間、完全に拒否した。力道山はある時間経過を機に、事前のシナリオをリセットする気だったに違いない。
一本背負いを拒否した後、力道山は直ぐさまスリーパーホールドすなわち頸動脈を締めにかかっている。さらに立ち上がった状態でチョーク気味のフロントスリーパーに切り替えるが、木村は危険を察知した。力道山も木村の態度に気づいて締めを外す。この流れはきわめて不自然である。
その後、不自然なロックアップが続く。プロレス的な技の流れに続いていけない。既に木村は力道山の動きに不穏を感じて、試合の流れを意図的に止めているように見える。
木村政彦の、故意かどうか判別しにくい“つま先蹴り”は、金蹴りとなって、力道山の下腹部にヒットする。これが力道山の感情を逆撫でした。この直後、あの猛烈な攻撃で木村はコーナーに追い込まれ、低い体勢でタックルを試みるが、逆に力道山の“つま先蹴り”の波状攻撃で木村は、無残な姿となる。コーナーで呆然と立ち尽くす木村に対し、力道山はナックル気味の強烈な張り手を木村の顔左側面に打ち、続いて右側面にも張り手を打った。木村はマットに沈む。
*
この試合はいくつかの偶然が重なっているものの、力道山の(力道山陣営の)の「力と政治の論理」による陰謀によって、木村(陣営)が敗北した決定的な試合である。皮肉にもこの試合のかたちによって、“力道山プロレス”的なプロレスが、日本のプロレスの源流となって、やがて総合格闘技の夜明けとなる申し子達に支持されていくのである。
こんなプロレスの古い話はさておき、そうした諸悪を含めたプロレスという異端な世界を、それを持ち上げるのでもなくけなすのでもなく、冷静沈着に、昭和の一事件として力道山を題材にしてしまった村松氏の《嗅覚》は、いま私の中でえらく新鮮で快活を覚えてならない。言い換えれば、村松氏の文体がどうも心地良い。
ちょうどあの頃、村松氏自ら出演したサントリーのコマーシャルがあった。“ワン・フィンガー”だとか“ツー・フィンガー”だとか。あれが頗る格好いい。
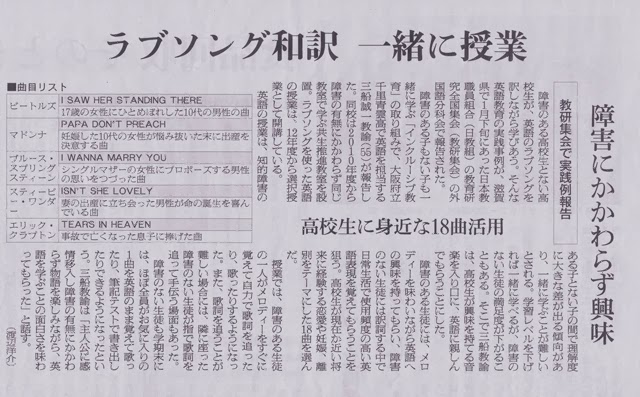

コメント