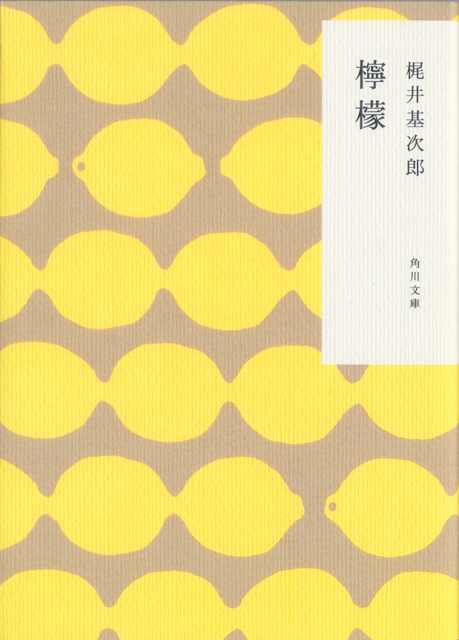 |
| 【梶井基次郎『檸檬』(角川文庫)】 |
筑摩書房の高校国語教科書『新現代文』で梶井基次郎の「檸檬」を読んだ。
この教科書は私が高校時代に使ったものではない。まだ10年前の新しい教科書だ。したがって「檸檬」のあちらこちらには、この教科書の以前の持ち主の、傍線やら注釈がこまかく丁寧にいっぱい書き込まれてあって、それこそよく学習した形跡で感心はしたのだが、私が読み返すにはあまりにもゴチャゴチャと――まさにガチャガチャした階調で――読みづらく鬱陶しいので、全集を買う前に角川文庫を買った。私はこちらの文庫版で、「檸檬」を静かに時間を忘れて読むことができた。
私の好きなバルテュスや中村彝の画を初めて見た時の感動のように、梶井基次郎の「檸檬」は私にとって鮮烈であった。檸檬はレモンである。しかし檸檬をレモンと書いてしまうと、この感動がよく伝わらない気がするから不思議だ。
実際私はレモンをスーパーで買ってきた。角氷を入れたグラスに鹿児島あたりの芋焼酎を半分ばかり注ぎ、炭酸水を入れ、最後にレモンを握りしめここぞとばかりの握力で果汁を搾り出して加えた。この時のなんとも言えない爽やかな香り。
――してやったり。どうだ、高校生では味わえぬ感動であろう。どんなに教科書に傍線を引っ張って注釈を書き込んでも、この出来たてのレモン仕立ての焼酎には敵うまい。
そうであった。確かに、《レモンエロウ》の《あの単純な色》とこの爽やかな香りの合致は見事なくらいで、「檸檬」での「私」がこの果物にその五感の刺戟を覚え昂奮したのも頷ける。私もきゅうっとグラスの中の液体を勢いよく口に流し込んだけれど、既製品では決してこうはいかない新鮮な果物の酸味と甘味とその香りと、そして芋焼酎の軽やかな酒精の酒精の苦み。これらの融合一体感は、ゾクゾクとした震えを覚える至福の瞬間である。
*
《えたいの知れない不吉な塊》という表現で始まる「檸檬」は、その冒頭におけるある種の不快な調子がまず渦巻いて、読む人をじっとりと困惑させる。
それを慰める贅沢なものとして、好きであった場所、丸善の商品の美的興奮へと推移する。さらにこまかい場所を挙げ、駄菓子屋であったり乾物屋の乾蝦や棒鱈や湯葉をながめる云々、果物屋と場所が移る。これらは、「私」の《えたいの知れない不吉な塊》から逃れるための彷徨だ。この果物屋を、近所の鎰屋の二階のガラス窓からすかして眺めるのが、いいらしい。
この眺めのいい果物屋で、あの檸檬を買うのである。紡錘形の恰好――。《もう往来を軽やかな昂奮に弾んで》、「私」は檸檬の幸福な感情を伴っていたのに、丸善に入って、再びあの嫌な不快な調子が戻ってきてしまう。丸善の商品の美的興奮はこの時起きなかった。
丸善に陳列された画本の数々が、「私」によってオモチャにされ遊ばれ、その審美的な陳列がめちゃめちゃに破壊される。このあたりの描写が非常に愉快だ。疲労と憂鬱と焦燥と倦怠と。ついにはそれが、一つの檸檬に向けられ、バラバラに積み上げられた画本やら何やらの頂きに、この明るい紡錘形の物体が設置されてしまうのである。
これだけでは、さほど昂奮は甦られない。ここでの最大の画策は、そのままにして立ち去ることである。立ち去って、あの大好きだった丸善を後にする。それは「私」にとっても愉快なことであったが、一方でそれはあの檸檬を置き去りにすることでもあった。眺めのいい果物屋で買ったばかりの愛玩物=檸檬が、持ち主と訣別し、別の世界に置き去りにされる――。
この梶井基次郎の「檸檬」を読む以前に、中村彝の描いた「カルピスの包み紙のある静物」(1923年)のあの水玉の清々しい青色の包み紙の写実が想い出される。
病臥する彝にとって、そこにあったカルピスの包み紙の明るい存在は、あの檸檬とまったく同じだ。皮肉にも、(場所は違えど)彝が通った大事な丸善の画本を、基次郎はオモチャにし破壊する。基次郎が書き上げた「檸檬」は1924年の10月と記されており、中村彝はその2ヵ月後に喀血で死去する。
梶井基次郎が実際、中村彝を知り得ていたかどうかはどうでもよく、私の空想のうちの連関に過ぎない話ではあるが、あの檸檬爆弾が中村彝を破壊した、という尋常でない“絵空事”は、私の中ですっかり定着し事実化してしまっている。
しかも彼らは、おそらく同じであろう《えたいの知れない不吉な塊》に取り憑かれてしまっていた。
ではいったい、私にとって、あなたにとって、檸檬的な存在とは、何であろうか。つまり檸檬はレモンであって、レモンではないのだ。私は気持ちを落ち着かせてから、グラスの液体を口に含ませた。


コメント