またもや“時計”にまつわる話である(当ブログ2013年8月13日付「パタパタ電波時計と学習教材のこと」、同年8月15日付「時計と時刻の話」参照)。
 |
| 【高校国語教科書の中の「ささやかな時計の死」】 |
2005年発行の高校国語教科書『新現代文』(筑摩書房)に村上春樹氏のエッセイが扱われている。「ささやかな時計の死」。普段私は村上春樹氏が書いた小説その他を読んだりしないのだが、教科書のエッセイは文庫版(新潮文庫)の『村上朝日堂 はいほー!』に拠ったとある。先入観なく読めそうな気がしたので、私はこれを読んだ。酒に酔ってジャズやクラシックを聴くまでもない、ありきたりな静寂な時間を過ごすために。
ともかく時計の話である。彼が子供の頃に体験した時計のねじを巻く行為。かつては、時計を動かすのにねじを巻かなければならなかった。時計が止まると、ねじを巻いてまた動かす。日常的にそれは繰り返され、億劫であっても時計のねじを巻くことは所有者(及びその家族)の日課であったのだ。
彼はそれが時代と共に電池で動く時計へと変わって、ねじ巻きから解放されたものの、ニ、三年に一度の電池時計の突然の死――突然の電池切れ――を経験するようになって、その時計の死の「冷たく重いもの」に「宿命の避けがたい到来」を思わせる、と述べている。
私が子供の頃は、既に身近な時計のほぼすべてが乾電池やリチウム電池で動く時計であったし、それがアナログ時計であろうとデジタル数字の時計であろうと同じで、時計が突然止まるということは、電池がなくなって切れてしまったということだと認識できていた。時計の古い電池を取り外して、新しい電池を買ってきて入れさえすれば、時計は再び動き出す。村上氏が仰々しく言うほど、それが「冷たく重いもの」という感覚はない。
むしろ私は、日常的に何の変哲もない時計が、気がつくと止まっていたり時刻が大幅に狂っていたりすると、あっと思い、まるで日常の天使が一瞬だけ非日常の悪魔を召喚したかのような快感を覚えるのだ。その一瞬の空気が変わる様が、私にとってはとても心地良い気分転換となることが多い。
ところが、子供の頃から電池時計に馴染みきっていた私が、ある環境下で、訳も分からず古い時代へとタイムスリップしたような状況になってしまったことがある。
今でもその理由が分からないのだ――。私が小学校を卒業し、中学校へ入学したのは、1985年のことである。増築して3年ほど経過した新しい校舎の小学校を出てその区域の市立中学校へやってきた時、中学校ではまだ木造モルタルの古い校舎であった。つまり新しい校舎の環境から古い校舎の環境へと変わったことになる。
尤もその年に中学校でも新校舎建築が始まり、2年時にはそちらに移ることになるのだが、中学1年の最初の1年間だけは、その木造モルタル教室での我慢続きの体験であった。夏は蒸し暑く、冬は窓の隙間風がぴゅうぴゅう入り込んで寒い。当然ながら床は板張りで、歩くたびに廊下がドンドンと震え、ギシギシと音を立て、午後の清掃の時に雑巾掛けをしてピカピカに光るまで床板をよく磨け、というような古風なことを先生に言われたりもした。
そして何故か、時計も古かった。それが何故だか分からない。教室の壁に掛けられていた時計は、紛れもなくねじ巻き式の古い木製時計であった。とっくの昔から身の回りでは電池時計が一般的だったのに、その中学校の古い校舎の内側ではまだねじ巻き式であった。
すっかり時代がずれていたのだ。古い校舎と古時計という組み合わせ自体は、けっこう見た目の違和感がなく、当時はあまり疑問を感じなかったけれど、明らかに1985年の学校の教室にしてみれば、ねじ巻き式の時計というのは、古すぎた。考えてみればたとえ校舎が古くとも、電池時計に置き換われた時間的猶予は十分あったろうに。
そういう環境下で奇怪だったのは、ねじ巻き式時計のねじを巻く番人の係がいた、ということだ。クラスメイトの中から1名選出され、ねじを巻く係となった男子がいた。その男子はあらかじめ先生から時計のねじを巻く際の真鍮製の金具が手渡されていた。その金具の形状もまた時代錯誤的で古めかしく、小学校の図書室で読んだシャーロック・ホームズの推理小説に出てきそうなものだった。毎日の日課として決められた時刻に時計の文字盤のカバーを外し、ねじを巻く。ただそれだけの係であったが、さぼると時計が止まってしまうので、止まる前にねじを巻く必要があった。
そのねじ巻き係の男子は、新校舎へ移るまでの1年間、時計の番をずっとしていたのかどうか、ちょっと思い出せない。もしかすると半年も経たずに解任させられたのかもしれない。何故なら、その後全教室の時計が電池時計に置き換えられた可能性は十分考えられるのだ。そんな一時の事とは言え、私は確かに、時代に逆行した時計のある教室で授業を受けていたし、その時計が錆びついた鋼と鋼を叩き合う古風な音を発して時を刻んでいたのも事実である。
*
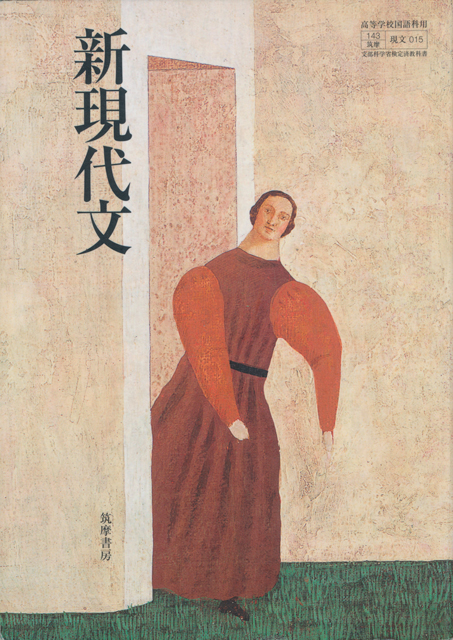 |
| 【筑摩書房『新現代文』】 |
「ささやかな時計の死」の中で村上氏は、死んだ友人の女性からもらった時計が電池切れで止まると、《そういえばあの子も死んじゃってもういないんだなとふと思った》と書いている。その時計を使い続けるかぎり、否応なく電池切れで止まるたびに彼女を思い出すのではないか、ということが感じられる切ない文章だ。しかし同時に、新しい電池を入れて時計を動かせば、彼女が再び呼吸して生きている、という感覚にもなりそうである。私ならそう感じていたい。
先述した中学校を卒業する以前に私は、自宅で長年使い続けていた鳩時計(定時になると小窓から鳩が飛び出してポッポッポと鳴く)をあっさり処分した。秒を刻むカッカッカという高い音と、定時の時のポッポッポが録音の際にノイズとなってマイクロフォンに混入してしまう、ということが分かって、目覚ましのアラームで使う以外、音のしないデジタル数字の時計に置き換えたのだった。
少なくとも子供の頃まで愛玩的な存在だった鳩時計はそこで死んで、無機質なデジタルの時計に置き換えられた時、私自身の時計に対する観念が一変したと言っていい。時計は《時》を伝えるある種の鬱陶しさからモノの役割を終え、単に普遍的に時刻を参照するためだけのサブツールとなった。
それがいったいどういうことなのか。まだ私は人生の半分をようやく通り過ぎようとしているばかりで、《時》を刻むことの喜びと不幸については、まだよく判然としないのである。
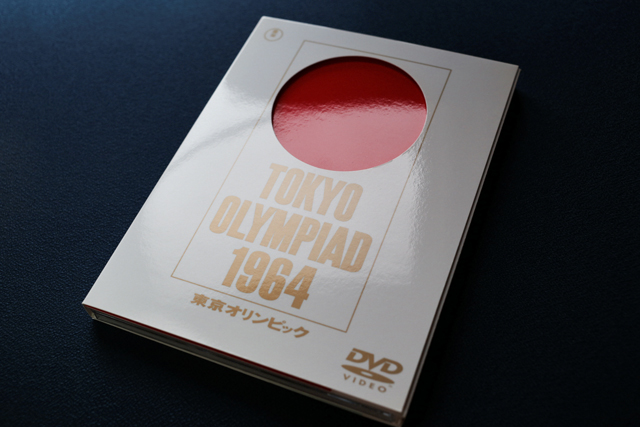
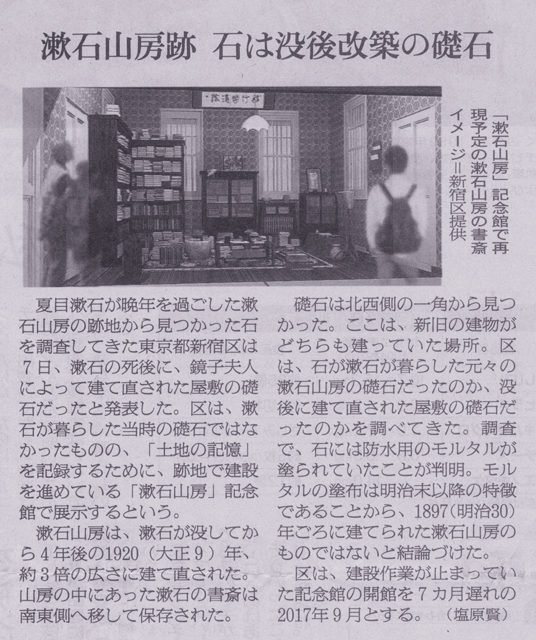
コメント