 |
| 【東博『黒田清輝―日本近代絵画の巨匠』】 |
先月の19日、上野・東京国立博物館にて『生誕150年 黒田清輝―日本近代絵画の巨匠』を観た。
良く晴れた午前。新緑に満ちた公園を抜けて東博の敷地に入り、ユリノキを見上げたその足で平成館に向かうと、彼の2つの画がコラージュされた広告パネルが待ち構えていた。東博ホームページでの広報によれば、4月28日の時点(初日から約1ヵ月経過)で入場者が“10万人”に達したという。会期は今月15日までなので、さらに入場者数が増えるに違いない。
黒田清輝の作品を、私はこれほど多くじっくりと観たことがなかった。私が黒田清輝の名を知ったのは小学生の頃である。切手蒐集をしていた折の、あの有名な、切手趣味週間「湖畔」(1967年発行)だ。そう言えば広告パネルのコラージュの傍らもこれであった。
あの切手は、切手にして気品が漂っていた。湖と山を背景にした全体の色合いは青く薄く、モチーフとなっている婦人の浴衣の薄青色も湖と同化していて協調的。何とも涼しげな“夏の画”だと思った。ひょっとすれば耳を傾ければ、その切手から湖のさざ波の音が聞こえてきそうだった。「湖畔」の作者であり、〈黒田清輝は明治時代の洋画家〉という確固たる肩書きが、私の中に素直に擦り込まれていった。
4年前の夏、同じ東博の本館で展示された『美術解剖学―人のかたちの学び』で、森鷗外や久米桂一郎らの資料と伴い、彼の美術解剖学の「受講ノート」を観たことは、私にとって黒田体験の2度目となった。
「受講ノート」は1888年、黒田清輝(22歳)がフランスの国立美術学校で解剖学の講義を受けた時のノートだ。あの趣味週間切手の原画である《湖畔》は、このようなデッサンの錬磨の賜であり、黒田絵画の筆致の基礎となっていることが理解できた(何故これを私が観に行ったのかといえば、翌月の当ブログ「YELLOWSという裸体」を書くための参考資料としたかったため)。
今特別展では、その頃の解剖講義の写生帖や男女の裸体デッサンなどを観ることができ、4年前に観た「受講ノート」とこれらの習作作品の関連が確認できた。
*
ところで漱石の話。漱石が大正元年、東京朝日新聞に12回にわたって連載した「文展と藝術」という評論の中に、黒田清輝の絵画のことが書かれている。漱石はその年の文展(会場は竹之台陳列館)で彼の画を観ている。
《黒田清輝氏の「習作」である。それには横向きの女の胸以上が描いてあつた。女は好い色の着物をたつた一枚肩から外して、装飾用の如く纏つていた。其顔と着物と背景の調子がぴたりと喰付いて有機的に分化した様な自然の落付を自分は味わつたのである。そうして若し日本の女を品位のある画らしいものに仕上げ得たものがあるとするなら、此習作は其一つに違ないと思つたのである。けれども夫以上自分は此絵に対して感ずる事は出来なかつた》
(『漱石全集』第11巻「文展と藝術」より引用※旧字体を新字体に改め)
前年に白馬会を解散した黒田清輝は当時46歳で、この時の文展の出品作が何であったかを、私は調べた。結果、それが《赤き衣を着たる女》だと分かった。それを確認するために東博の今特別展の図録を開いたところ、そこには既に漱石云々、「文展と藝術」云々という解説文が載っていて、私は呆気にとられた。自ら調べる必要はなかったのだ。はじめからここを読めばよかったのだ。
図録の解説者、いや、もはや《赤き衣を着たる女》という作品は解題研究の既成事実として、漱石の評論「文展と藝術」と一対になってしまっている。《赤き衣を着たる女》と言えば漱石の「文展と藝術」…。私はそれも知らず、逆に漱石の方から調べてその画に辿り着いたわけだが、これは取り越し苦労であった。
文展での漱石はともかく、私は東博の平成館でその画を観た時、確かにその女の姿に釘付けになったのである。無論、その時は漱石云々は何も知らず――。私が釘付けになったのは、婦人の顔の、こめかみに対してである。
こめかみには、この婦人の、この女の情念あるいは怨念のようなものがこもっていると感じた。この画全体に一抹の不安感が与えられているとするならば、それはこめかみの筋肉の緊張によるものと思われる。
単に画のモデルとして緊張していた、だけかも知れない。しかしながら黒田清輝はそれを写実的にとらえ、画のバランスを考慮しながら、書き込んだ。先の「文展と藝術」は、漱石が寺田寅彦を連れて文展を鑑賞した時の評論だそうだが、その“友”と記される寺田寅彦があの画を観て、首から肩にかけてしきりに堅い堅いと言ったと、漱石は書いている。
堅い堅い。
再び図録を開いて《赤き衣を着たる女》を眺めてみた。すると、確かに寺田寅彦が言うように、首から肩にかけての筆遣いが「堅い」のである。裸体の肉感はかろうじてあるが、艶めかしさに欠ける堅さ。この「堅い」という寺田の言葉も、画の批評の永年にわたる既成事実として一対となってしまっているのだとすれば、漱石の罪はまことに大きいと言わざるを得ない。
婦人の唇から頬にかけての、何とも言いようのない丸みを帯びた豊満。耳をほとんど隠している髪のほつれ具合の繊細さ。その耳でさえも、赤みを帯びた色に満ち、見る対象の肉欲を仄めかす。然るに、こめかみ。
こめかみ。
あのこめかみの緊張が、それらを否定し、絶妙な度合いでそれを反故にしている。今更、首から肩にかけてを肉感的に筆致でふくよかにしてみせたところで、全体としての抗えぬ女の情念あるいは怨念は、残る。
そういう意味では、ただならぬ画である。単なる婦人画ではない。女は赤き衣で美しく纏い、静謐な印象を与えているにもかかわらず、何か数奇な運命を抱えているかの如く、暗い。
黒田清輝は日本の近代の洋画発展に貢献した、巨匠。まさかその回顧展で、思いがけず胸を打たれる絵画に出くわすとは思わなかった。
こんなふうにしてあの画の、美を超えたなにものかを私は感じ得たのだけれど、これが彼の代表作である《智・感・情》の精神性の部分と、幾分でも関係あるかということについて、絵画に対して無知である私にはまだまだ探究し得ない領域である。東京美術学校と岡倉天心との関係性においての、何らかの精神性を推理してみるのだが、これ以上の深入りは、今はやめておく。黒田清輝の作品には、他にももっと奥深いものがたくさんあるので、いずれの機会に書くことにする。

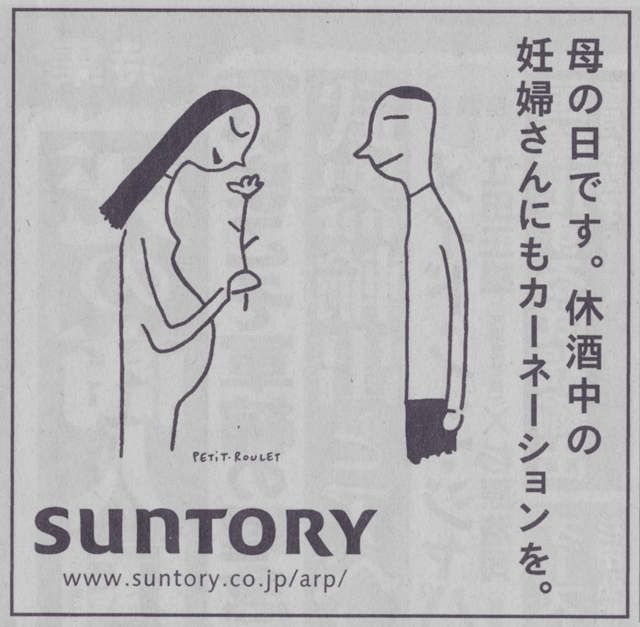
コメント