 |
| 【映画『櫻の園』(1990年)のビデオ版パッケージ】 |
先日、新聞にて、「第41回全国高校総合文化祭」(みやぎ総文2017=総文祭)で催された高校演劇の総評なるものを読んだ。普段、商業演劇しか観ない人にとっては、学生演劇というのはとかく鬼門ととらえがちである。稚拙な演技でなんだか退屈しそうと思いたがるが、実際は、ほとんどそうではない。
むしろ生々しいほどの思春期の刺々しさや倦怠感、喪失感が役柄の素性に盛り込まれることが多く、そうした若年の「リアル」な世界は、商業演劇では絶対に垣間見ることができないもの。私は、時代をうつしとった学生にしか演じることのできない、等身大の若者を観るのが好きだ。そしてまたその「リアル」も、時代によって変容し、とらえられ方も変わってくる。そうした世代間の様々な認識が交差するなかで、演劇性の持つ魅力に尚いっそう、惹きつけられてしまうのである。
その舞台。小間使いのドゥニャーシャが蝋燭台を持って舞台中央へ歩いていく。ロパーヒン役が後ろを続く。第一幕の始まりで、この映画は閉じられる。私たちの心の中は、いつもここで桜の花片を散らし、春という切ない日々を、若い出来事のことのように収めてしまう。映画『櫻の園』はそれを淡々とショパンの変奏曲で彩った、美しい悲喜劇である。
それはそうと、総文祭や高校演劇といったことで思い起こすことがある――。私が20代で演劇をやっていた頃、後輩のメンバーに高校演劇の“ビデオテープ”を渡したのだ。それは、全国大会を制覇した複数の優秀校の演劇を編集した、テレビ番組の録画ビデオであったが、〈こういうものを観て演技の勉強をするように〉という私の意図だったように思う。そんなことをして、演劇に関心を持ったり、演技論を仲間内で交わしていた頃が、ひどく懐かしい。
――あれからもう、20年以上が経った。近頃でも私は、方々の大学生の演劇を観ることがある。演劇の当事者ではなくなったものの、それに向けられる真剣の眼差しは、あの頃とちっとも変わらないのではないだろうか。今、自宅の書棚のあちこちを探し回って、岩波文庫のチェーホフの『桜の園』(小野理子訳)を求めている。どこへやってしまったのか、『桜の園』の本が見つからない。もう諦めて、一冊買おうという魂胆である。そして気持ちを落ち着かせるため、映画を再び鑑賞したのだった。
§
吉田秋生の原作マンガで、中原俊監督の1990年公開の映画『櫻の園』。主演は中島ひろ子、つみきみほ、白島靖代、宮澤美保。私がこの映画を初めて観たのは、おそらく公開翌年の19歳の頃だったと思われる。6年前にもこの映画を思い起こし、その頃のことを書いた(当ブログ「櫻の園という時代〈一〉」)。
――私立櫻華学園高等科の演劇部は、毎年創立記念日にチェーホフの「桜の園」を上演する。その創立記念日の前日、部員の一人が校外で、ある事件を引き起こした。学校の中でそれが問題となり、「桜の園」の上演が危ぶまれる。他の部員達にも緊張が走る。そうした中、この日の演劇部では、幾人かの心が揺れ動かされていく――。
映画を観る前、チェーホフの戯曲「桜の園」を予習しておく必要があるかといえば、それはまったくない。何故なら、この映画は直接チェーホフの「桜の園」とは関係なく、部員達の心理劇が軸となっているからだ。私自身も、戯曲「桜の園」をなおざりにしてきた。そうしたことから、いま私の気持ちは、この映画自体のことと、戯曲「桜の園」のこととで分岐され、〈これ以上後者をなおざりにしないよう配慮せよ〉と、自らに言い聞かせ自戒したばかりなのだ。が、肝心のテクストが見つからない。依然としてやきもきした状況をやり過ごしてはいるが、ここは、映画自体に集中することにする。
以前、この映画のことを書いたとき、《大事なのはショパンの「前奏曲作品28 第7番イ長調」の音楽的なゆらめきのイメージ》という文章を綴った。どういうことかというと、ショパンの「前奏曲作品28 第7番イ長調」はとても短い曲で、例を挙げると、アレクサンドル・ブライロフスキーの1960年頃の同演奏の録音では、たった46秒しかないのだ。たった46秒では、この映画に染み渡らせる音楽とは成り得ない。現にこの映画では、これを解決する画期的な策として、ショパンの曲の雰囲気を均一に保つべく、大胆に拡張して編曲したフェデリコ・モンポウ(Federico Mompou)の「ショパンの主題による変奏曲」(演奏は熊本マリ)が各シーンで流用されている。素晴らしい方法である。
§
ところで先ほど私は、この映画はチェーホフの「桜の園」とは関係ない、と書いた。しかし本当に関係ないとは、言い切れない部分を、その心理劇のうちに見いだした。いや、できうるなら19歳の時に気づくべきであった。人は時となって変化していく。時は人となって変幻するということを。躊躇せず断言する――とまで理解は至らないが。
映画『櫻の園』は、上演を控えた朝、演劇部の部室にて、部員の城丸が彼氏と密会しているところから始まる。それはその日の春らしい日和に似た、とても穏やかで静かな、ありふれた男女の密会だ。城丸はこの日上演される「桜の園」の舞台監督である。上演の進行をいっさい取り仕切るアシスタントである。そんな几帳面で部員達を掌握しなければならない係が、男子禁制の学園で彼氏と密会している。規律を乱してはならないからこその、密会である。学生達の秩序観念はごくありふれて、冷徹には保たれていない。
密会して部室でキスをしているのだから、この学校の風紀は普通にゆるいのだ。このゆるさに佇む女子の品性がとても自然でリアルで、実に若者らしい。またそれは春という芽生えの季節のゆるさでもあると思えるのだが、次に登場する演劇部の部長・清水もまた、校則をわざと破り、髪にパーマをかけてきて周囲を驚かす。さらにこの日は、杉山という生徒が前日、喫茶店で制服姿で煙草を吸っていたところを補導されて問題となり、記念式典の直前に緊急の職員会議が開かれるという事態になる。
それぞれの問題行動は、若さ故の特権である。それぞれの心の内の《秘密》を、決して暴き合ったりはしない。が、共有はされるべきだと思っている。共有はされるべきだが、自分の内々の《秘密》だけは、共有されたくない。この矛盾した考え方自体が、若者の特権である。
部員達にとって最も厳かな日に、自己の心が氷解していく。何か心に縛り付けていたものがほどけていき、春のゆるさの罠にはまって、自らの意志で《秘密》が開け放たれていく。自己にとって心の内の《秘密》と括っていたものが、なんと幼く野暮なものであったかと、「少女」であった自己から、その幼い精神の脱皮を図ろうとする。子供の頃の《秘密》めいたものは、成長と共に確たる《秘密》へと信奉し、その信奉が氷解して明け透けとなっていく頃の過渡期。
「桜の園」上演の日の、個々の内側にある迫り来る危機とは、卒業という《訣別》の儀へ向かうための、明確な意志決定であろう。意志決定とは…。その彼らにとって心の内の《秘密》とは…。紛れもなく、《秘密》という内心の秘め事からの《訣別》の決心を意味している、言わば大人への通過点にすぎない。が、それは、大人への階段を駆け上がろうする感覚から生じた、大きな「罠」でもある。
この日の朝、教員の間で問題視された杉山が部室に現れ、部長の清水と束の間の時間を過ごすとき、まだ我々は、杉山の心の《秘密》を知らない。しかし杉山は、部長の清水が「桜の園」で女地主ラネーフスカヤを演じる倉田を密かに愛していることを、とうに知っている。倉田自身は、どちらかというと無頓着な方で、自分に好意を抱いている清水、そしてその清水への視線を外そうとしない杉山の関係下に対し、何ら苦心している様子はなく、ただラネーフスカヤを演じることだけで精一杯だ。この相関関係は、「桜の園」の舞台にも見事に投影され、ラネーフスカヤ(倉田)の小間使いドゥニャーシャを演じるのは清水、その小間使いを愛する帳簿係エピホードフを演じるのが杉山、となっている。
上演の本番前、部室に面した屋外にて、既に衣裳を着て準備を整えた清水と倉田は、密やかに、二人の時間を過ごす。互いに記念写真を撮り合う。これも厳かな日に取り交わされた、密会である。その様子を、壁一つ隔てた所で、杉山が窺っている。清水の、倉田への核心の言葉の断片一つ一つを、杉山は心をかみ殺して聞いている。そして部室で拾ってあった煙草の箱から1本、吸う。それは、くじけそうな自分の心に対する精一杯の抵抗、紊乱への抑止のあらわれであるが、舞台の上演はこれから、断固として始まる。始まってしまう。もう自分では止めることのできない大人の「罠」だ。
その舞台。小間使いのドゥニャーシャが蝋燭台を持って舞台中央へ歩いていく。ロパーヒン役が後ろを続く。第一幕の始まりで、この映画は閉じられる。私たちの心の中は、いつもここで桜の花片を散らし、春という切ない日々を、若い出来事のことのように収めてしまう。映画『櫻の園』はそれを淡々とショパンの変奏曲で彩った、美しい悲喜劇である。
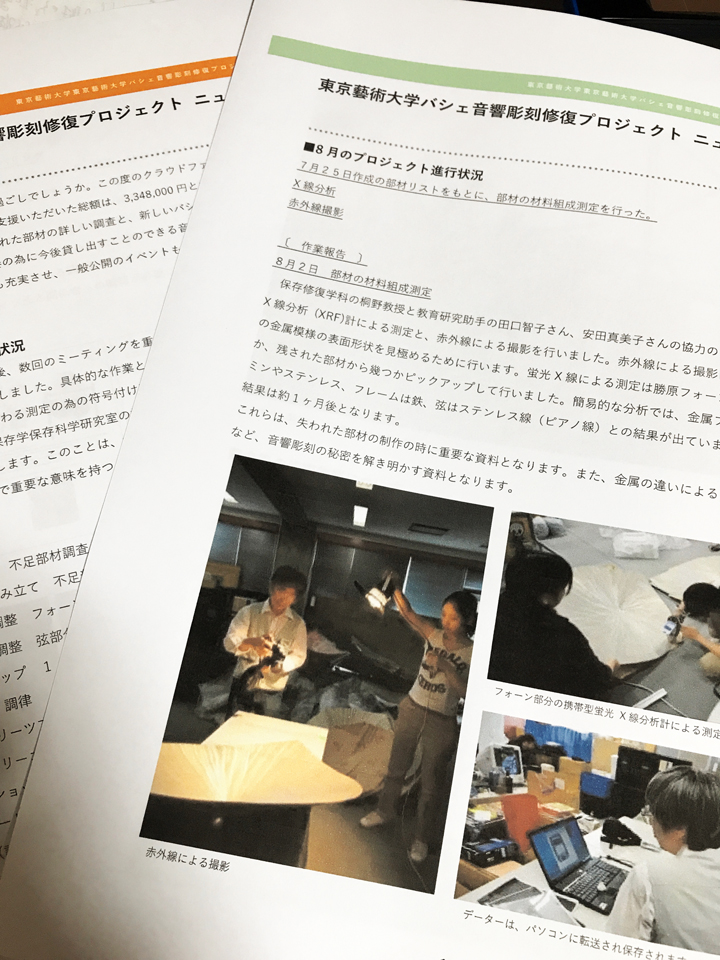

コメント