 |
| 【『洋酒天国』第51号】 |
秋雨が長く鬱陶しい。かくも長き雨の日が続くと、くさくさしてしまって、本が恋しくなる。映画が恋しくなる――。
手に取った『洋酒天国』第51号には、古今東西の映画の、酒を飲む名場面を列挙した「目で飲んだ名場面」などという誌面があって、ジェラール・フィリップ主演の『モンパルナスの灯』がほんのわずか触れられており、私はこの映画に興味を持った。実際にこの映画を観たところ、うーんうーんと唸って思わず身体がよろけそうになった。酔っていたせいであろうか。いやいや、この映画…うーん、モディリアーニねえ、と呟いてみても埒があかない。そう、同様にして埒があかないのが、実はヨーテン第51号なのである。
今年3月のブログ「ごきげんよう『洋酒天国』」で、“ヨーテン”の話題はそれを最後にした…つもりだったのが、すっかり間が抜けた事情により前回は「強精カクテルいろいろ『洋酒天国』」を書き、今回もぬけぬけと壽屋(現サントリー)のPR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)について書く。
§
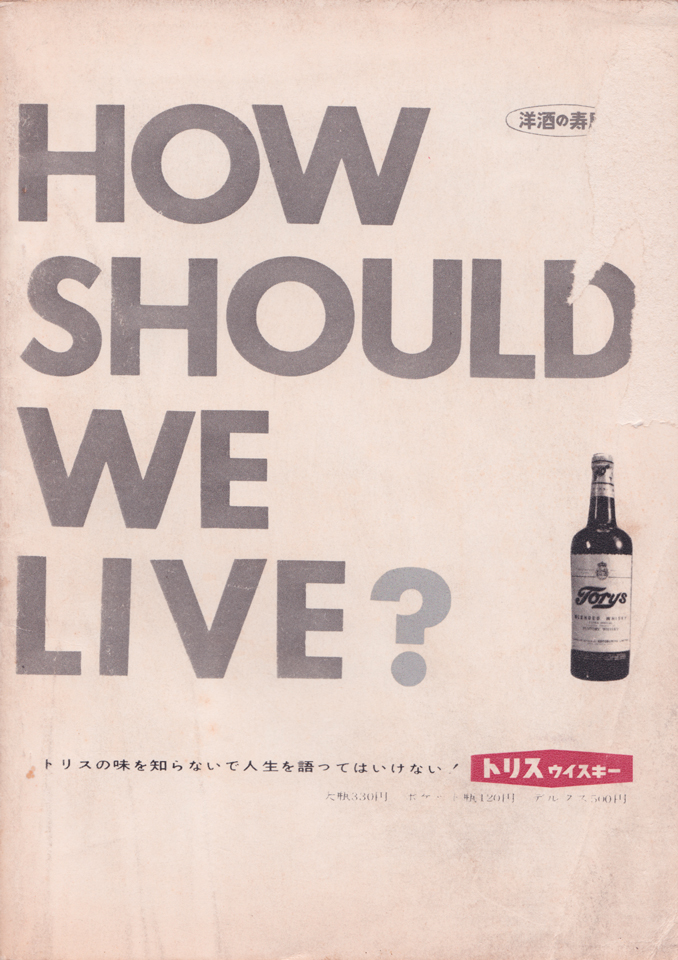 |
| 【裏表紙のトリスウイスキーの広告】 |
第51号は昭和36年6月発行。この号よりそれまでのB6判からA5判と大きくなり、中身の趣向が大きく変わる。昭和36年、当時どうやらリバイバル・ブームだったらしく、第51号ではなんと、大正モダニズムの復古調を企て。大正9年に創刊した娯楽雑誌『新青年』をモチーフに、いくつかの随筆やレイアウトを『新青年』の文章そのままで掲載している。
当時壽屋の宣伝部は多忙を極めており、その前号(第50号)の発行(昭和35年10月)からおよそ8ヵ月のブランクがあった。言うなれば壽屋はこの頃、アンクルトリスの広告やテレビ・コマーシャルが大ヒットし、トリスウイスキーの人気と景気で沸いていたのだ。開高健作のキャッチコピー“「人間」らしくやりたいナ”や、山口瞳作の“トリスを飲んでHawaiiへ行こう!”は決定的な殺し文句となった。そうした宣伝部の多忙な影響をもろに受けたおかげで、皮肉なことに『洋酒天国』はブランクを大きく置かざるを得ず、内容的にも心機一転の模索が図られていたのである。
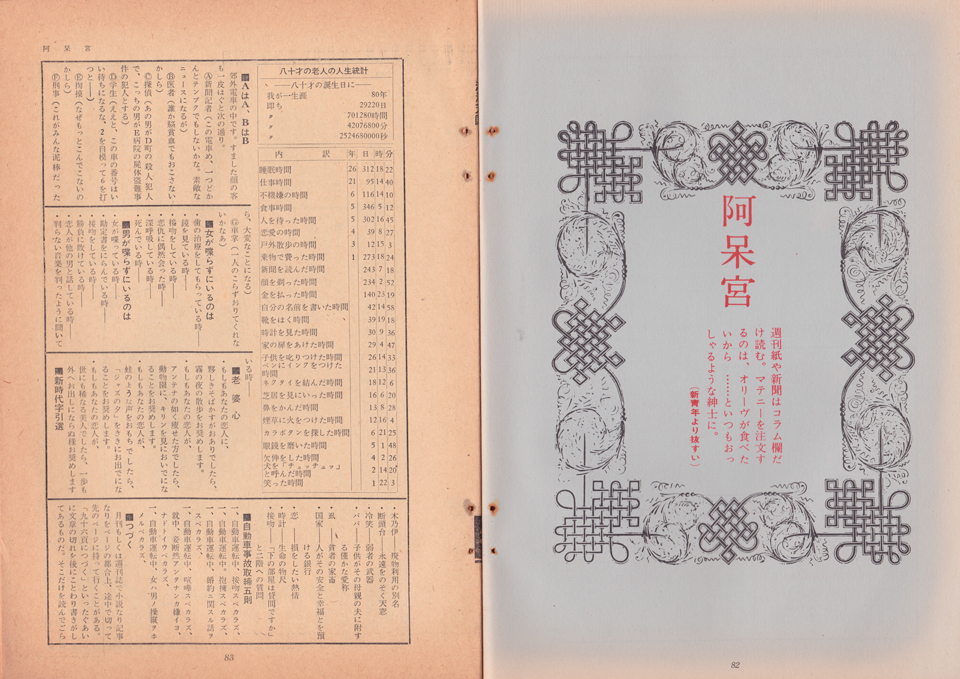 |
| 【雑誌『新青年』風の「阿呆宮」】 |
いずれにせよ、第51号は少々、お堅い。その代わり、硬派な読み物満載である。
トリスバーの陽気な友としての“ヨーテン”の価値は、既にそれまでの旧号で人気を博しており、実証済みである。つまり、お気楽なエッセイとエロティシズム路線。これにユーモアたっぷりのイラストが加わる(坂根進や柳原良平)。酒を飲む夜の男達の気まぐれな視線が、このPR誌にそそがれる。第51号はこれも一つの実験であろうが、一転して『新青年』風となり、その分厚さも170ページと増している。かつての名調子であったお気楽なエッセイとエロティシズムがここではほとんど封印されてしまっている。
さてそれでどうなのかというと、確かに読み物が格段に増え、一冊としたら読み応えあるようにも思えるが、陽気な友、ではない。果たして、『新青年』という都会のインテリ青年層向け雑誌の復古とは、これいかに――。考えてみると、大正時代のその頃に学生で読んでいた青年らは、昭和36年頃となれば、もう三十路半ばであろうか。そうした30代のサラリーマンがトリスバーで懐かしき『新青年』と出合うという構図は、決して悪くはなかろう。しかし、それはそれ。これはこれ。やはり、お気楽な“ヨーテン”の名調子(それを具現化したアイコンがピカロじいさん=アンクルトリス)には、あの暗げなワルツの『新青年』はまったく肌が合わないんだナ、これが。
§
その気怠さを案じているのが、映画『モンパルナスの灯』である。先述した「目で飲んだ名場面」で“つきあいは格別”と題して解説しているジャック・ベッケル監督の1958年のフランス映画『モンパルナスの灯』(“Les amants de Montparnasse”)。一般的には評価が高いが、なんとも暗くていけない。
ジェラール・フィリップが演じたイタリア画家アメデオ・クレメンテ・モディリアーニはただの酒浸りで女好きである。少なくともこの映画では、そのようにしか見えない。モディリアーニの性格が根暗、だから始終、どんよりとした表情しか見せてくれない。
とびきり美人なジャンヌ・エビュテルヌと同棲し始めてからの彼は、やや生活に落ち着きを見せるが、この映画で描かれているモディリアーニは芸術的素養がほとんど垣間見られず、いったいどのあたりが芸術家なのか、よく分からない。つまらぬ男が絵描きとして奈落の底に落ちていくだけの野暮なストーリーになってしまっているが、実際のモディリアーニはどうだったのであろうか。ただし、あれだけ女に愛されていたのだから、文句はなかろう、どこが不幸なのだ、とは思う。
本来、モディリアーニの絵の素晴らしさというのは、あの独特な人物描写とその裸体画の中の一際美しい肌色(赤みを帯びた淡黄色)にこそある。彼の魂の本質的な優しさがそこに表れている。あの映画では、ほとんど裸体画に関して素通りし(1950年代の映画としては無理もないが)、モノクロームだからもちろんその色彩の豊かさを表現することができない。ともかく、「目で飲んだ名場面」は酒を飲むシーンに刮目するエッセイとしてみても、あの堕落極まる酒浸りのモディリアーニをリストアップしたところで、決してお気楽にはならないのである。
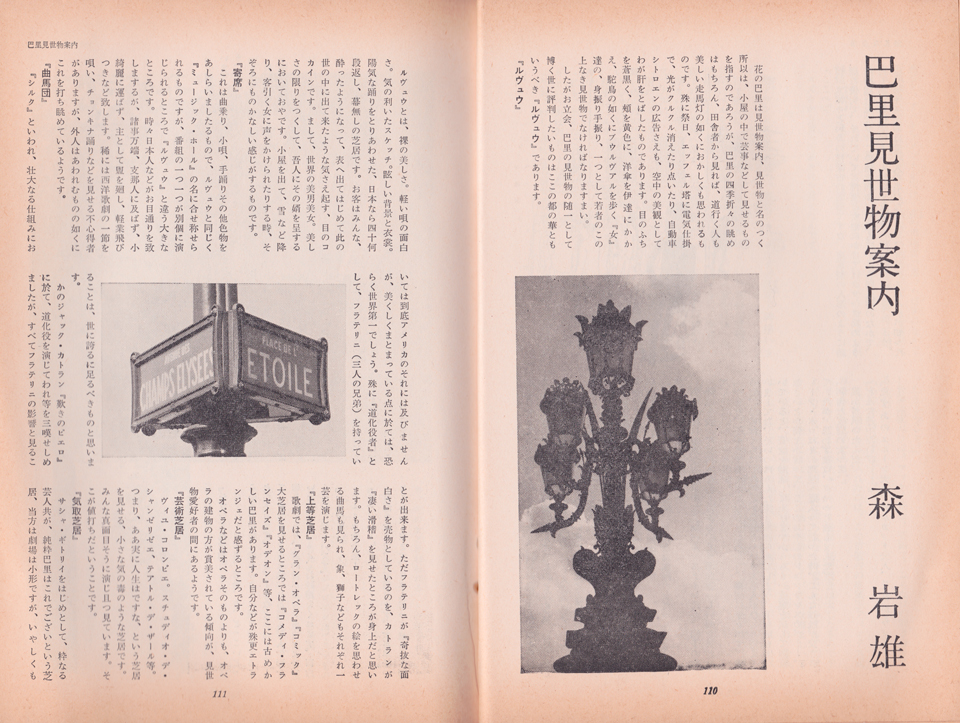 |
| 【森岩雄氏のエッセイ「巴里見世物案内」】 |
森岩雄著のエッセイ「巴里見世物案内」では、なんとかお気楽さを残して、旧来の“ヨーテン”らしさを保っている。
このエッセイは昭和2年6月号の『新青年』に拠る。森氏は当時、映画の脚本家として活躍。また演劇にも造詣が深い。昭和30年代以降は森氏は東宝映画の重鎮となるが、「巴里見世物案内」はまさにモディリアーニが闊歩していた頃の、パリの芝居小屋風情を記録した小品であり、精読に値する内容である。一つだけ挙げるとすれば、「曲馬団」であろうか。
《『シルク』といわれ、壮大なる仕組みにおいては到底アメリカのそれには及びませんが、美くしくまとまっている点に於ては、恐らく世界第一でしょう。殊に『道化役者』として、フラテリニ(三人の兄弟)を持っていることは、世に誇るに足るべきものと思います。かのジャック・カトラン『歎きのピエロ』に於て、道化役を演じてわれ等を三嘆せしめましたが、すべてフラテリニの影響と見ることが出来ます。ただフラテリニが『奇抜な面白さ』を売物としているのを、カトランが『凄い滑稽』を見せたところが身上だと思います。もちろん、ロートレックの画を思わせる曲馬も見られ、象、獅子などもそれぞれ一芸を演じます》
(『洋酒天国』第51号より引用※原文そのまま)
『モンパルナスの灯』に代表される同時代の、つまりジャック・ベッケル的映画のダメな要素を大いに鼓舞し、徹頭徹尾愛し、恣意的には徹底的に批判し、熱くなっていったのが、ヌーヴェルヴァーグの騎士、フランソワ・トリュフォー監督の存在であろう。ジャック・ベッケルではまだエロティシズムの片鱗が浮き立っていないが、トリュフォー映画になると若者が肉となり、モノクロームの中でもしっかりと、モディリアーニの肌色が感じられるのである。ある意味、当時の壽屋宣伝部が目指していた情趣というのもこれ。大正モダニズムの『新青年』に酔っているだけでは、ダメなのであった。


コメント