 |
| 【壽屋PR誌『洋酒天国』第4号】 |
今年に入って時折、シェリー酒なんていうのを飲んだけれど、その他はほぼ確実に、毎夜、ウイスキー一辺倒である。スコッチとアイリッシュである。スコッチは、シングルモルトのグレンリヴェットが美味かったし、いま飲み続けている12年物のザ・バルヴェニーも、スコッチならではのコクがあって美味い。思わず唸ってしまう。
アイリッシュはオールド・ブッシュミルズのブレンデッド。こちらはつい先日、空瓶になった。酒に関しては、日本酒の地酒よりもアイリッシュのラベルの方が親近感がある。おかげでここ最近は、サントリーのトリスも角瓶も遠のいてしまっていて、ジャパニーズ・ウイスキーを忘れてしまっている。あ? そう、かれこれしばらく飲んでいない「山崎」も「白州」の味も、もうてんで憶えちゃいないんだな、これが…。とここはひとまず、肴にもならぬウイスキー談義で嘯いておこう。
§
 |
| 【これは珍しい岡本太郎氏の「酔と夢」】 |
お待ちかね壽屋PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第4号は、昭和31年7月発行。表紙はお馴染み、坂根進氏作のフォト&イラストのコラージュ。
昭和31年(1956年)は、“太陽族”や“ゲイボーイ”といった言葉が流行った年である。ちなみに“太陽族”(タイヨウゾク)とは何のことでございましょう? もはや死語に近いと思われるので、語源について書いておく。
同年、第34回芥川賞を受賞した石原慎太郎の短篇小説『太陽の季節』が新潮社から刊行された。この短篇小説は大いに物議を醸した。そこから“太陽族”という言葉が生まれたのだけれど、ここでは敢えて、Wikipediaからその意を引用してみる。
《『太陽の季節』の芥川賞受賞を受けて『週刊東京』誌で行なわれた石原慎太郎と大宅壮一の対談で、大宅が「太陽族」との言葉を用いたことから、特に夏の海辺で無秩序な行動をとる享楽的な若者(慎太郎刈りにサングラス、アロハシャツの格好をしている不良集団)のことを指す言葉として流行語化した》
(Wikipedia“太陽の季節”より引用)
“太陽族”のみならず、社会の乱れた風紀を取り締まる、という公安的気概が、この時代にはあった。時代の要請でもあった。私は溝口健二監督の遺作映画『赤線地帯』(主演は京マチ子、若尾文子、木暮実千代、三益愛子)が好きである。あれも5月に公布された“売春防止法”に絡んだ話であった。この年の7月には、横山光輝の「鉄人28号」が月刊『少年』(光文社)より連載開始。悪の犯罪組織に少年探偵が立ち向かうというストーリーの人気漫画。こうした少年漫画の世界にも、社会の乱れた風紀への公安的気概が充満する。東京都はこの月、“深夜喫茶”営業の取り締まりを強化する条例を公布。未成年者の取り締まりのほか、喫茶店での宿泊を禁止した。
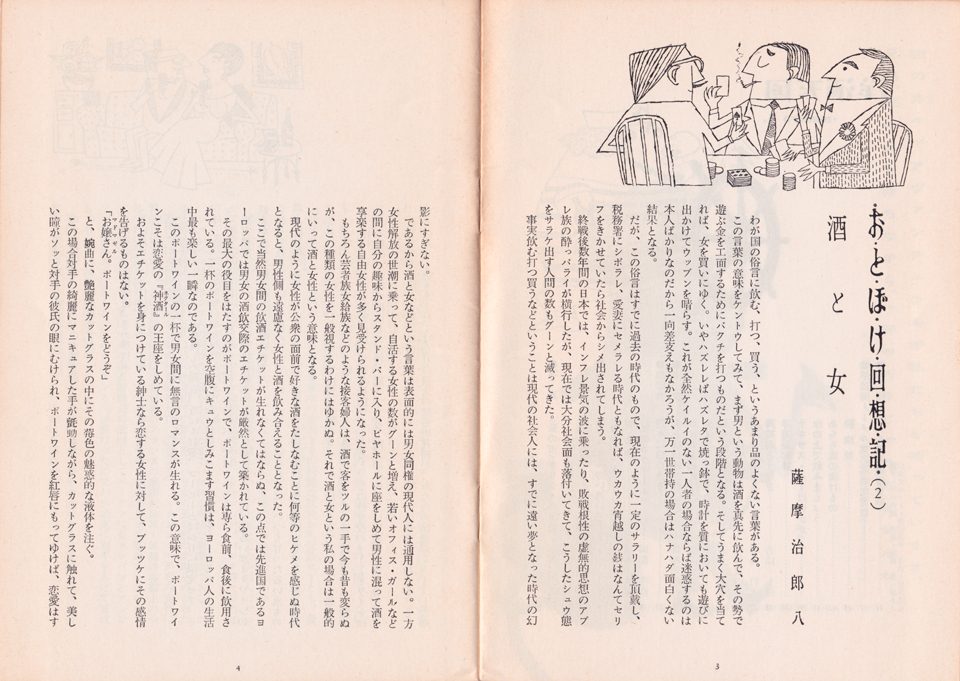 |
| 【薩摩治郎八「おとぼけ回想記」の「酒と女」】 |
さて、昭和31年という戦後11年目を迎えた復興末期の、そのあざとい社会の空気を察知して書き記したのは、薩摩治郎八氏の連載もの、「おとぼけ回想記」の「酒と女」。治郎八氏については、当ブログ「薩摩治郎八氏と藤田嗣治の『洋酒天国』」で少し触れたが、ここでの「酒と女」の話は、いわゆる“飲む・打つ・買う”の俗言への苦言から始まっている。“飲む・打つ・買う”はもう時代錯誤、品が悪い、といった論旨。
“飲む・打つ・買う”の俗言で思い浮かべることがある。ついこのあいだ、上方の落語家・月亭八方氏が芸能生活50周年を迎え、若い頃のエピソードを自身が語っていた。若い頃は“飲む・打つ・買う”を自堕落にやっていたそうだ。その挙げ句、たいへんな借金に追われ、危うく堕落する寸前であった。ここぞと奮起一番、しゃにむに働いて、とにかくテレビやラジオに出まくり、借金を返済した――という話だったかと思われる。
一方の治郎八氏の「酒と女」の話は、“飲む”の趣向に力点が置かれている。いまでは男女同権、女性が好んで酒場を訪れる人が増えた。ここで大事なのは男女間の飲酒エチケット、といったふう。ポートワインを差し出して、甘く女性を口説け。ポートワインは、恋愛の“神酒”(ネクタール)であると。この人の酒と女の話は、ポートワインのように清らかで、とてもエレガントなのである。
§
今号も何かとエロティック。写真家・稲村隆正氏のヌード写真が神秘的でかなわない。
《シンプルな女体の線には複雑な感情がある。ヌード専門ではなかったが、今迄時々撮ってみて居た。現在何かとてもヌードを撮ってみたくて仕方がない。掴みたいものがもやもやして居て、未だ形にはならないが…》
(『洋酒天国』第4号より引用)
 |
| 【写真家・稲村隆正のヌードフォト】 |
黒髪の束を右手で掬い上げ、項を露出させている。突き出た乳房は影となり、密やかな背筋から柔らかい素肌の臀部にかけて、そのしなやかな曲線のうねりに、光が当たっている――。こういったモノクロームのしきたりでは、間接光のグレーが実に艶めかしく美しく映え、この場合、尻の谷間の輪郭線が印象の強い肉欲の刺戟となる。これはまだ、稲村氏の習作の範疇なのだろうか。そぞろ、彼の撮ったヌード写真集が欲しくなってしまう。私にはこれは、真夏の入道雲の空の中、天にそびえる巨人のお釈迦様が、雨風をシャワーに見立て、優雅に寛いでいる写真にしか、見えないのである。
§
 |
| 【田中利一「インカの市場」】 |
そんなこんなで字数を稼いでしまい、岡本太郎氏の「酔と夢」のことも、田中利一氏(朝日放送編成局長)の「インカの市場」のことにも触れる余裕がなくなってしまった。これは困った。
「インカの市場」における田中氏の南米アンデスの旅のフォト・ルポルタージュ。標高3,000メートルはあるクスコでの“市場”と思われる写真は、彼も書き記しているとおり、インカの末裔の風俗を帯び、濃い原色の衣服で身を纏い、ペルーの山高帽で知られる白色の帽子が一際あざやかで、民衆のざわざわとした雰囲気がそこから伝わってくる。
南米の酒ということに関しては、ヨーテンの編集者である開高健氏がとても詳しい。彼が酒について述べた文筆作品を読めばいい。ペルーのブランデーのピスコ(Pisco)はマスカット種が原料、ブラジルのピンガ(Pinga)はラム酒で、原料はサトウキビ。アルゼンチンのワイン(Vino)では、マルベックやトロンテスが有名。吉行淳之介と開高健の軽快な名著『対談 美酒について』(新潮文庫)の冒頭を読むと、この南米の酒のピスコだのピンガの話が出てきて、またこれが得意の“猥談”にもなっていてすこぶる面白い。
あの昭和30年代、南米のピスコだのピンガだのの酒の話など、東京や大阪のトリスバーでは、遠い異国の“大人の”お伽話か寓話にしか思われなかっただろうが、今ではこうした南米の酒が、日本に居て好きなように飲める。なんと自由で幸せなことか。逆に言えば、あの時代で異国の酒の軽妙洒脱に触れられるとは、ヨーテンとはいかに良質な文化誌であったか、と思う。この手の文化の、温故知新を思わないわけにはいかない。

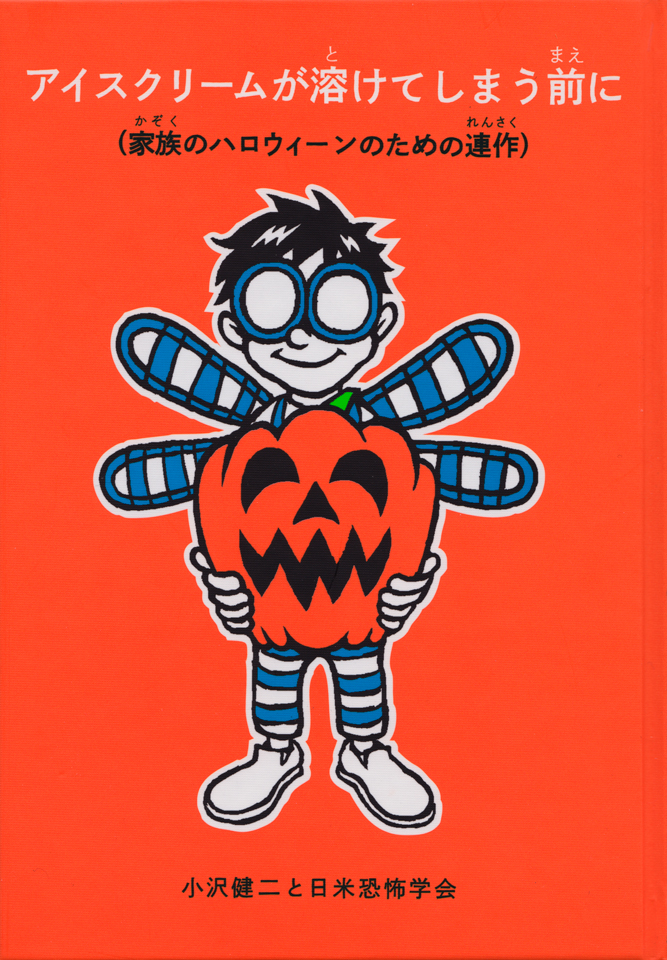
コメント