いま私は中国茶の「武夷肉桂」(ぶいにっけい)を専門店から取り寄せて、そのふくよかなお茶のひとときを、束の間の休息を愉しもうとしている。岡倉天心と私淑するmas氏の話をすれば、おのずとそれはお茶の話になるという筋道が、昨年の前回の〈二〉まで。今回もこれに懲りず、お茶の精神世界を遊行してみたくなった。
§
たいへん息苦しいことに、近所に都合のいい喫茶店がない――ということに時々、悲哀を感じる。ちょっとしたファミレスはあるが、雑然とした周囲は小綺麗な街らしさも、風光明媚な風景も非ず。いわゆる殺風景というやつで、ファミレスに居てもあまり落ち着かない。
心から落ち着く喫茶店というコミュニティの装置が身近にないことは、不幸というか不運というか、心の安寧を損ねるばかりか、日常生活の機微が豊かにならず、とかく生活上のいいアイデアが浮かばないものである。喫茶と書店はずっと以前から私にとって安寧の場所の拠点であるけれど、子どもの頃に憧れた駅前の純喫茶「田園」の、そのまさに純喫茶たる風情は、もはや個人趣味的郷愁感を通り越し、単なる思想的幻想に過ぎなくなってしまった。
 |
| 【2018年5月2日付朝日新聞朝刊「多様性を体現した岡倉天心」】 |
そういえば今年の初夏、“五浦コヒー”というのを飲んだ。これは、茨城大学とひたちなか市に本店のあるサザコーヒー(SAZA COFFEE)が2016年に共同開発したコーヒーである。サザコーヒーの店舗は茨城大の水戸キャンパス内にもある。“五浦コヒー”は、岡倉天心がボストンで飲まれていたであろう浅煎りのコーヒーを再現したもので、飲むとその浅煎りの味わいが口の中で爽やかに広がる。すっきりとしていて喉越しのいい切れ味だ。
5月2日付の朝日新聞朝刊に「多様性を体現した岡倉天心」と題されてこのコーヒーが紹介された。天心は明治36年の夏に東京を離れ、茨城の五浦(いづら)に隠遁。翌年にはアメリカ・ニューヨーク、そしてボストンへ。その後何度かボストンと日本を行き来し、明治39年5月にニューヨークのフォックス・ダフィールド社から『茶の本』(The Book of Tea)を刊行。新聞記事で“五浦コヒー”を紹介した茨城大の准教授・清水恵美子さんは、『茶の本』は茶道の教本ではなく、茶道の心得の《和敬清寂》に通ずる、と述べている。
 |
| 【岡倉天心がボストンで飲んでいたとされるコーヒーを再現した五浦コヒー】 |
《和敬清寂》とは、宋代の劉元甫(りゅうげんぽ)の『茶堂清規』に由来する言葉で、主客が相互に敬い、茶室や茶器などは質素を心がける精神のことを指す。天心が語り尽くした『茶の本』は、まさにその観念を貫き、驚くべきことに現代に甦る“五浦コヒー”もまた、その味わいとしての《和敬清寂》の精神を玩味した飲み物なのである。
§
ところで、岩波文庫版『茶の本』の最初のページには、“岡倉覚三”とキャプションされた、(北京・白雲観で撮られたとされる)天心の肖像写真が載っている。この写真の天心の姿こそが、私の天心像を強烈に印象づけた一つとなっているのだが、つい先日、上野の東京国立博物館にて、「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」と題された企画写真展(撮影者は早崎稉吉、塚本靖、関野貞)を観覧した。
 |
| 【東博・平成館にて「中国写真紀行―日本人が撮った100年前の風景―」】 |
明治26年7月、天心は美術学校生の早崎稉吉(三重県津市出身、東京美術学校絵画科入学)を同行させ、清国(清朝末期)の美術調査の目的で旅に出た。その頃、日本と清国は武力衝突の危機(日清戦争)が迫っていたため、天心らは日本公使館の指示で頭は弁髪、着物は中国服という身なりで出発したという。この時の旅はたいへん難儀なもので、過酷を極めた。遺跡は荒廃し、盗賊から身を守ることにも神経を磨り減らし、粗末な宿では南京虫(トコジラミ)にもやられた。
企画写真展で展示してあった写真は、それより以後の、早崎が明治36年から38年にかけて中国に滞在した際のものであり、この時天心は同行していない。早崎が石泓寺石窟や華山、孔子廟などを撮影した写真を私は見た。そこに天心がいるはずもないが、どこか天心の影が感じられなくもなかった。天心が2度目の中国に訪れたのは、明治39年の10月から翌年の2月までの4ヵ月ほどの旅で、この時は早崎も同行している。
話を『茶の本』に戻す。Chapter 1の「The Cup Of Humanity」の題を岩波文庫版(村岡博訳)では「人情の碗」と訳しているが、ここでは西洋に伝わる茶のエピソードが記されていて興味深い。
ヨーロッパに伝わる茶についての最も古い記事は、アラビアの旅行者の物語にあるとされ、879年以後に広東での主要な歳入の財源は塩と茶の税であった。16世紀の終わりにはオランダ人が、灌木の葉から爽やかな飲料が作られることを報じたとあり、1610年にヨーロッパで初めて茶を輸入したのはオランダの東インド会社である。ヨーロッパでは茶の普及に反対する人もいて、1756年、ジョウナス・ハンウェイは、茶を用いると男は背が低くなり、女も美を失うと述べた。しかし、飲料としての茶はヨーロッパで瞬く間に広がり、18世紀の前半にはロンドンで喫茶店が現れた。茶は生活の必要品となり、課税の対象となった。
《アメリカ植民地は圧迫を甘んじて受けていたが、ついに、茶の重税に堪えかねて人間の忍耐力も尽きてしまった。アメリカの独立は、ボストン港に茶箱を投じたことに始まる》
(岩波文庫『茶の本』村岡博訳から引用)
若い頃、“ボストンチャカイジケン”と初めて聴いたとき、白人の紳士淑女が茶会ですったもんだの大げんかをしてもみくちゃになっている様子を、冗談交じりで思い浮かべて友達と大笑いしたことがあった。茶会で何が事件になるのか、という意味合いで嘲笑したのだけれど、結局この“謎”は今も解けていないような気がして唖然とする。
もちろんアメリカ独立の歴史に出てくる「ボストン茶会事件」(Boston Tea Party)は、そんなような事件ではない。広辞苑を引くとこうある。
《1773年、イギリスの制定した茶条例に反対して、ボストンの急進分子が東インド会社の茶船を急襲した事件。アメリカ独立運動の一契機》
(岩波書店『広辞苑』第七版より引用)
1765年の印紙法に反対したパトリック=ヘンリによる独立運動の演説、そしてトマス=ペインの「コモン=センス」による植民地独立の主張などの影響が、1776年のアメリカ独立宣言に至る。急進分子が茶箱を海に投げ捨て、海がティーと化してこれがティー・パーティーなんだという話(情景)が、どこまで本当でどこまでが比喩なのか詳しく調べていないけれど、茶にまつわる話は面白い場合が多い。天心は茶の魅力についてこう述べている。茶には、ワインのような傲慢さ(arrogance)がなく、コーヒーのような自意識もない(self-consciousness)。また、ココアのような無邪気な作り笑い(simpering innocence)もないと。
次回はその魅力的な茶の、「武夷肉桂」について語る。
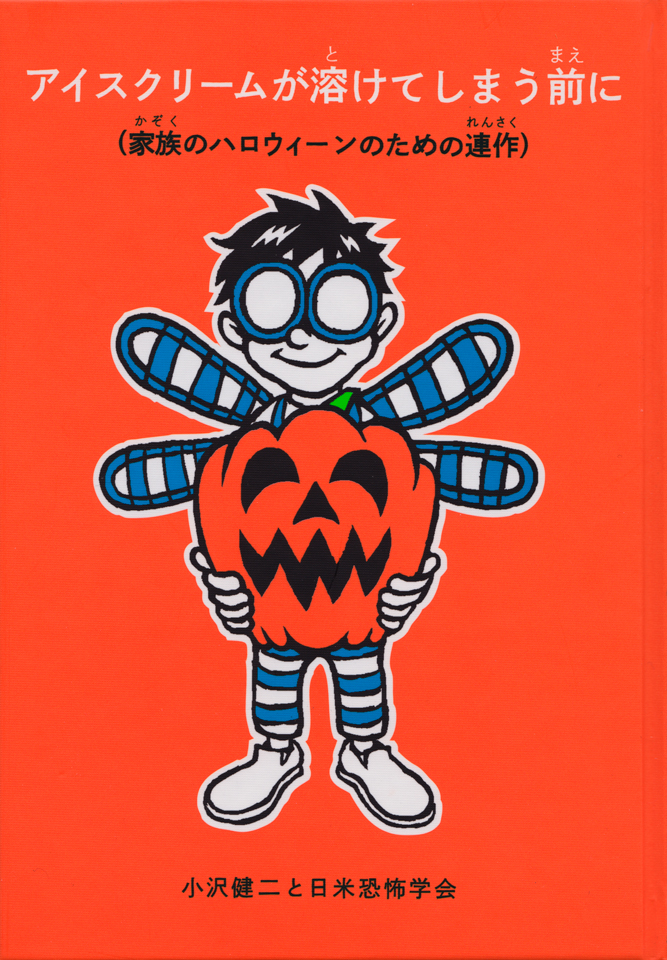

コメント