新宿…シンジュク…Shinjuku――と、かの時代の新宿に思いを馳せてみる。1960年代から70年代にかけての新宿。その頃私はまだ生まれていなかったから、1980年代以前の新宿の空気を知らないし、あまり話にも聞かなかった。知らなかった頃の昭和の新宿が、たまらなく知りたくなる。当面はまず、机上の空想でその頃の新宿という街を読み解いていくしかない。
§
机の上に資料を並べた。グラスに琥珀色の酒を注ぎ、その薫香を味わいながら、新宿の、今よりももっと“図太かった”街の様子を、大雑把に想像してみる。地下階段から這い出た東口付近の通りの、歩く人々の交差とネオンの夜景。どこまでも世相が反映する人々の服装、化粧、身につける装飾品。そして今でこそ、大事そうに片手に抱えるケータイからSNSに夢中になる人々のうつろな眼差しというものは、あの頃には、まったくなかった。そのことは、逆に不可思議な想像と映るかも知れない。思う存分、そんな昔の新宿の街を、心にしみるまで想像してみた――。
昭和の新宿への懐古的空想は、まるで古びて黒ずんだ幻燈機の放つ、妖しい光のように淡く切ない。ゆらめく光が幻影を作り出し、幻影と幻影とが交錯し、《記憶》の襞を刺戟する。
新宿という街は、どこか人々の《記憶》を曖昧にしてしまう負の力がある。特有の後ろめたさが、心の裏側にこびりついて失うことがない。私がかつて、学生時代に街を歩いて目撃した新宿の所々には、60年代から70年代にかけての新宿の幻影なるものが、二重写しのようになって残存していたように思われる。この時既に、私が見た街の記憶は、事実と虚構の境界線をゆらゆらと行き来するような曖昧なものであった。
新宿は、闊達とした街である。時代の変化を感じさせない文化的スケールがある。どういうわけだか今、私は、新宿という街を愛してしまっている。繰り返し繰り返し、そのことを追想している。
確かに中学生の頃は、新宿という街の猥雑さに憧れた。国籍を問わず多種多様な恰好をした大人達が、主体性もなく街をさまよっていることに憧れた。が、街への憧れと愛着はさほど長くは続かなかった。いま再び、新宿という街について思いを馳せてみると、やはり少年時代に見た新宿の、あの大人びた、どこか汚らわしくそれでいて少し寂びて枯れた心持ちの、なんとも言えないざわざわとした雰囲気が、たまらなく脳裏に甦ってくるのである。
きっと、mas氏のせいなのだろう。あの街の猥雑さとラジカルな側面に心惹かれてとうとうと語っていたmas氏に洗脳されてしまったのに違いない。当ブログ「お茶とサブ・カルチャーのアーティクル〈七〉」では、私淑するmas氏の新宿“ゴールデン街”の話に及んで、写真とカメラ、ジャズについて少々論じた。このサブカルの流れを与しなければならない。だから今、新宿という街に対して非常に濃い思いを馳せている。
§
言わずもがな、寺山修司の世界観に染まってしまった――。ここから抜け出せる自信がない。ならば、どっぷりと浸かるしかないようだ。こうして机の上に広げてしまった60年代から70年代にかけての新宿界隈に関する資料を読み漁っているうち、浅川マキと寺山修司の世界にぶち当たってしまったら、とことんそれに付き合うまでなのである。諦めて、映画を観ればいい。
つい先日、寺山修司の1971年監督作品である映画『書を捨てよ町へ出よう』(人力飛行機プロ、日本アート・ギルド・シアター)のブルーレイ版を観た。原作は、彼の著書『書を捨てよ、町へ出よう』――。
私が演劇活動にのめり込んでいた20代の頃、演劇を志す者として、〈シェイクスピアと寺山修司だけは避けて通れ〉というのが座右の銘だった。役者がシェイクスピアもしくは寺山修司の毒気にかぶれだしたら、たちまちその毒が体内を駆け巡り、解毒できなくなる。しかもその毒沼から抜けきれずに溺死するであろうことは明白だったのだ。言わば、シェイクスピア・ワールドの“シェイクスピア俳優”となり、寺山修司ワールドの“寺山修司俳優”になるという、ある種間の抜けた結末として、判で押したような同根の俳優人らが増殖されるのがオチであった。
しかしながら歳を追うと、その毒気なるものを身体の方が欲してくるのであった。愚かな誘惑である。サソリの毒にでも噛まれてみたいとも思う。いや、寺山修司は47歳で亡くなったのだから、その享年の峠を越えようとしている私にとっては、毒は毒とならない。毒が体内に入り込んでも、あっけなく中和されてしまう気がするのだ。
ならば、存分に毒沼に浸かるがよい。寺山修司ワールドの乗り物料金はすべてわしが全額負担いたしますよん、と、あの世の窓から寺山修司が顔をこちらに出して笑っているではないか。それは悪戯っ子のような低い声であったにせよ、悪意はまるで感じられないのである。
 |
| 【文化人の善き住処でもあった風月堂】 |
映画『書を捨てよ町へ出よう』と限りなく同名に近い原作『書を捨てよ、町へ出よう』とは、原作の映画化という関係にはなっていない。それぞれ別物ととらえていい。しかしながら原作も映画も、一貫した寺山修司の信念はど真ん中を通っている。すなわち「大きなタマを持て」ということである。原作ではノーマン・メイラーとアーサー・ミラーの言わば“タマ”の話が出てくるが、この意味を知りたければ、どちらか片方でも鑑賞すべきだ。“タマ”は大きい方がいい――。
ちなみに、私が所有している角川文庫の『書を捨てよ、町へ出よう』の装幀は、緑色のベタ塗りの平成22年改版なのだけれど、この淡い緑色がまた、私が愛するアイルランドの《三位一体》を示す三つ葉のクローバーの色とも競合する。偶然の成り行きながら、気風が同調するかのようで、私の信念もそういう意味では、馬鹿の一つ覚えの風情として一貫している。
§
 |
| 【ヒッピーやフーテン族がたむろしていた風月堂】 |
ともあれ、まだまだ寺山修司のパラレルワールドを無為に広げたくない。ここでは抑制し、映画の話は別稿に譲るとする。その彼がかつて好きで通いまくったという名曲喫茶(あるいはパーラーと称すべきか)「新宿風月堂」(しんじゅくふうげつどう)について書いてみたいのである。
Wikipediaで「新宿風月堂」を調べてみた。
風月堂は、1946年(昭和21年)に新宿区角筈(現三丁目、ビックロのあたり)に開業した、とある。ちょっとこの説明だけではぶっきらぼうに思われる。場所を丁寧に書くと、こうなる。JR新宿駅東口を出て、アルタのある新宿通りを東へと歩いていき、ビックロを越えた新宿三丁目西の路地を右に曲がる。そうして、喫茶らんぷるの向かいの新宿シアターモリエールのあたりが、かつての風月堂――。この界隈には昔、東映の任侠映画で人気を博した“新宿昭和館”という映画館があった(2002年に閉館)。今はK’s Cinemaとなっている。新宿の街のこまかい箇所はいつまた変わるかも知れないという不確定要素が絶えずあるから、人々の心の内の、あの店は今どうなっているのか? あそこにはどんな店があったか? といった街の世俗的な関心度は、決して薄まることがない。
 |
| 【何故これほどまでに福島菊次郎は風月堂にこだわったのか】 |
ともかく、風月堂は名曲喫茶だった。
創業当時すなわち昭和21年の終戦直後は、音源自体が貴重だったクラシックのレコードをかけ、そのクラシック音楽を目当てに客足が伸び、評判を博したのだという。レコードの所有者、そしてまた絵画コレクターでもあった資産家横山五郎がオーナーの風月堂は、別の側面ではアート・ギャラリーであったらしい。Wikipediaには、盛況だった頃の風月堂に訪れた錚錚たる著名人が列挙されていたので、引用しておく。
《滝口修造、白石かずこ、天本英世、三枝成章、三國連太郎、ビートたけし、野坂昭如、五木寛之、岡本太郎、栗田勇、岸田今日子、長沢節、朝倉摂、谷川俊太郎、唐十郎、安藤忠雄、寺山修司、若松孝二、高田渡、蛭子能収》
(Wikipedia「風月堂(東京都新宿区)」より引用)
文化人が多く訪れた風月堂の、在りし日を照射した写真は、なかなか見つけるのが困難である。反体制の社会派で知られた写真家福島菊次郎の写真集『戦後の若者たち Part II リブとふうてん』(三一書房・1981年初版)には、1960年代以降の風月堂の、若者達の賑やかな会話さえ聞こえてきそうな雰囲気、もうもうと燻らせる紫煙、つんとくるアルコールの臭い、まるで幻覚剤がそのあたりに転がっていそうなイメージの写真が多く掲載されており、そうした若者達の、あの時代特有の、体臭でむせかえる雑駁とした風月堂の店内の様子が、モノクロームの写真の中に押し込められていて秀逸である。写真集自体、今となっては入手が難しい稀本となってしまっている。いずれにせよ、当時の風月堂を知る貴重な資料である。
写真集の小題の、「風月堂紳士録」を取り上げ、当時の店内の様子を見ていきたい。
これを写した福島氏も、実は風月堂の常連客であった。当初はクラシック音楽で優雅なひとときを過ごせていたこの店も、《六五年頃になると風月堂の客すじは急に変った》という。異様なほど、騒々しくなったのである。福島氏は店内の客達の雑談のノイズから、耳に止まった横文字らしき言葉を抽出してメモを取った。
《ヌーベルバーグ、イッピーラジカル、ビートニック、コミューン、サイケデリック、アングラポップ、アンダーグラウンド。人名ではヘミングウェイ、サルトル、トインビー、ソルジェニツィン、高橋和巳、唐十郎、寺山修司》
(福島菊次郎『戦後の若者たち Part II リブとふうてん』より引用)
ここでは“ビートニック”と記してあるが、私も50年代以降のビートニク(beatnik)の洗礼のなんたるかを知りたくて、近頃ウィリアム・バロウズの小説『裸のランチ』(“The Naked Lunch”)に手を伸ばした。ある種の心地良い凄まじさが感じられる。これをもし、今の若者が手に取って読んだとしたら、なかなか思いがけぬ感受に苛まれるのではないか。
むしろこれを読むと、みんな“作家”稼業で飯が食いたくなる。腐っていく得体の知れない人生、すなわちそのカンヅメの中身は自分自身である。まったくもって自分自身の身体が腐り始めるのに絶えられなくなったならば、恐怖で家にこもって居られなくなるだろう。そして外に飛び出したくなる。外に飛び出し、作家になろうじゃないか(ここのところは寺山修司の“書を捨てよ、町へ出よう”とまったく同じ主旨)という逆説的心理。
ビートニクの小説でむず痒くなった頭を落ち着かせるためには、悪友を連れて新宿の風月堂に駆け込むのがいちばん――と思った若者は多かったかも知れない。その行動性はまことに理に叶っている。健全である。ヒッピーやフーテンとなって猛烈に他人と会話をしたくなる時代だった、のである。
§
 |
| 【時代を象徴し、思索の場でもあった風月堂】 |
風月堂は、1973年8月をもって閉店した。風月堂が背負わされた役割はこの時代に終わったのだった。戦後の復興期からビートニク、ヒッピー、フーテンといった文化に良くも悪くも煽られ、そのあらゆる功罪の重荷を背負わされて自家中毒となった。だから、風月堂の歴史はあっけなく短かったのだ。本来的に、人々の憩いの場である喫茶は、世俗の感覚の浮き沈みに諍うことができない。今、渋谷の街がその重荷を背負わされている感がなくもない。1970年代初頭、そうした世俗の潮流の、新古の切れ目が訪れたのだった。
唐組の唐十郎(当時は状況劇場)も風月堂の常連客であった。
《もう毎日行ってました。客にはアレン・ギンズバーグの詩集なんか抱えたフーテン族の詩人が多くてね。あのころの新宿には映画関係者がたくさんいたので、その人たちに自分の顔を売ろうという目的もありました。劇作家の竹内健さんを介して麿赤兒に初めて会ったのも風月堂です。初期の状況劇場には、風月堂で集めたメンバーが多かった》
(都市出版『東京人』2005年7月号より引用)
 |
| 【外国人が女性をくどく場でもあった風月堂】 |
この雑誌の同号には、「『あの時代』とは何だったのか 大きな安定の中の小さな反乱。」と題した随筆で御厨貴氏が、1970年前後の時代論を述べていて、思わず納得させられた。
《七〇年前後に青春を送った団塊の世代と、それ以降の世代で決定的に違うのは、後の世代には共通の思想、経験というものがない。団塊の世代が経験した学生反乱が、世代という言葉が当て嵌まる最後の共有体験ではないだろうか。安田講堂の紛争が終わった時に、世代の共通体験はなくなったのです。団塊の世代が今でもわりと団結力があるのは、共通体験があるからで、それ以後の世代にはほとんどありません。安田講堂以降の三十年余は、そういう意味で切れ目がまったくない。その上に皆バーチャルになってしまった》
(都市出版『東京人』2005年7月号より引用)
何か、言いようのない思いが込み上げてくる。新宿の街をあてどもなくさまよってみたい、とも思う。そこにはまだ、昭和の強烈な何かが、残っているかも知れないのである。




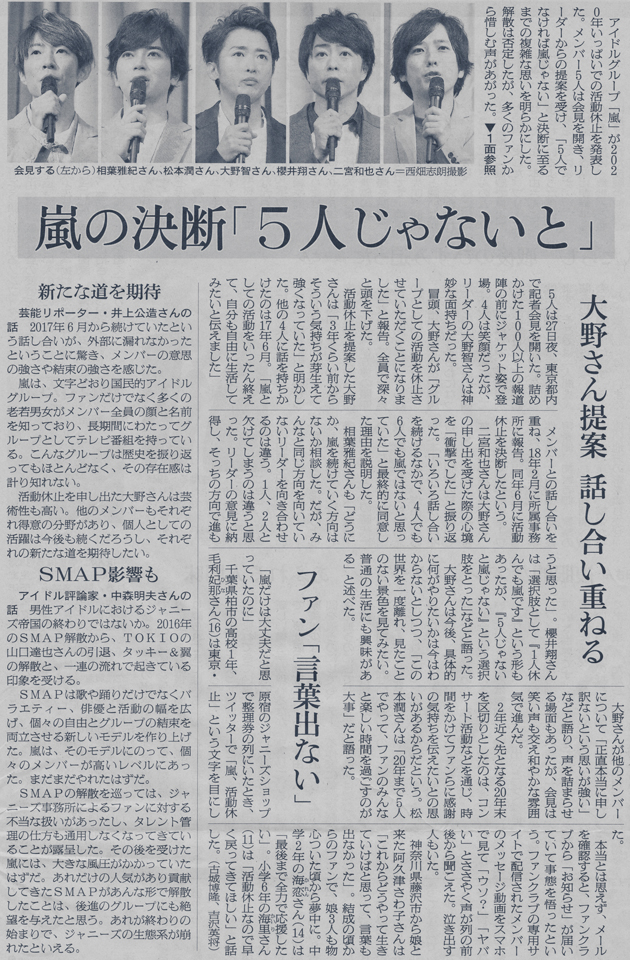

コメント