 |
| 【1983年刊、サントリー音楽叢書③『エロス in Music』】 |
個人的にここしばらく文学や演劇に関しては、寺山修司に着目し、その周縁の人々や作品に没頭していたいと思った。ごく最近知り得たのは、寺山修司がエロス(肉欲から通ずる愛。性愛)について述べた言説である。寺山と民族音楽の造詣が深い小泉文夫とが、“対談”という形式で、音楽に係るエロスについてのディスカッションを編纂した、ある書籍の企画があった。1983年刊のサントリー音楽叢書③『エロス in Music』(サントリー音楽財団・TBSブリタニカ)である。
はじめにざっくりと、この本のシリーズ――サントリー音楽叢書――について解説しておく。1982年1月に、最初のサントリー音楽叢書①『オペラ 新しい舞台空間の創造』が刊行された。この本の主なトピックスとしては、ドナルド・キーン、山田洋次、大木正興らによる鼎談「オペラへの招待」や、坂東玉三郎と畑中良輔による対談「オペラVS.歌舞伎」など。同年7月には、第2弾となるサントリー音楽叢書②『1919~1938 音楽沸騰』が出る。2つの世界大戦に挟まれた時代の現代音楽をテーマとし、武満徹、諸井誠、山口昌男らによる鼎談「もうひとつの音楽を求めて」、柴田南雄と高階秀爾の対談「現代への投影」といった内容が盛り込まれている。
ところで詳しい経緯は分からないが、いくら調べてみても、1983年刊のサントリー音楽叢書③以降のシリーズは、見当たらないのである。どうもこのシリーズは、わずか2年の間のたった3冊の出版で打ち切りとなったようだ。
この事情を当て推量するならば、3冊目の『エロス in Music』の内容が、当時にしてはあまりにも、強烈かつ斬新すぎたのではないか――。しかし、その内容が決して的外れなものではなく、かなりエロスの本質に踏み込んだ、音楽との係わり合いについて多様な論客を結集した内容であったことは、言うまでもない。ちなみにこの本の表紙の画は、池田満寿夫氏の作品である。本中にも池田満寿夫と佐藤陽子の二人が、「音楽・絵画・エロス」と題し、随筆を寄稿している。
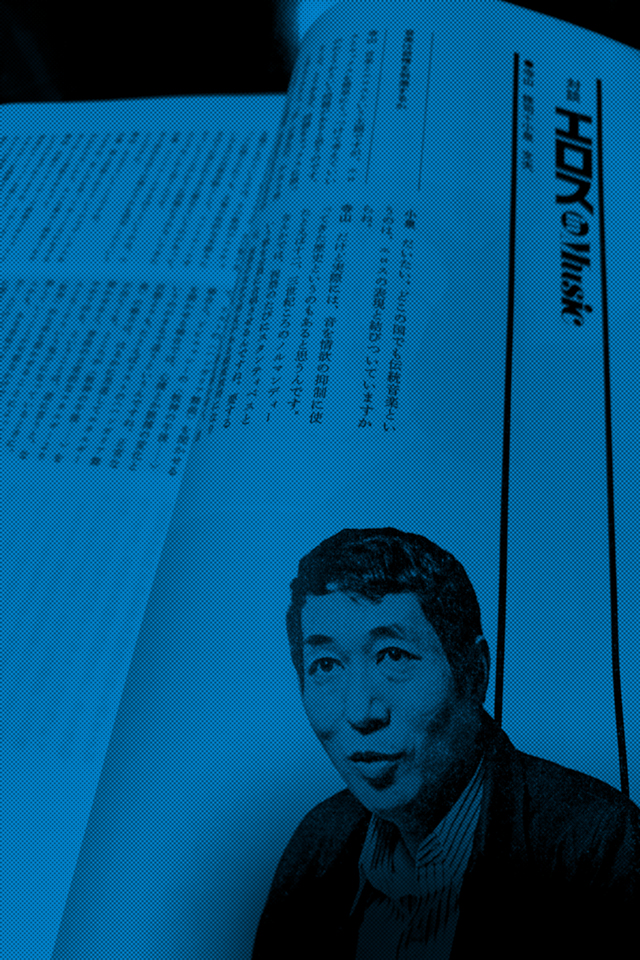 |
| 【本の巻頭を飾る対談「エロス in Music」の寺山修司】 |
寺山修司とは何者か
では、サントリー音楽叢書③『エロス in Music』における寺山修司と小泉文夫の対談――“音楽の中のエロス”――に話を絞ろう。まず本の中で、二人の略歴が記されてあったので、あらかじめそれをここに引用しておく。
《寺山修司(てらやましゅうじ)
昭和十年生まれ。詩人、劇作家、演出家、映画監督、シナリオライター。芸術選奨新人賞、芸術祭賞、ベオグラード国際演劇祭グランプリ受賞。著書に『寺山修司全歌集』『寺山修司戯曲集』『田園に死す』『月蝕機関説』『迷路と死海・わが演劇』などがある》
《小泉文夫(こいずみふみお)
昭和二年生まれ。東京芸術大学教授。サントリー学芸賞受賞。著書に『日本伝統音楽の研究』『世界の民族音楽探訪』『音楽の根源にあるもの』『エスキモーの歌』『民族音楽研究ノート』などがある》
(『エロス in Music』より引用)
この『エロス in Music』における寺山氏と小泉氏の対談は、そのディスカッションの音声を文字に起こし、多かれ少なかれ編纂されたものであるとしても、白熱した大人同士の討論の臨場感が、文字の隙間からひしひしと伝わってくる貴重な筆記録となっている。語弊を恐れずに言うと、二人とも全くふざけておらず、大真面目であった。むしろ寺山氏の方が、この機に是が非でも、音楽とエロスの係わりについて深く丹念に探っていきたいという好奇心があったからではなかったか。
この本が刊行されたのは――既に述べたが――1983年(昭和58年)の、こまかくは1月である。小泉氏との対談があったのは、それより前と考えられる。寺山氏が肝硬変による敗血症で亡くなったのは、昭和58年の5月4日である。享年47歳だった。つまり、小泉氏との対談で、彼の肉声から、己の実存主義の経験的萌芽とも言える自己完結論としての、“音楽の中のエロス”のテーマに、半ば置き換わって語られていた――と思えなくもないのである。
詩人であり劇作家である寺山修司が、生前どんなことを思索し、万物あるいは形而上の思想・哲学に関してどんな言説を放っていたかに、私自身はすこぶる関心があり、気の赴くまま、彼の著書や資料を漁っている最中である。そのうちのエロスへの思索に関しては、それこそ枚挙に暇がなく、様々な形で表出されており、彼の生涯における思考ベクトルの基礎的あるいは主眼的な役割を果たした命題であったかと思われるのだ。
しかし例えば、彼の代表作である著書『書を捨てよ、町へ出よう』(角川文庫)の「青年よ大尻を抱け」(当ブログ「寺山修司の『青年よ大尻を抱け』〈一〉」参照)においては、若者の男女の「性的魅力」について、読者の目線に合わせ、文体を緩やかにたわませながらコミカルに語り尽くし、《性の文化》がまだ未成熟であるとする若者へエールを送る――といった扇情的快活さがあったりする。
ただし、彼の詩的思考のカジュアルな文体は、そこはかとなく孤独性を感じるものだ。60年代から80年代前半における寺山氏の様々な活動におけるその実存主義的な、溢れんばかりの文化人類学的思考は、若者に限らずとも、道に迷い込んだ社会人全般に一石を投じる効果が、ある種の社会風刺としてあったように思われる。
然るに、晩年期に差し掛かった、“音楽の中のエロス”をテーマとした『エロス in Music』での小泉氏との語らいは、決してカジュアルなものにはならず硬派に徹底し、音楽の本質を洗いざらい流暢に探りつつも、性とはなにか、あるいは根源的な人間とセックスとの関係性において、実に素直に、また愚直に述べたものであり、彼の言説の資料としてはたいへん貴重なものの一つであるかと思う。
ここでは、その言説の全てを論じていくわけにはいかないが、とりわけ際立った箇所について言及してみたい。
 |
| 【ミュージカル『オー・カルカッタ!』の一幕】 |
音楽の中のエロス―その欲情と禁制
対談の内容は6つに分割され、以下のような小見出しが付けられていた。
①音楽は欲情を刺激するか
②巫女としての歌手
③日本の歌に、エロスはあるか
④肉体の解放・検閲・性の人工化
⑤機械楽器と“人間らしさ”の変貌
⑥挑発としての音楽
この対談の冒頭、すなわち①の「音楽は欲情を刺激するか」に係る問題点として、寺山氏は実に興味深い話をし始める。“音楽の中のエロス”のエロスについては、これをセックスと簡単に結びつけて考えてよいものかどうか…という着眼点である。
というのも彼は、根源的に音の発生が男女を結びつける、あるいは性と性を結びつける役割について考えていたのは進化論のダーウィンであったけれども、その逆に、音を「情欲の抑制」に用いた歴史もある――というのだ。
寺山氏は一つ例を挙げる。12、3世紀のノルマンディーでは、祝祭の度にスタンティペスという歌を全員に合唱させること。その歌は、祝祭の中で男女が放埒になってきた時に歌わせ、逆に情欲から禁欲へ向かわせる役割があったというのである。
小泉氏も、郷土芸能に位置する裸祭りを例に挙げ、若いエネルギーを発散させる役割に異議を唱えない。さらに寺山氏は、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」を例にとり、人間の心拍・脈拍の同調効果をエヴィデンスとした、情欲を沈静化させる音楽の規範類型がある旨を語り、単に“音楽の中のエロス”とは、音楽に係る性の情動のみを意味せず、逆の沈静化・抑制化の向きもあることを示唆し、この対談のテーマは意外なほど大きく裾野が広がっていく。
古代から中世~近代において、祭事の合唱(独唱)、賛美歌といったものの中に、エロス(性の規範的理念)の昇華が想像できるが、時代がくだって現代においては、“音楽の中のエロス”の意味合いは沈静化・抑制化のベクトルがほぼ皆無となり、情欲を掻き立てる言わば、集積回路的役割となっているたぐいの音楽が、ほとんどである。
二人は1960年代末に起こったアメリカのポルノ解禁にも触れ、とりわけ性表現の自由と解放が、エロティシズムを弱体化させ、“音楽の中のエロス”のあるべき情態に変化が見られていることに着目している(④「肉体の解放・検閲・性の人工化」)。
寺山氏は「人工的なもの」というのが、エロティシズムのある部分に大きな役割を果たしていると語る。北欧やアメリカの女性は化粧をしない、つまりエロティシズムは自然なものだとする観念があるが、エロティシズムはつくられたもの、すなわち「人工的なもの」をともなうと考えていいのではないかとする。小泉氏は、ここで歌舞伎の女形の化粧を例に挙げて補足するが、寺山氏は、巫女(神がかりの状態になって口寄せをする女性のこと。イタコ)としての流行歌手であるとか、ロリータ・コンプレックス文化などというものの“つくられた人間”として、それを了解共有し、「代理の性体験」を味わっているのではないかと述べる。
抑圧された女性の心象が音楽の中へ
さらに二人の話は発展し、深まる――。
日本では江戸時代、女の人は広い帯を締めるようになって胴体を締め付け、不自由になっていく。同時に不動産の所有権というのもなくなる。そうした頃に並行して、庶民の音楽では弦楽器が扱われるようになる。かつて能などではメロディーを笛(管楽器)で吹いて表現していたものが、音楽の流行としてそれが弦楽器に置き換わっていく。笛は男性の(象徴の)楽器であり、弦楽器は女性の(象徴の)楽器であるとし、江戸時代になると、三味線や琴が主流となっていったという。
ヨーロッパでも同じようなことが起こったと、小泉氏は付け加える。18世紀にコルセットが流行り、女性の胴体を人工的に締め付け、男性の審美眼に叶うべく美体を作り上げていった。法律の上でも、女性の地位が窮屈になっていく。ところが反面、音楽では、やはり弦楽器が台頭主流となって、男性の(象徴の)楽器である管楽器や打楽器がなりをひそめ、旋律を担っていた役割から引き下がって、それらが脇役となっていった。
つまり、そうした封建的な時代の男性優位社会においては、男性の欲望(=支配欲)が肥大化した社会的様相となっていて、女性の地位における規定や所有の権利は、著しく抑制・禁制もしくは制限され、性(=生殖)の対象としての女性の美化、すなわち「人工的なもの」の装飾化、偶像化が蔓延り、音楽表現においては、性の対象としての女性の存在が心象的に主題となって弦楽器が扱われ、男性の欲望(=支配欲)の観念の、中心的役割を果たしたのだろうとする。
 |
| 【寺山氏と対談した小泉文夫】 |
ミュージカル『ヘアー』とは何であったか
この対談の最後に語られていたのは、⑥の「挑発としての音楽」である。小泉氏は、ニューヨークのミュージカル『ヘアー』が与えた社会的影響の大きさに驚いたという。とくに大学の学生達に与えたショックは大きかったと語る。
寺山氏もこの話題に率先して加わる――。『ヘアー』のプレミア上演の演出で、開場前、劇場前にずらりと並んだ観客の周囲を、役者達がマリファナを吸いながらうろつくのだという。そして客達に金をくれとせびる。当然客達はいやな気持ちで追い払ったりするのだが、開場になって客達が劇場に入っていくと、その連中も紛れ込んで25セントくれよなどと言いながら入ってきてしまう。そしてそのまま舞台に上がり、彼らの芝居が始まる――という演出。
開演直後、コインちょうだい、25セントちょうだいと、ターザンのように縄にぶら下がって、客席側の観客に訴え続ける芝居(演出)がしだいに秩序化(=常態化)され、観客の意識が困惑を超越してそれに対し抵抗できなくなっていった時、彼らは全裸になるしか抗議の術がないところまで追い込まれ、ブロードウェイ・ミュージカル史上最も有名な曲の一つである「アクエリアス」(“Aquarius”)を盛大に合唱する。この時観客は泣くのだと――。アメリカの悲惨な現実を劇場の中で疑似体験し、小市民的感覚を根底から覆す衝撃的なミュージカルであったと寺山氏は述べる。
音楽は、そうした根源的な「意識を揺さぶる特性」の表出によって、社会を挑発し、社会を変え得る力を持っているのだとする、一つの考え方ができるだろう。寺山氏は、ここに大きな可能性の問題として提起している。むろんそのことが、彼自体の活動の主たる追求だったとも言える。
小泉氏は、そのことの分かりやすい凡例として、江戸時代中期の浄瑠璃の太夫・宮古路豊後掾(みやこじぶんごのじょう)の豊後節を取り上げている。まさにその時代、行き詰まってがんじがらめになった男女が心中をする歌、すなわち、心中すればいい――そういう心中を美化する歌を宮古路豊後掾が歌った時、世間では心中事件がたいへん流行ってしまったのだという。幕府は焦り、豊後掾を追放する。
語り物や浄瑠璃で社会が動かされてしまう例証だとし、その大きな力の可能性が音楽に、今でもあるはずだと小泉氏は言う。その力をどう解放していくか――。寺山氏はこれに応え、「それが我々の課題だ」と述べ、対談は終わる。
§
音楽にはエロスが内在している――と定義した時、そのエロスとは、性の欲望にとどまらず、人を突き動かすエネルギーとしてのエロスであることを、二人の知識人は示唆している。たいへん重要かつ重大なテーマである。
ある意味、その時代において寺山氏の存在自体が、こうしたテーマを容易く想起させることができた証左ではないかとすら思うのだが、21世紀の今日の、音楽を語る論旨の趣向においては、こうした本来的に多様な側面を持った音楽に対する論考が、かつての時代と比べても、あまりに平面的かつ視野の狭い限定的な論旨に偏っていないだろうかということを、私は懸念し危惧する。全く気の毒なほど、若者は多様な側面を持った音楽と接し切れていないのではないか。あらためて、寺山修司の思考性の包括力に私は舌を巻くのである。


コメント