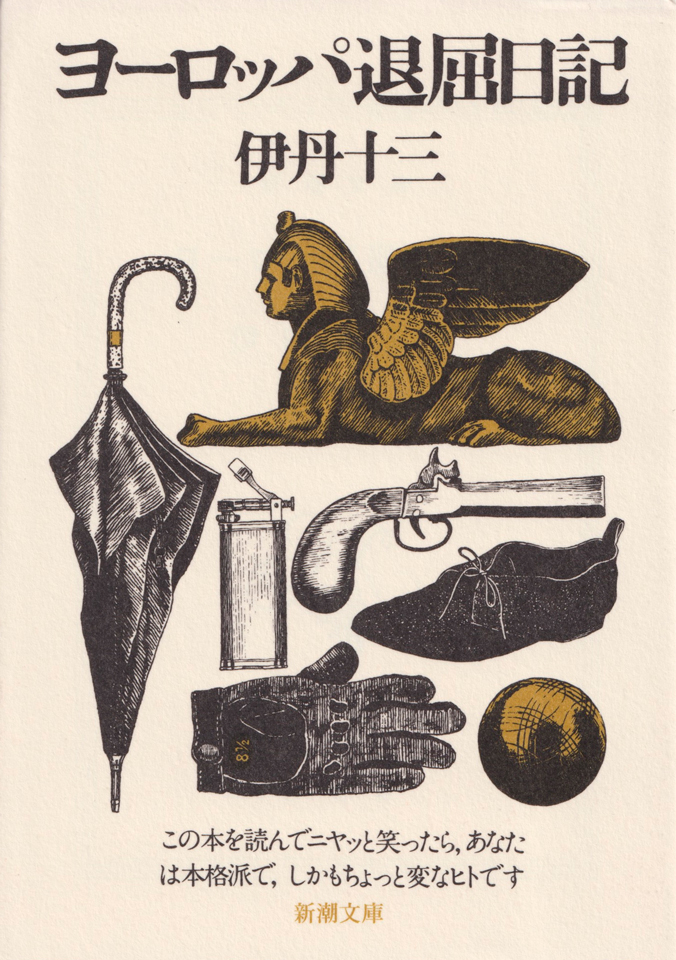 |
| 【伊丹十三著『ヨーロッパ退屈日記』新潮文庫版】 |
当ブログ2016年11月付の「『洋酒天国』と活動屋放談」で初めて、伊丹十三氏の『ヨーロッパ退屈日記』について触れている。といっても、ほとんど素通りであった。しかし、この本を革製のバッグに忍ばせておいて、ヨーロッパなどへ思索の旅をしてみたい――。そういう憧れを強く抱かせてくれる名著であるから、このままではいられない。
伊丹十三。個人的には、それまで何度となく彼の監督映画を観たつもりであったし、俳優としての出演作であった1983年の『家族ゲーム』(監督は森田芳光、主演は松田優作、宮川一朗太)における印象は、なかなか忘れ難く深く刻まれており、大雑把に解説すれば、中学生の主人公の父親役を演じて、情愛に欠けた潔癖性を見事に表現し、翌年の日本アカデミー賞の助演男優賞を受賞していたりする。個性派俳優としてのキャリアが円熟期を迎えた頃、伊丹氏は『お葬式』(1984年)で監督デビューし、芸能界におけるそのインパクトの余波は桁外れに大きかった。以後の連なる監督作品については、敢えて述べなくても、よく知られているとおりである。
しかしながら、ある年代の方々にとっては、伊丹氏と言えば、『ヨーロッパ退屈日記』なのだろう。俳優であり映画監督であり、その傍らに文学作品として佇立する名著『ヨーロッパ退屈日記』について、私の個人的な思い入れを込め、今後不定期でぽつりぽつりと触れていきたいと思っている。そういう決断を自らに課した。言わずもがな、これまでのあいだに、彼の文学作品に触れる機会がほとんどなかったからだ。
今回は――その第一の手始めとして――彼の軽妙なる来歴を含めたうえで、この名著のなんたるかについて、概略的に叙述していきたい。
本の略歴と伊丹十三氏のプロフィール
俳優としては個性派俳優、あるいは技巧派で知られる伊丹氏の、壮年期に差し掛かる直前にしたためた文筆モノの代表作が、『ヨーロッパ退屈日記』である。このタイトルを付けたのは、『洋酒天国』の編集にも携わってきた、直木賞作家でエッセイストの山口瞳だ。
伊丹氏と山口氏が初めて出会ったのは、お互いにかなり若い頃であった――というのは間違いのない事実である。山口氏は昭和29年に國學院大學を卒業し、河出書房の雑誌『知性』の編集部に属していた。伊丹氏とはそこで出会ったらしいのだが、伊丹氏は駆け出しの商業デザイナーだったのである。伊丹氏によると、この当時“商業デザイナー”などという言い方はまだなく、版下屋とか書き文字屋、図案家と呼ばれていたそうである。ところで、彼らの当時の年齢が、一見するとあやふやなのである。
山口氏がこの本(昭和40年刊のポケット文春版)の裏表紙に書いている内容によれば、初めて出会ったのは、伊丹氏が19歳の時であり、自分は26歳だったとしている。
しかし、伊丹氏が昭和50年刊のB6版のあとがきで述べるには、あの山口氏が述べた年齢はあくまで“脚色”であって、本当は自分が21歳の時、山口氏の方は29歳だった――という。さて、どちらの言い分が正しいのであろうか。調べてみれば簡単で、伊丹氏は昭和8年生まれ、山口氏は大正15年(昭和元年)生まれであるから、伊丹氏の言い分が正しい。
そうした若い頃に知り合ったのを基礎として、伊丹氏は『知性』廃刊後に俳優となり、結婚(昭和35年)もして、それから渡欧もして1年経過する。帰国後、文藝春秋からの依頼で、この著作の“原形なるもの”を書き、それが没となってしまう。だがその後、壽屋(現サントリー)の宣伝部にいた山口氏の計らいがあってか否か、“原形なるもの”に多少手が加えられた原稿が、『洋酒天国』の小冊子に採用され、掲載される。
その時の、「ヨーロッパ退屈日記」と付けられたエッセイが初めて世に出た功績というのは、あまりにも大きかったように思われる。壽屋のPR誌『洋酒天国』の第56号(昭和38年1月発行)に掲載された「ヨーロッパ退屈日記」の著者名は、“伊丹一三”である。現在読まれている『ヨーロッパ退屈日記』からすれば、この時の「ヨーロッパ退屈日記」はまだ“未熟”然としたものであり、具体的に言うと、第一部にある「エピック嫌い」までの15の掌編にすぎなかったのだ。
以後、同名の連載モノは別誌(『婦人画報』)で2年継続され、さらに別の雑誌で書いたものを足し合わせて、第四部にいたる“完熟”の中身で単行本にしたのが、昭和40年(1965年)3月に文藝春秋にて刊行されたポケット文春版である。
ちなみに、今ここに私が手控えているのは、新潮文庫版の『ヨーロッパ退屈日記』である。刊行した翌年には、最初の妻(川喜多和子さん)と離婚が成立し、その1年後、女優・宮本信子さんと出会い、芸名を“伊丹十三”と改める。昭和44年に宮本さんと結婚。以後のキャリアへの関心は、ここでは止めておいて割愛する。
いずれにせよ、個人的には、単行本となる前の“未熟”状態の同書を『洋酒天国』(第56号)で読むことができたのは幸いであったし、この名著を深く掘り下げてみようと思ったきっかけとなったことは、言うまでもない。
“完熟”の『ヨーロッパ退屈日記』を味わいたい
こうした経緯で5年前、「ヨーロッパ退屈日記」の中身(繰り返すようだが、“未熟”状態であった昭和38年のもの)を読んでおきながら、その面白い中身を黙殺――当ブログで紹介できぬままやり過ご――した理由についてはこうである。
つまり、この『ヨーロッパ退屈日記』を深く掘り下げるためには、まず準備段階として、次の4つについての造詣を深めておかなければならぬ――と直観したのだった。
第一は、「萬国輿地全圖」(ばんこくよちぜんず)について。第二は、和風スパゲッティとも称される“ナポリタン”のことについて。第三は、彼が出演した映画『北京の五十五日』(監督はニコラス・レイ)のことについて。第四は、同様にして彼の出演作である『ロード・ジム』(監督はリチャード・ブルックス)について――。これら4つをまず先に調べておかなければ、『ヨーロッパ退屈日記』を潔癖に語ることにはできない――と思ったわけである。そういう理由で、〈すこぶる面白いエッセイだ〉と思っていたにもかかわらず、ついに5年も放置してしまったということである。
参照のための『北京の五十五日』と『ロード・ジム』のディスクは、既に手元に用意している。したがってこれから、少しずつ、不定期という形で、この本を語っていくことにしたい。果たして、どれだけの人が関心を持っていただけるであろうか。不安ながら期待したいところではあるけれども、まずは、伊丹氏の簡潔なるプロフィールを、あらためて本のカバーから引用しておくことにする。
《1933(昭和8)年映画監督伊丹万作の長男として京都に生まれる。映画俳優、デザイナー、エッセイスト、後に映画監督。TV番組、TVCMの名作にも数多く関わり、精神分析がテーマの雑誌「モノンクル」の編集長も務めた。翻訳者としての仕事もあり、料理の腕も一級だった。映画「お葬式」発表以降は映画監督が本業に。数々のヒット作を送り出した後、’97(平成9)12月没。エッセイスト伊丹十三の魅力を一冊にまとめた『伊丹十三の本』(新潮社)がある》
(新潮文庫『ヨーロッパ退屈日記』の表紙カバー裏より引用)

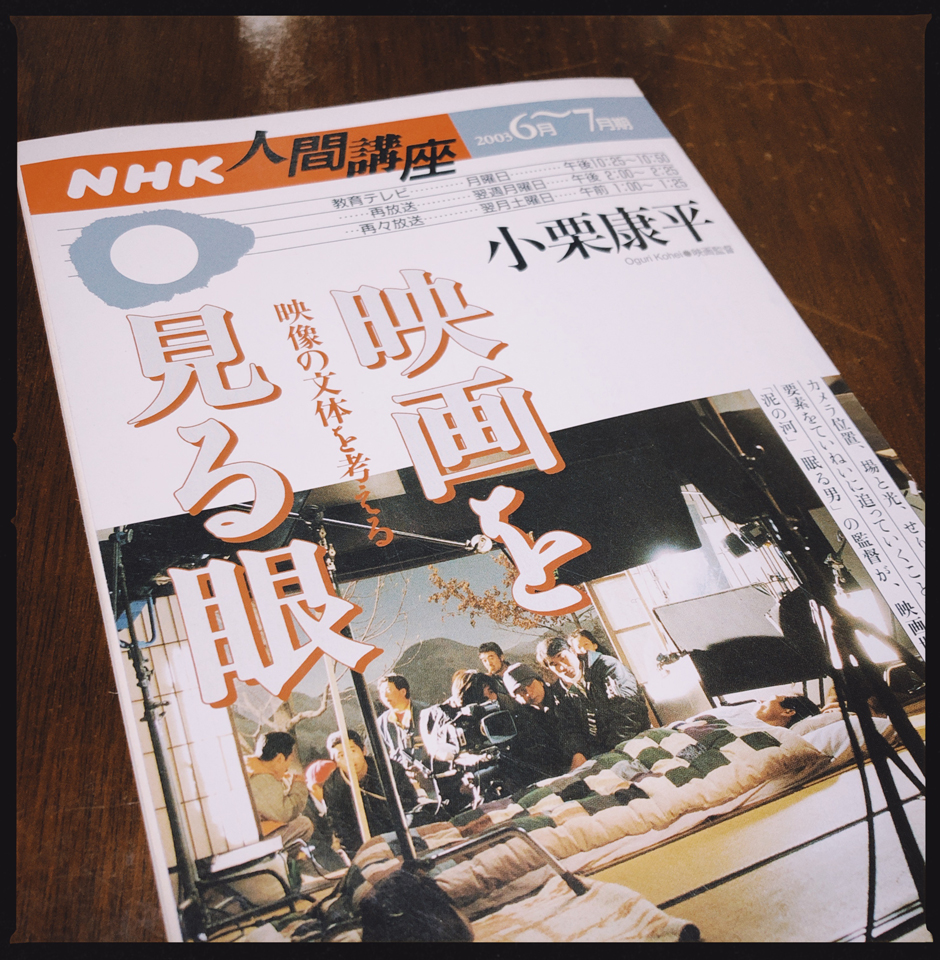
コメント