自己主張をするにしても、音楽や映像、文筆などの創作活動を続けていくにしても、自身のインプット&アウトプットをめぐるモノとコトの「ガラパゴス化」は、避けられない自明となってきた。そういったことの決意表明をここでしたい。
「ガラパゴス化」の考察は、《容易ならざる時代》を生き抜くための私なりの知恵、処世術である。「こうあらねば」を捨てる。こうした考察には、メリットとデメリットがあるにせよ、悪い面ばかりに囚われることなく、それを善きコトとして断捨離の精神を貫いていきたい。“ガラパゴス”の定義として、以下、2つの文章を引用しておく。
《Galápagos Is. 正称はコロン諸島Archipelago de Colon。東太平洋の赤道直下、エクァドル海岸より西方1,000キロメートルにある同国属領の火山島群で、大小13島と多数の岩礁とから成る。総面積7,844平方キロメートル、人口2,412(1962年推定)。主都はサン・クリストバルで、同名の島にある。1535年スペイン人トマス・デ・ベルランガTomás de Berlangaが発見した当時は無人島でゾウガメが多くすんでいたので、来島者の間にカメのスペイン語ガラパゴスで知られるようになった。(中略)発見以来スペイン植民地として少数の移住者があり、19世紀前半はアメリカ捕鯨船の寄港地としてさかえた。(後略)》
(平凡社『世界大百科事典』1965年初版より引用)
《日本や特定の地域の中では広く用いられているものの、世界的には汎用性が低い製品やシステム。世界標準の進出を阻むが、一たび流入すると淘汰されやすい。エクアドルの西側に位置するガラパゴス諸島の、他と隔絶された環境において、独特な生態系が発達していることにたとえて言ったもの》
(三省堂『新明解国語辞典』第八版より引用)
昨今では、“ガラケー”(=ガラパゴス・ケータイ)という愛称で知られるように、汎用性の乏しい旧型のケータイは、存在が忘れられるどころかむしろ際立って、少数派の特異な生態系ともなっている。もともとエクアドルの「ガラパゴス諸島」という、その隔絶された既存の島の印象からくる新語の定着は、以上のような説明で十分かと思われる。
隔絶された環境であるとはいえ、その内周で《独特の生態系が発達している》というのが肝である。私の創作活動の中で、インプット&アウトプットにおけるモノとコトが、独自の生態系で機能している、あるいは培養されている、発酵しているというふうでなければならない。かつて私は、東京・台東区上野にあった千代田工科芸術専門学校(千代田学園)に通っていた一人の学生であった。もう昔の話である。しかし、その学校で培ったノウハウや経験を、生涯活かしていこうと思っている。継ぎ足し継ぎ足しの「焼き鳥のたれ」のように、深みの真髄を究めたい。
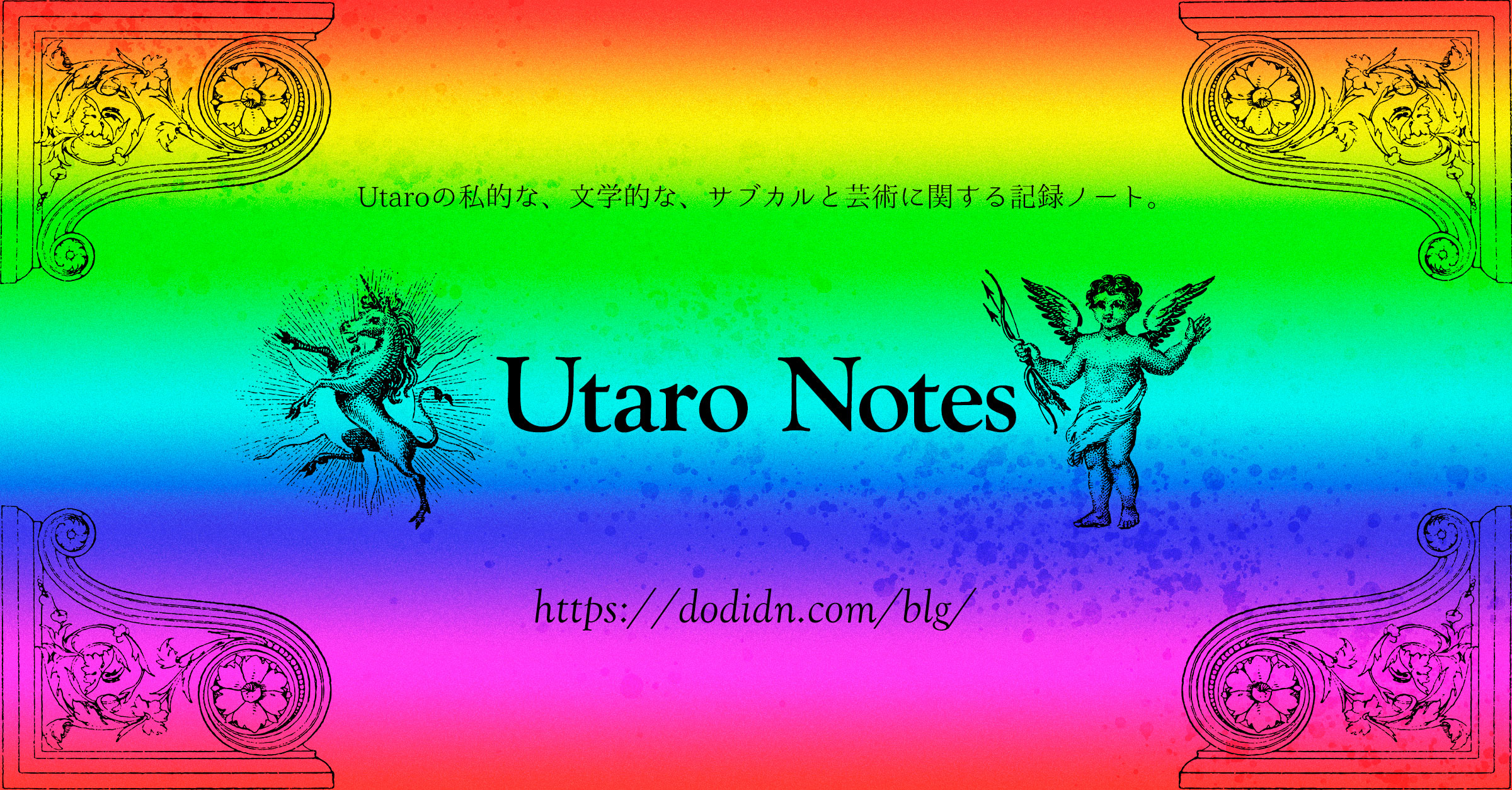


コメント