先月、幼少期から小中学校にかけて幼馴染みだったある友人のお母さんが、少し前に亡くなった――と聞いた。友人もそのお母さんも、私にとっては少年時代の記憶が生々しく残る、気さくな印象が強かっただけに、〈そうか、我々はもう、そういう宿命的なとしつきを迎えるようになってしまったのだ〉と頭を垂れた瞬間、空を切り裂くような切ない悲しみを覚えた。
子よりも先に親が死んでいくというのは、人のさだめに違いない。いや、全ての生きものにおいて、逃れられない宿命である。ただやはり、人が死んで「自然に還る」ということは、互いに生存していた時の関係には二度と戻れないのだから、とてつもなく寂しい心の痛みを伴う。
実体として「もう会えない」という正直な気持ちと、いや、いつでも「心の中で会える」という観念の永遠性をなんとか享受したうえで、歯を食いしばって寂しさに堪えようとするせめぎ合いで、人は切実に、己のちっぽけな人生というものの試練を悟る。
それはいわば、孤独で辛いものの情念であったりするから、「誰かに寄り添って生きていたい」と思うのが、人間の性(さが)というものではないだろうか。
人間の性(さが)や人間の幸福について、深く考えさせられる映画がある。人は何を拠り所にして、生きていけるのだろうかという問いかけをもたらす映画――。
1977年日本公開、佐藤純彌監督の『人間の証明』がそれである。洋題は、“Proof of the Man”。原作は、森村誠一の同名小説(角川文庫)。

ホームランとピンク・レディーとキングコング
若い世代の方からすれば、77年というと、たいへん古い映画、ということになってしまう。日本式の年号で表すと、「昭和52年」である。昭和52年――私はまだ5歳であった。
5歳にして興味津々だったのは、“テレビ”(テレヴィジョン)と呼ばれる大きい箱型の装置で、当時はいわゆる木目造りの“家具調テレビ”(家においてあったのはパナカラー)だったのだ。
昭和52年、箱型のテレビのブラウン管から映し出される、視覚的な記憶として濃いのは、9月3日、読売ジャイアンツ(巨人軍)の王貞治さんの雄姿である。王さんが756本のホームラン世界記録を更新し、ニュースその他諸々の情報となって駆け巡った。
またその頃、歌手のピンク・レディーが人気を博し、「渚のシンドバッド」が大ヒットして、あちらこちらの番組で歌いまくっていたという印象もある。私はおそらく、テレビに映るピンク・レディーの二人の歌を聴きながら、「渚のシンドバッド」を口ずさんではしゃいで踊っていたに違いないのだ。
“映画”――というジャンルに対する好奇心は、前年、角川映画の第一作である『犬神家の一族』(監督は市川崑)を、家族全員で映画館に行って観たので、既に芽生えていた。暗闇の中で放たれる、七色の光線による芸術は、幼くして私を虜にした。
さらに映画についていうと、同じ前年(76年)12月から公開された、ジョン・ギラーミン監督の映画『キングコング』(主演はジェフ・ブリッジス、チャールズ・グローディン、ジェシカ・ラング)は、私に映画的サブカルチャーの醍醐味を知らしめたきっかけの作品といっていい。
『キングコング』は、1933年の同名映画のリメイク作品であり、スクリーンの中で女優ジェシカ・ラングがコングを可憐にあやし、彼女の切なく甘く野性的な表情が、私の脳裏に刻み込まれた。
その頃やけに、家族で映画を観る機会が多かった――。
『キングコング』を観た帰り、立ち寄ったイトーヨーカドーで、1冊の本を親に買ってもらった。
それは、『キングコング』の製作・撮影に関するメイキング本であった。当時4歳だった私が、映画館を出た後、その余韻にひたり、作品の関連本を思わず買ってしまうといった、一端の映画ファン的な行動をこのとき初めて経験したことになる。自称“映画狂”における諸現象が、この時より表れたのだ。
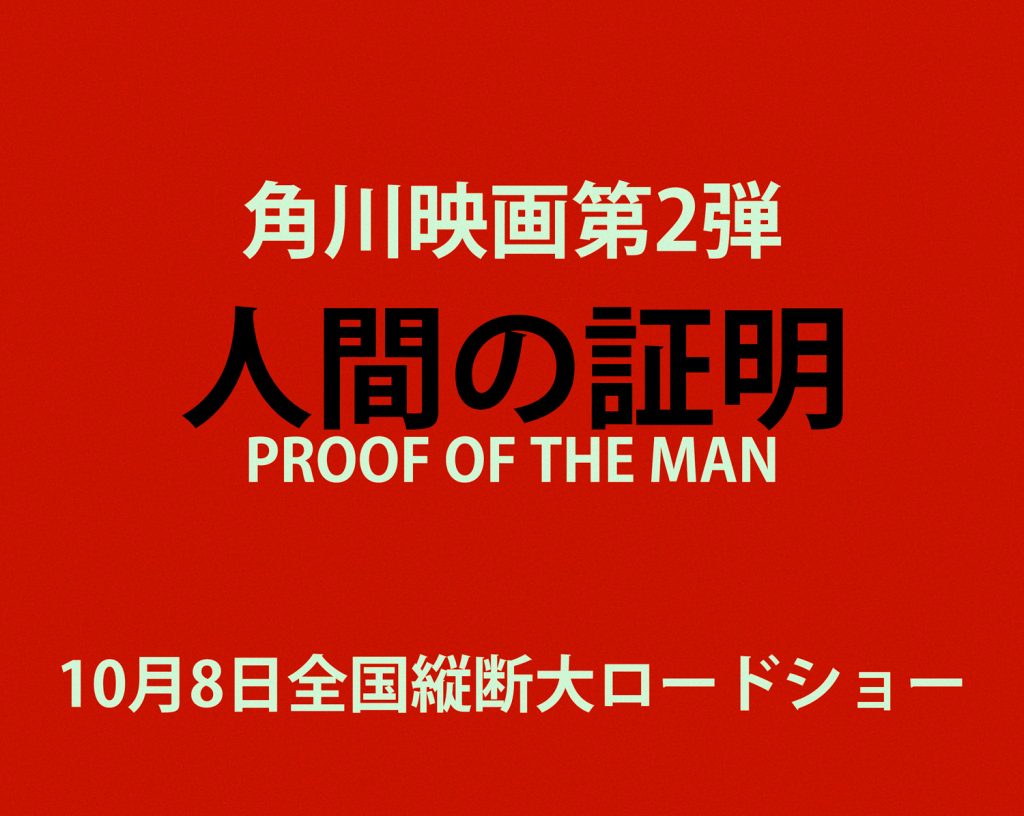
『人間の証明』という映画
さて、77年10月公開の期日に向かっていく、幼少期の私の『人間の証明』に対する関心度は――むろん映画狂として――徐々に高まっていったということについて、書かねばなるまい。
この点においてもはや、幼少期であったという注釈は、取り払うべきかもしれない。その頃執拗にテレビで流れていた、『人間の証明』の宣伝用コマーシャル・フィルム(CF)に対し、私はかなり高い純度で、その執着心を培養していったように思われる。
『人間の証明』のCFは、その独特の暗部のディテールが凝っていて、真に迫るものがあった。
谷底に落ちていく麦わら帽子の映像に、松田優作さんの声で西條八十の詩の「帽子」(※もと『少年詩集』の「ぼくの帽子」の改題)が読み上げられる。公開前の数十日の間、テレビで流れていたその30秒のスポットに、釘付けとなったのである。
《母さん 僕のあの帽子 どうしたでしょうね。ええ、夏、碓氷から霧積へゆくみちで、谷底へ落としたあの麦稈帽子ですよ》(※映画版に準じ、現代仮名遣いに置き換えた)
《角川映画第2弾》
《人間の証明》
《10月8日全国縦断大ロードショー》
《読んでから見るか、見てから読むか》
ブラウン管にそのCFが映るたび、私は現実を離れ、ある種の空間にさまよった。谷底に落ちていく麦わら帽子の映像と、タイトルの“人間の証明”の太い文字がどきつく心を揺さぶる。まさに衝撃である。いったいこの映画は、どんな映画なのだろうと――。
“ニンゲン”の“ショウメイ”とは。
ショウメイ=証明は、正しいことを表すアカシ=証のことだ。ならばこの映画は、人間が人間であることのアカシをテーマにしているというのか。人間が人間であること。幼少期の私には、到底理解できない難しいテーマであり、ただそれを繰り返しつぶやき、懊悩する以外になかった。
映像から想起される様々な空想は、生々しい現実感の恐怖となってじわじわと溢れかえり、私はこの映画を見ることは許されないのではないかとさえ思った。次第に思考回路がぼんやりとしてきて、いみじくもあの空中で回転して谷底に落ちていく麦わら帽子に、得体のしれない死への予兆を覚えたのだった。
ニンゲンノショウメイ――。まだ観ぬ映画への恐るべき憬れは、その後の少年時代にどのような影響を及ぼしたというのだろう。それについては未だ言葉にすらできない〈想い〉というものがある。

キスミーの黒人青年
主演は松田優作、岡田茉莉子、ジョー山中、ジョージ・ケネディ、鶴田浩二、三船敏郎。
映画の冒頭は、ニューヨークのビル群の空撮映像。その次に、汚れた身なりの者が、もうひとりの者の差し出す書面にサインをするショット。顔は見えない。書面に記された氏名は、“Johnny Hayward”(ジョニー・ヘイワード)。
ジョニー(ジョー山中)が100ドル紙幣の束を受け取る。
彼は、イースト・ハーレムのスラムに住む黒人青年で、日本行きの飛行機のチケットを買い、嬉しさを隠しきれない。そして、にこやかな笑顔を振りまきながら、スーツをオーダーする。
そのままそれを着込んで店から出ると、彼はどうだといわんばかりに、それまで着ていた無用になった衣服をダストボックスに投げ捨て、街を歩き去っていく。
それからタクシーに乗り、ハーレムのアパートに帰ってきたジョニー。
軽く荷物をまとめ、ボロボロの階段を降りていく。そこへ現れたのは、太った中年の黒人女性マリオ(テレサ・メリット)。彼女はアパートの管理人だ。彼女がジョニーに声をかける。「ヘイ、ジョニー、どこへ行くんだい?」
彼は瞬時にこう答える。「キスミー」
「いまなんていった?」
「キスミー、ママ、ハレルヤ!」
ジョニーがその場でジャンプする。
その瞬間――ストップモーションとなり、スクリーン上のジョニーの立ち位置が大きく右にずれ、右端にシフトしたとき、太い文字で、“人間の証明”のタイトルが現れる。そして瞬く間に大野雄二作曲のテーマ曲――フュージョン系にリアレンジされたアップテンポの「Proof of the Man」――が流れ始め、クレジットが続く。
ニューヨークの雑駁とした喧噪の風景。実に軽やかな明るいオープニングである。あの30秒スポットCFのような、謎めいた暗さは微塵も感じられない。ニューヨークには多様な人種が住み、それぞれの人々が幸福と自由を求め、活発にうごめいている。
これらが、若いジョニーの躍動感に溢れたハイセンスなオープニング・シークェンスであり、新進気鋭の角川映画らしい映像美となっている。
ファッションショーと殺人事件
次なるシークェンスは、ファッションショーである。
数人の黒人女性のモデルたちが、彩られたシンメトリーや直線の反復による抽象的なデザインの衣装を纏い、華やかにステージでパフォーマンスを繰り広げている。都会的なファッションショーであるが、このシークェンスはやや(たぶん意図的に)冗長気味になっている。
魅了されるショーの衣装をデザインしたのは、服飾デザイナーの八杉恭子(岡田茉莉子)。締めのステージで黒ラメのドレス姿の八杉が現れ、会場は拍手喝采となる。
歳を重ねて落ち着いた表情の八杉は、艶やかで美しく、カリスマ性が感じられる。
しかし――事件の黒い影が忍び寄ってくる。
42階スカイ・ラウンジ直行のエレベーター。なんとそこに立っている青年はジョニーであり、彼の胸にナイフが刺さっている。古びた「西條八十詩集」の本が彼の体から落ち、「ストウハ…」といって倒れ込んでしまった。ジョニーはエレベーターの中で死んだ。
それは、ショーが終わった後の夜である。麹町署から警視庁の刑事らが駆けつけ、捜査が開始された。
ガイシャの身元はパスポートから、1950年生まれのニューヨーク在住のジョニー・ヘイワードとわかる。つまり、あのニューヨークで札束を受け取り、日本行でアパートを引き払った黒人青年である。
警察犬による捜査で、ホテル付近の公園が、ジョニーが刺された第一の現場だと概ね断定。遺留品捜査が始まる。
古びた麦わら帽子が発見される。若手刑事の棟居(松田優作)は、ジョニーが最後に言い遺した言葉=“ストウハ”は、“ストロウ・ハット”、つまりこの麦わら帽子のことではないかと推理。しかもそこから見上げたホテルのライトアップが、まるで麦わら帽子の形に見えるではないか。
なぜジョニーは、公園で刺され、それにもかかわらず、八杉のファッションショーが催されているホテルのスカイ・ラウンジへと向かい、「ストウハ…」と言い遺したのだろうか。
ストーリーの核心
殺人現場で捜査が開始された直後、激しく雨が降り出した。
この雨の中、別の場所で、もう一つの不運な事件が起こる。皮肉にもその事件は、折り重なるように一つに結びつき、やがてある者を消し去っていくのだが…。
麹町署の刑事らを演じているのは、松田優作の他、個性派揃いの俳優たちである。鶴田浩二、ハナ肇、鈴木瑞穂、地井武男、和田浩治、峰岸徹。
棟居刑事を演じる松田と、横渡刑事を演じるハナ肇のコンビは、捜査班の軸足的存在となっており、それぞれ“ヨコさん”“ムネさん”と呼び合って、信頼関係を深めているようだ。
日本からの依頼で、ニューヨークの市警第27分署の刑事ケン・シュフタンを演じているのは、映画『エアポート’75』に出演したジョージ・ケネディ。彼がジョニーの身元調査のために、億劫な心持ちでスラム街を度々行き来するシーンは、この映画の確たるハイライトとなっている。しかも日本映画において、これまでにない画期的なシークェンスなのだ。
これについて、映画評論家の河野基比古氏が、映画パンフの解説の中でこう述べている。
「人間の証明」のニューヨーク・ロケは、まったく新しい日本映画の境地を切り開いたといえる。ここに登場するニューヨークは、それ自体が重要な登場人物のように息をしている。生きているニューヨークを捕えることは、アメリカ映画でさえ難しいことなのだ。
『人間の証明』劇場版パンフ/河野基比古「交錯する二つの灼熱点」より引用
ニューヨークが生きているからこそ、東京も生きていなければならない。この映画が製作技術的に、アメリカのスタッフを初めて起用したとか、ニューヨーク市に製作費を投入したとかいうことも、もちろん重大だが、それよりも、ニューヨークと東京が、まったく等価値に、その生態そのままにスクリーンに映しだされた初めての映画という意味で画期的なのである。それは、いままでアメリカ映画が東京なり、日本を描いた場合のお粗末さを考えれば、充分、納得がいくはずだ。
河野氏が述べるように、ニューヨークと東京という二つの都市が、同じ映画に登場するそれぞれのシーンとして、まさしくどちらも“生きて息をしている”等価値でなければならないとするならば、回想シーン――ほぼこれが筋の主題――で表出する過去の事実、すなわち日米戦争の戦後下の、ある女と少年――八杉恭子と棟居刑事――のむごたらしい出会いの「暗い影」を描くべく、アメリカ相手に無謀な戦争をおっ始めた帝国日本軍の残虐性と、戦後の進駐軍の、アメリカ兵が日本人にひどく残酷的な暴力を振るったことを「等価値で描く」ということになり、一言でいえば戦争の悲惨な一面としてとらえられるわけだが、場合によっては、ニューヨーク市の撮影許可並びにアメリカ人俳優の起用は実現しなかったのではないかという危惧が想像できるのだ。
結果的にニューヨークの撮影は許可が取れ、そこにジョージ・ケネディらが登場するという前代未聞の構成は実現し、フィルムに収まった。
これぞ角川映画という新しい思潮の作品が、この後続々と枚挙に暇がなく公開されていくのだけれど、そういう意味でもたらした『人間の証明』のエポックメイキングは、まずそれのみで能弁に語ることができるし、「70年代」という稀有な時代が生み出したこの作品は、日米の奇跡的な接合点であったかもしれないのである。
黒人青年ジョニー・ヘイワードがニューヨークを旅立ち、遠い異国の地日本を訪れ、自分の本当の母と再会を果たさんとした(あるいは果たした)矢先の悲劇は、悲劇であるという以外何ものでもない。
ジョニーは殺され、そこに一人の女・八杉恭子がいた――というだけの話である。
ジョニーは尊い命を失い、恭子も命の果てに転落した。二人のいる空間に、その空に、あの懐かしい麦わら帽子が舞うのである。ジョニーは終戦後の日本の地で生まれた、不幸な混血児であった。

失われた麦わら帽子
ジョニーが大切に持っていた、麦わら帽子と西條八十の詩集。そのうちの詩が、先述した《母さん 僕のあの帽子 どうしたでしょうね…》である。
ジョニーのあふれかえる記憶には、幼い頃、霧積で、麦わら帽子をかぶって遊んだことと、若い母と父の面影があった。むろんこれは、八杉恭子にとって最も思い出したくない、消し去りたい記憶であったが。
ジョニーは懐かしい母の記憶を頼りに、本当の母と再会するため、日本にやってきた。
父ウィルシャー・ヘイワードの想いは息子に託されたのだった。ウィルシャーは、息子にどんな想いを託したのだろうか。自らの命を危険に晒し、大金を金持ちの男から引き出させ、息子はその金で旅立った。
この息子と本当の母親を会わせる拠り所の想いとは、いったいなんだったのか。息子ジョニーとウィルシャーの思惑には、幾分かあるいは相当、乖離があったかと思うのだが、ほとんどこれについては謎である。
あのとき、麦わら帽子が旅先の霧積の草原で宙を舞った――という詩的かつ空想的な記憶が成立するのであれば、恭子にとって、その悲劇の切っ先ともいえるナイフは、息子ジョニーの胸を貫くであろうことを、既にその時、予期していたはずである。
いずれ、彼は私に会いに来るであろうと。会いに来れば私は破滅なのだと。しかしそれが、私にとって唯一の幸福であろうと――。
人間の一生、人間の幸福
人間の一生というものの本質を、とどのつまり子どもが成長し、おとなになる中で幸福を築こうとする、その堅い決意と信念によってのみ希求される涙ぐましい努力である――と規定するならば、私が幼少期に『人間の証明』を鑑賞し、直観的に人の一生の酷さを悟ったことは、悲劇的遭遇といわざるを得ないことだろうか。いや、私は決してそう思わない。
映画館の後方の天井付近から、光が差し、その光が拡張しつつ真っ白なスクリーンに「像」を映し出していることの実に不思議な発見を、私は不幸の因果だと思っていないし、映画が人を不幸にする装置だとも思わない。ただし、暗がりの映画館を後にし、一歩、街の片隅の現実世界に戻っていく時、映画とは、何たる人を惑わす芸術なのだろうと好意的に感嘆するのである。
私の中で、あの空に放たれた麦わら帽子の連続した「像」が消えることは、ない。人間の一生とは、その何かを失う悲しみの妄念の集積に違いないのである。
ピアノ・ソロの前奏から、ジョー山中が“Mama, do you remember…”と歌い始める「Proof of the Man」 (作詞:西条八十、角川春樹、ジョー山中/作曲:大野雄二)は、あまりにも多く耳にしてきた名曲である。
「予告編」の啓示からも察せられる、“失われた麦わら帽子を探すこと”――。
これはゲームではない。底深く物悲しい、人の一生の代償なのだ。5歳の私は「予告編」で打ちのめされ、幼い子どもとしての心に、もう一つの心を生んだように思う。ゆえに、命は大事にしなければならないと。



コメント