
先日、青沼ペトロのウェブ小説サイト[架空の演劇の物語]を脱稿した。あの小説は、90年代の若者たちの、可憐なる演劇熱について書いたつもりである。“架空の”――とあるように、大方フィクションに違いないが、ところどころ微細な事柄で、私自身の体験的な側面を書き入れたことは否定しない。
自分が初めて小説を書くとするならば、どんな題材が適当かと考えたとき、演劇しかないと思った。この判断は決して間違っていなかった。
仮に一人の若者の登場をそこに設定したとする。すると、たちまちその人物が若者らしく思念を掻き立て、演劇にかかわるありとあらゆる事物と結合して、どんどん情景が膨らんでいき、作者である私の、文字を打つスピードが疾走するかのように加速する…。しかし、字数が増えれば増えるほど、危うさも増す。あまりにも空想癖が常軌を逸し、事柄が発展しすぎて収拾がつかなくなってくる。私にとって演劇を題材にすることは、危険な火遊びでもあったのだ。
失われていく演劇への興味
書き進めていた昨年の夏過ぎ、この小説の全体構造がようやく明らかになった時点で、たちまち筆を下ろしたくなった。それは当初から予期していたことなのだが、私がこの小説を脱稿すれば、演劇に対しての全ての興味を失うのではないかという懸念であった。それが、中途の段階で感じられたのである。
既に創作ノートには、それ以降のこまかな筋書きと、大凡の本文の草稿を書き記してあったので、そこからの加筆修正や推敲はさほど難儀な作業ではなかった。しかし、登場人物たちが諸々の事態を収拾して、ある年代から社会人演劇の領域を飛び越え、そこから一気に商業的発展を遂げるかのような「革新的な筋」は避けたいと思っていた。したがって、いかに主人公が平時の、平凡な生活に戻って鎮座していくかのコンテクストにもっていけるかが肝要となり、そこにだけ苦心を払ったつもりである。演劇人は常に、一介の市井の、蒼氓(そうぼう)――Artisanに過ぎないことに、おおむね敬意を表し、その矜持を自覚すべきだろうと思うのだ。
この小説を書き終えて、恥ずかしながら私自身が演劇にかかわった経験の瑣事について、どうしても触れておかねばならぬと思った。そうしなければ、小説を書いた理由が判然としないからである。
自己演劇略史
私自身の若き演劇経験の活動期は、1991年から96年のわずか5年間である。
ただし、この時の同胞たちとの腐れ縁で、遍歴が幾分か漸進し、2012年から2019年において再接触、すなわち「演劇への回帰」という趣旨での少なからずの関わり合いを持ち、ショートフィルムの製作にも携わった。この数十年間は、総体的にいえば、演劇に対する気鋭は衰えていなかったのだと思う。
これはほんの少し、小説の中味を明らかにしてしまうことになるのだけれど、小説では「2010年」と「2015年」が時代点の肯綮(こうけい)となっている。
実際に私も、2010年に東京・池袋の思い出深い劇場を再訪し、2015年には、その後近しくしていただいた慶應義塾大学藤沢キャンパス(SFC)の演劇サークルのメンバーとの邂逅があり、彼らの著しい活躍を垣間見るため、王子小劇場などに幾度か訪れた思い出もある。
こうした自己の、取るに足らない演劇略史においては、少々発展を遂げた面もある。が、“架空の”小説においては、こうした経験譚は採らず、全くちがう経緯をたどることとなっている。
とはいえ、私個人の91年から96年の活動期は、きわめて演劇熱の消耗度合いの激しい、ややもすれば脂汗をひたすら掻き続けるような体験に始終した。
元々、高校時代に都内の某劇団の公演鑑賞に執着しつつ、まるで絵に描いたような演劇少年らしく、新宿の紀伊國屋書店の“演劇関連書籍コーナー”に時々立ち寄り、未来社のてすぴす双書などの本をあちらこちら手に取って、それらをむさぼり読んだのを都合のよい経験とし、のちの千代田学園時代では、久貴千彩子先生の教授で脚本論も習った。
こうしたことを演劇熱の「たたき台」としたかったものの、実際の小劇団活動では、その手のテクストや脚本論に関心を向ける者はほとんどいなかった。次第に我らの演劇の化けの皮が剥がれ、客観的にみれば演劇畑の習性とは程遠い、ただただお客から笑いをとりたいためだけの、粗雑な「お笑い芸人集団」に陥っていたという愕然たる始末であり、根本的な演劇論に介在する表現集団を目指していた結成当初の志(こころざし)は、半ばにして頓挫し、私個人の欲求でもあった(ある意味での)「正統な演劇」への探究心は暗闇に閉ざされ、自己の無力さを悔やんでの呵責に打ちひしがれる時期もあった。
ときに今でも、地元では、私がかつて定着していた同集団が、存続していたりする。が、それは元々の創成メンバーとはほとんど無縁の人たちによるものであり、理念や志を異にする集団である。私との関係は一切ない。彼らに市井の演劇への未来像を託すことは暴論であり、後世に残されるものは何一つ無い。わが町の若者たちの演劇熱といったものは衰退どころか、見る影もないのである。
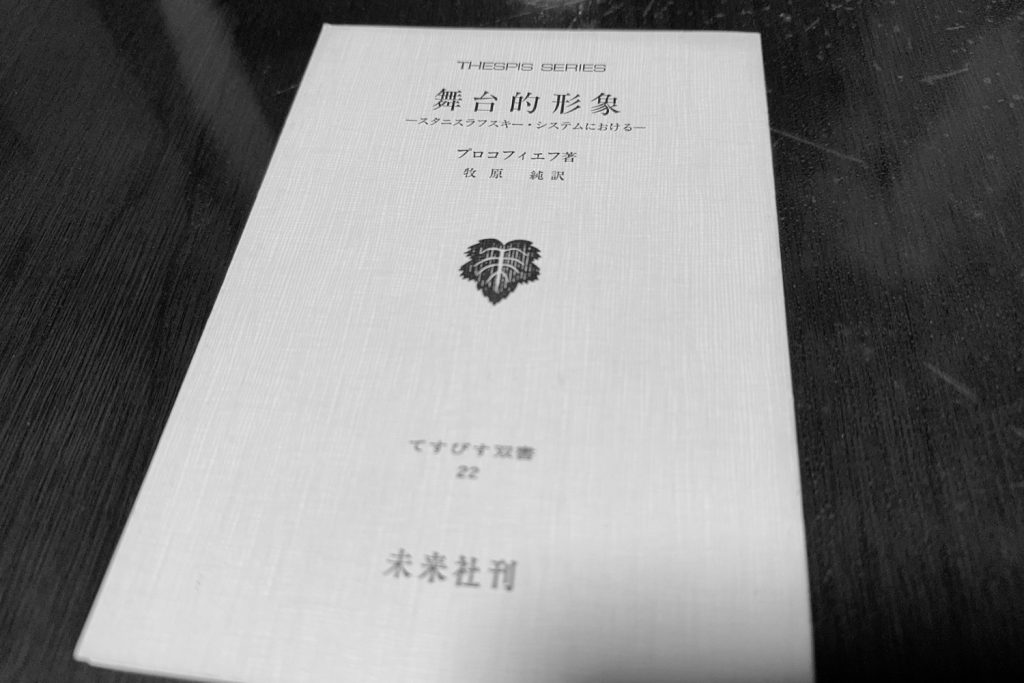
面影を残すスタニスラフスキー
こうしたことについて、甚だ、馬鹿馬鹿しい話に終始してしまって、我ながら呆気にとられている。
先程まで手元に、懐かしいてすぴすの本の、プロコフィエフ著『舞台的形象―スタニスラフスキー・システムにおける―』(牧原純訳)があった。演劇に関する大概の資料は、小説を書き終えてほとんど断捨離してしまった。しかし、かろうじてこれだけが残されていたので、今のうちに、そこから一つ摘み取って記録しておこうと思う。
私の好きな名文である。
《もしチェーホフの戯曲に「月がのぼる」と書いてあつたら、この月の出は観客のためではなく登場人物のためでなくてはならない。彼らは月について一言も言わないかもしれない。しかし月の出は彼らに今までなかつた何か新しい自覚をもたらす》
私のあの活動期において、そんなチェーホフを語り合うことも、「月がのぼる」ト書きすらも無い、悄然とする日々を送っていたのだった。若き日にチェーホフはやりたかったし、それは遠い演劇の憧れであった。
ある俳優の「傍ら」が、役者ではなくただの「棒杭」であることもあるだろうと述べ、スタニスラフスキーはこんなことも述べている。
《もし君の論理が強力であるなら、これは君を立ちんぼにさせはしない。たとえば、戯曲の行動の論理によつて、君は、もし彼が君を見つめたら君は自分の感情をかくさなければならないということを知つている。つまり、この場合は、魔術的な「かりにもし」と論理を応用したまえ》
私もその魔術的な「かりにもし」のちからで、ほんの少し熱を帯びた、若者たちが登場する“架空の”小説を、書いてみたまでのことである。
§
[架空の演劇の物語]を書き終えて、私は、演劇と乖離する旨を想っている。
それは決意というものではなく、ごく自然な心の移ろいとしての、泡沫のたち消えのようなものだ。演劇に対する熱情は、とうに尽きてしまっているのだった。
尤も、かつての経験から、今日においてのこうした文芸的創作活動や、映像に関する制作において、演劇の基礎たるものが、諸般の「行動規範」となり得ることはじゅうじゅう承知している。だから、乖離するとはいっても、身についたものは決して消えるものではない。
そうしたこととは別にして、私自身が演劇に対する新しい企てや掘削をおこなうことは、思念上、もはや「無い」ということをここでいいたい。
かつて近しかった同胞の一人が、懸命に今、後輩を指導しつつ、自らの朗読活動を通じて、演劇に邁進していることを、私は知っている。その同胞に対してだけは、率直に、誠実な人である旨を讃えたい。
例えば、数十年も前に、芥川龍之介の「運」を共同で手がけたことがあったが、なんと今の、彼の修練的朗読作品群の中に、それがひと粒加えられていることは、感慨深いものがあった。それはつまり、見事に彼が正真正銘の演劇人であることを物語っているのだ。あの時の志を体現した、たった一つの残り火であろう。
[架空の演劇の物語]を書き終えて、一つは、自身の過去の清算を果たし――すなわち演劇と乖離し、過去の略史を全て消し去り――演劇を語る側の執着としても尽きた(※ただし、私の好きな寺山修司に関してはまだ何も語っていない気がするから、これは別個である)ことを示唆する。
もう一つは、小説というジャンルに、「新たな希望」を個人的に持ち得られるかどうか、しばし思い描いてみたい。その示唆である。
“架空の”――は、あまりにも危険な火遊びであった。さらば演劇。されど、ここに今、私の「新しい時代」が到来した予感は、あるといえばある。恐縮ながら、その話はいささか急すぎるので、又の機会にしたい。

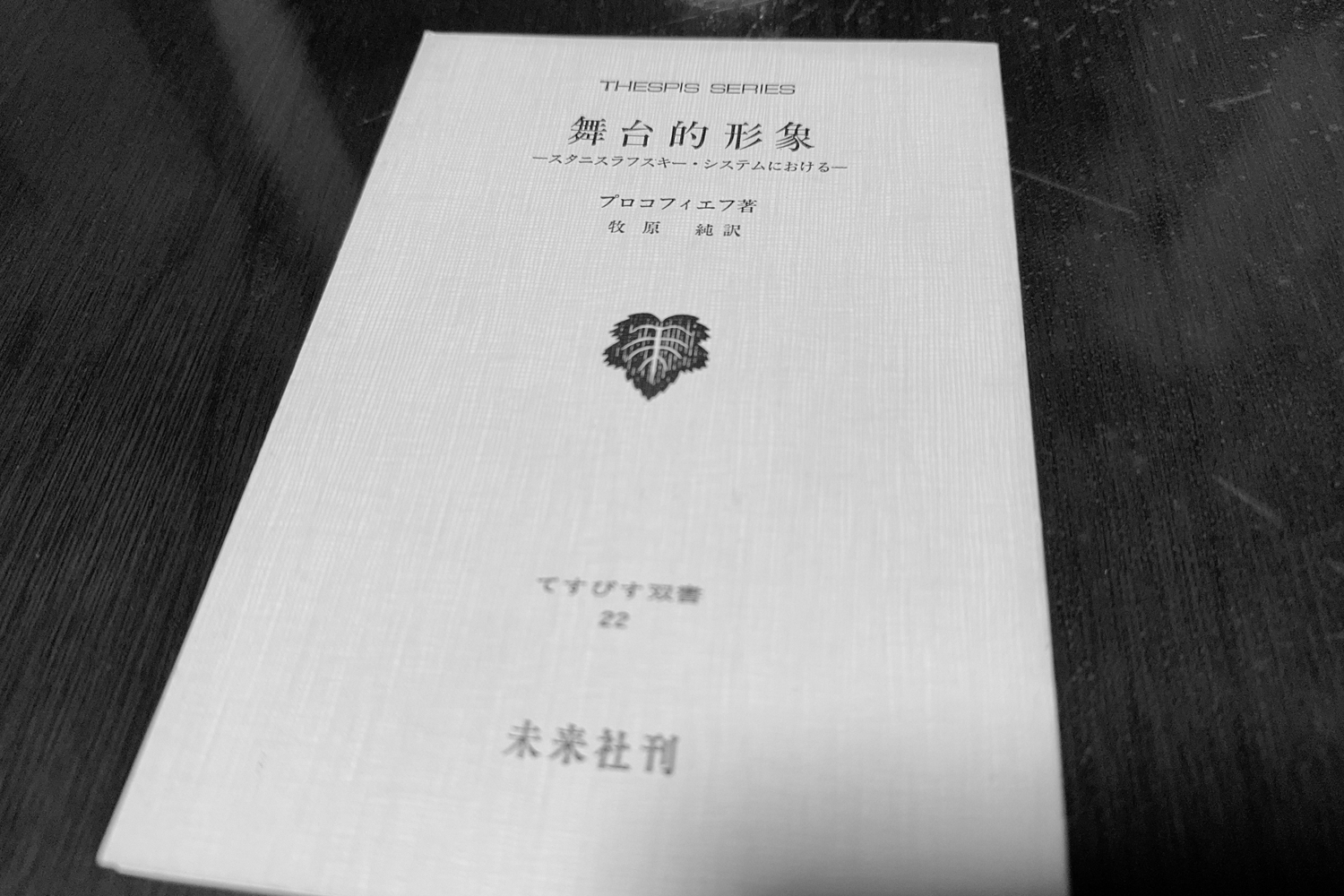


コメント