
他稿で、マレーネ・ディートリヒ(Marlene Dietrich)の歴史的な“下着姿”についてふれた。1930年公開の主演映画『嘆きの天使』(“Der blaue Engel”/ドイツ)においてである。
まず、この映画を観た当時の観客は、二重の衝撃があったのではないか。ディートリヒという新鮮なる女優の、これまで見たこともない美貌と気品溢れる圧倒的な存在感。そしてその彼女が、あまりにもセクシーで、容易ならざるエロティックな“下着姿”であったこと――。
私も、その衝撃を受けた観客のうちの一人に含ませていただきたい。彼女の限りない魅力に、心が打ちのめされたといっていい。
女たらしの一兵卒と歌手アミーの恋物語『モロッコ』
映画『嘆きの天使』は、トーキーの創成期において、ディートリヒのどことなくニヒルな顔立ちと、痩身ですっくと立った肢体から醸し出す「エロティシズムの魔性」を世に知らしめた、空前絶後の画期的な作品だった。この映画でディートリヒは、女優としての存在感が認められ、すぐさまアメリカのハリウッドからお呼びがかかる。『モロッコ』(“Morocco”/1930年)である。
主演はマレーネ・ディートリヒ、ゲイリー・クーパー(Gary Cooper)、アドルフ・マンジュー(Adolphe Menjou)。監督は『嘆きの天使』と同じジョセフ・フォン・スタンバーグ(Josef von Sternberg)。
モロッコに駐屯するフランス外国人部隊の一兵卒トム・ブラウン(ゲイリー・クーパー)は色男で女たらし。キャバレーで女性を連れて飲んでいると、目の前のステージにとてつもなく美しい女性が現れたのだ。“男装の麗人”を演じる歌手アミー・ジョリー(マレーネ・ディートリヒ)。トムはすっかりアミーに一目惚れしてしまい、連れの女性は逆上する。
アミーに一目惚れした男はもう一人いた。富豪の紳士ベシエール。彼は自信たっぷりにアミーに求婚し、トムはそのことを知って、アミーへの恋心を自ら退かせたりもする。だが、そんなどうしようもない一兵卒トムのもとに、行く末の覚悟を決めて追いかけていったのは、アミーの方だった。
部隊の行進がモロッコの地を去ろうとした時、アミーはベシエールに別れを告げた。そして消えかけていたトムの遠影を追い求め、靴を脱いで裸足となって、風と砂にあらがう荒涼の砂漠の中に突き進んでいくのだった――。
日本の映画館のスクリーンに、初めてディートリヒが登場したのは、実は『モロッコ』が先だった。アメリカでの公開より遅れて翌年の31年(昭和6年)2月11日に封切。『嘆きの天使』はその後に公開されたが、どうやら日本では、『モロッコ』のインパクトのほうが遥かに大きかったようである。この映画は数年間に及び、東京などで繰り返し上映されたという。
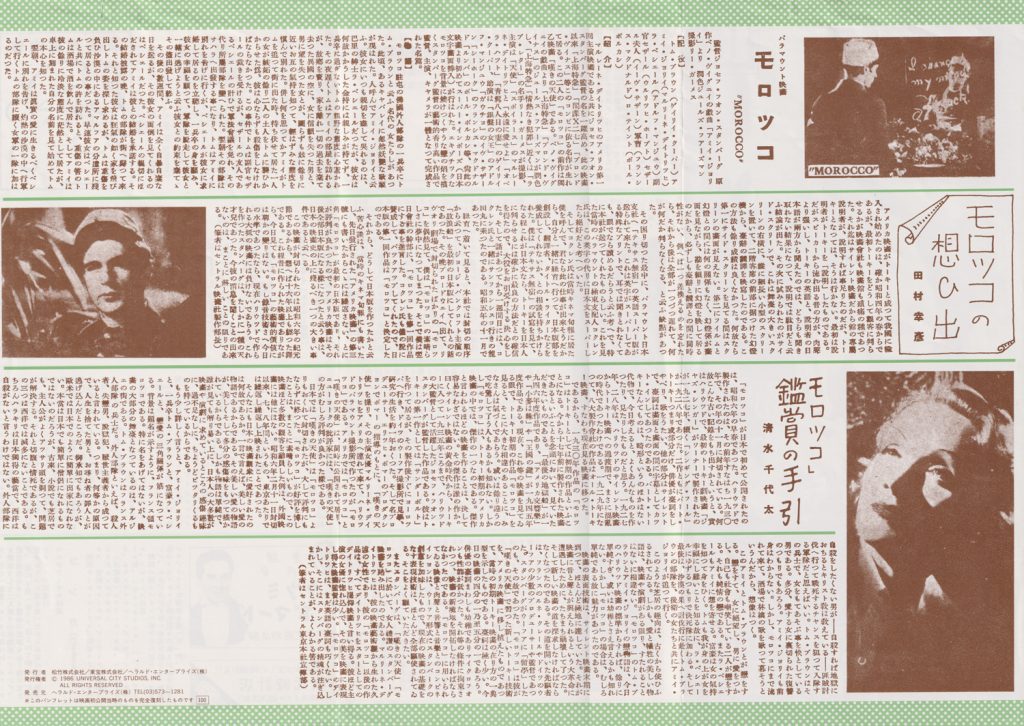
日本における字幕スーパーの始まり
『モロッコ』は、日本で最初の“字幕付きトーキー映画”であった。
実をいうと私は、子どもの頃、市川崑監督の映画『悪魔の手毬唄』(1977年)を観て、初めて“すーぱーいんぽーず”という言葉を聴いた。
すーぱーいんぽーず?
なんのこっちゃ、それ?
その言葉を聴いて、変な想像が頭をかすめたのだけれど、ともかくそれは、柔らかい口調の岸惠子さんのセリフの中に出てくる言葉だった。『モロッコ』で初めて「スーパーインポーズ」(superimpose)が採用され、あの頃そうした字幕付きの映画がどんどん増えたために、弁士たちが已むなく職を失っていった――というくだりである。実際に、そうであったらしい。
その『モロッコ』の字幕スーパーに関して、詳しい資料を入手した。
かつて福岡にあったスクリン・セントラル社が昭和20年末もしくは21年頃に発行した「スクリン・セントラル」(No.16/発行人は豊津修)の復刻版(発行は1986年/ヘラルド・エンタープライズ)。そのパンフレットには、「モロツコの想ひ出」という見出しで、セントラル映画社の製作部長であった田村幸彦氏の記で、当時の状況が綴られている。なんとこの人は、その字幕スーパーの最初の製作責任者なのだ。
以下は、「モロツコの想ひ出」の文章を要約したものである。
――アメリカのトーキー映画が日本に輸入され始めたのは、昭和4年の春頃。この英語のトーキーを、観客にどうわからせるか、映画会社も映画館も頭痛の種であった。
最初は、説明者(※弁士?)がトーキーを「説明」した。
しかしこれでは、スピーカーから出る音声のほうが大きいし、英語のトーキーと説明者の日本語が両方耳に入ってくるので観客は聞き取りづらい。そんなわけで、「説明」では駄目だということになった。
次に試みられたのは、メインのスクリーンの右横に、サイド・スクリーンを設置した方法である。
これは縦に細長い小型スクリーンで、2階客席の前部から幻燈機を使ってセリフの日本語訳を投影したもの。 しかしこれも、あまり芳しくなかった。
観客は、サイド・スクリーンの方も目で追う。するとその間、メインのスクリーンを見ることができないのだ。さらにこれは、映画自体のフィルムとサイド・スクリーンの投影とが機械的に連動しているわけではないので、幻燈の係がメインのスクリーンを見ながら、勘を頼りにサイド・スクリーンのそれを差し替えなければならないのだ。すると、俳優のセリフと幻燈の翻訳には同時性が乏しく、時間差が生じてしまう。一つ差し替え忘れると、次々に遅れて、何がなんだかわからなくなる、ということがあった。
はて、どうすればいいのか困っている中、パラマウントの日本支社に、『テキサス無宿』の英語スーパー版が送られてきた。
これは、英字でスーパーがプリントされたもので、これなら耳で聞き取れなくても眼で読めるだろうと、本社が送ってくれたようである。パラマウントの極東支配人のコクレン氏がこれを見て、この英字を、日本文にしてみてスーパーしたらよかろうと考えついたのだ。
コクレン氏はキネマ旬報にいた私を呼び、君ならこの仕事ができそうだから一緒にニューヨークに行って、日本版の部署を創設し、翻訳者やタイトル・ライターを養成してくれないだろうか、との相談を持ちかけられた。その話があって1週間後、コクレン氏と一緒に、サンフランシスコ行きの龍田丸に乗船した。昭和5年の11月のことである。
その後ニューヨークに着くと、ジョージ・バンクロフト主演の『放浪船』を最初の日本版にしてくれとの話があった。
ところがその晩ブロードウェイで、リヴオリ劇場(※Rivoli Theatreのことか?)で封切られたばかりの『モロッコ』を偶然見、この映画の素晴らしさに夢中になった。そこで翌日、会社の幹部に、『モロッコ』を最初の日本版にしたいということを持ちかけた。コクレン氏もそれに賛成してくれて、ついに日本版の最初の作品は、『モロッコ』と決定した――。
田村氏はこの時の字幕スーパーの具体的な製作方法や苦心談について、当時の『キネマ旬報』に記したらしい。私はまだ、その“キネ旬”を発見入手できていないので、さらなる詳細は今のところ不明なのだが、この『モロッコ』を機に、それ以降のアメリカ映画が全部日本版字幕スーパーになったということに関して、彼は《日本の映画史の上に残るべき一つの大きい事件である》と述べている。たしかに、この業績の影響はたいへん大きかったと思われる。

ディートリヒ渇仰の映画
そうした意味で、アメリカの映画『モロッコ』が、当時の日本で弁士たちを追いやってしまった影響には、多分の悲哀が伴う。それまでのサイレント映画の「完全なる見せ物小屋的娯楽」であった映画産業が、パンドラの箱をこじ開けてトーキーとなり、一種のリアリズムに近づいて、娯楽の本質を変えてしまったからだ。ある意見においては、真の映画はサイレント映画までだ――と豪語して定義付けするのも無理はない。アメリカからやって来た映画『モロッコ』には、職を失った弁士たちの、恨みつらみの怨念がこもっているともいえる。
それはそれとして――。
なんといってもこの映画においては、ディートリヒの魅力を忘れるわけにはいかない。彼女の姿がスクリーンに映し出され、それをまんじりと見た観客の、途方もない衝撃。私はその時の日本人の衝撃を、想像しないわけにはいかないのだ。ディートリヒ扮する歌手アミー・ジョリーの、可憐で命がけの恋沙汰が、当時の日本人の男女の心情にどのような影響を及ぼしたのか、私はそこに大いなる好奇心を抱いてしまうのであった。
最後に、スタンバーグ監督とディートリヒについて、前述のパンフレット「スクリン・セントラル」から、セントラル東京本社宣伝部・清水千代太氏の解説「『モロッコ』鑑賞の手引」を一部以下に引用して、この稿を了したい。
スタンバーグは、「嘆きの天使」「モロツコ」に於いて、女人礼讃のスタンバーグ映画を踏み出したのである。マルリーネ・デイトリツヒは、彼の映画芸術観から生れた久遠の女性であり、彼の「モロツコ」以後の作品は、すべてデイトリツヒをスターとしてのデイトリツヒ渇仰映画と言い得る。彼ほど主演の女優に惚れ込んで、その美を映画に表現し得た映画監督は少い。「モロツコ」のデイトリツヒは、まだ英語の台詞も巧くない。しかし、そこにはスタンバーグの精魂が注ぎ込まれていることが、よくわかる筈である。
「スクリン・セントラル」No.16(復刻版)清水千代太「『モロッコ』鑑賞の手引」より引用



コメント