 |
| 【中学国語教科書(光村図書)】 |
私はいったいいつ、大人になったのだろうか。少年としての子供が、大人として振る舞う少年となり、そして大人としての大人に成長していく過程のそれぞれの兆しは、いったいいつ、どのようにして顕れたのであろうか。
そんなことを思うのは、大人としての大人になりきれない、少年としての大人のわだかまりが、私の身体に未だ燻っているからである。成長とは、育って成熟すること。しかしその成熟という意味が、様々な文学を通じて、別の意味にあるのではないかということが、ようやく分かってきた。私は、己における大人への成長の道程を、たどたどしくも文学の側面から掴み取ってみたいと思ったのだ。
私にとっての成長期、すなわちその中学校時代は、大人として振る舞わなければならない(大人になることを過度に要求された)自己意識の緊張感を、最も強いられていた過酷な3年間であった。それはほとんど明るみを帯びない暗闇の内の瑣末と言っていい、まったく何事にも羽ばたく勇気を持てなかった徒労と怠惰の時代であり、唯一、私が夢中になり得たのは、演劇と音楽に対してだけであった。
このことには多少の誇張がある。だが、小学校を卒業する頃には既に、“少年として”の子供として月並みな、惜別や失恋、裏切りや拒絶といった対人関係における幾十の痛苦を身体に染みこませていた私は、中学校という新たな環境への免疫力が著しく減退していた。ここではもっと、その痛苦を味わわなければならないのかという重い恐怖があった。勉強する意欲を半ば失い、ただただ好きな演劇と音楽に夢中になるのが関の山で、学校の中の様々な活動を億劫に思っていたのは事実であるし、いちいち怠惰な態度をとり、能動的な学校生活というものを“ありふれたかたち”としても、送ることができなかったのである。
そうした徒労の3年間を、私は今、とても後悔している。親身にそれを支えてくれたであろう文学が、そこに有っただろうに――。
§
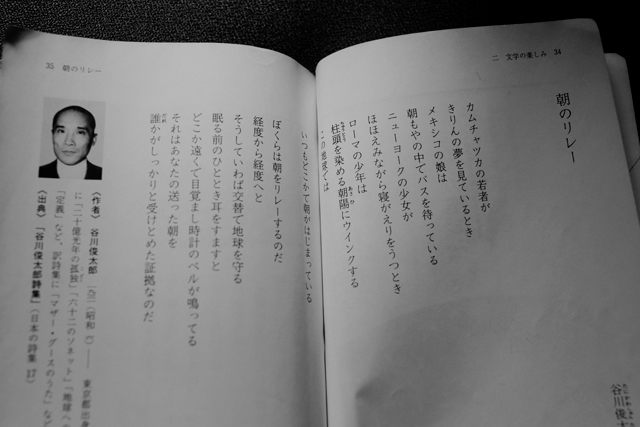 |
| 【谷川俊太郎「朝のリレー」】 |
ここにある中学国語教科書が、当時私の母校で使っていた教科書ではなく、あくまでその状況に近い象徴的な教科書として意味があるとするならば、これを読むことで、当時私が何を読み落としてしまっていたかを探ることができるだろうと思った。
これは元々、A子が中学1年で使っていた光村図書の国語教科書である(A子については、昨年「A子と教科書と魯迅」で書いた。A子は私より7歳年下である。これは平成4年2月発行の教科書であって、A子は私と同じ地元の学校を卒業したから、私もおそらくこれとほぼ同じ内容の国語教科書を使っていた可能性はないことはない)。
面白いことに、中学1年の国語教科書というのは、小学の国語教科書の名残があるのだ。どういうことかというと、教科書の第1章では、まだ教科書体(小学校の教科書で扱われている子供向けの書体)のままで文章が記されている。第1章は、児童文学作家・杉みき子著の「あの坂をのぼれば」で始まるのだが、その書体は小学校で扱っていた懐かしい教科書体であり、中学の学習内容へ推移するにあたり、教科書としての難易な度合いを緩やかにしながら推し進めようという試みなのだろう。
第2章になるとこれが、教科書体と明朝体を合わせたような、中庸の書体に置き換わる。この中庸の書体が、この中学1年の教科書の基本書体になっている。
ちなみに、第2章は谷川俊太郎の「朝のリレー」という詩で始まる。この第2章から置き換わった中庸の書体は、例えば、筑摩書房の高校用の国語教科書の書体とくらべると、明らかに見た目が柔らかく、子供っぽい。字体そのものが大きく読み易い長所はあるが、先の厳然たる教科書体の名残を多分に引きずり、書体のみならず挿絵や図表などの表現の軟らかさを総合すると、中学1年の国語教科書というのは、感覚的に言わば、“少年として”の子供に与えられた、児童文学の体質なのであった。
内容はやや文面的に大人びてはいるものの、それでも動物や植物などの自然や科学をテーマにした読み物が多く、第3章にあるアンリ・ファーブルの「フシダカバチの秘密」などを見ると、そうだ、確かにこうしたファーブルの読み物を読んだ憶えがある、と、思い出すのである。このファーブルが、とてつもなく少年の面影の匂いをリアルに思い起こしてくれる。中学1年という“少年として”の子供における、その視線の対象は、まだまだこうした自然の虫たちや動物といった外野の世界に関心が高かったのかも知れない。
そうして、外野から内省へ――。
この教科書の終わりの方、ヘルマン・ヘッセが登場する。ヘッセの短篇「少年の日の思い出」。ここで一気に、大人へのきざはしを予感させる。ヘッセの「少年の日の思い出」は、これも一つの児童文学の呈なのだろうが、少し暗く息苦しさを感じる作品だ。この紛れもない暗く息苦しいということが、純文学特有の気怠い潮を思わせ、子供にとって新たな対象の発見となり、それは「自己省察」を意味した大人への感覚の入口である。この話は次回に続く。

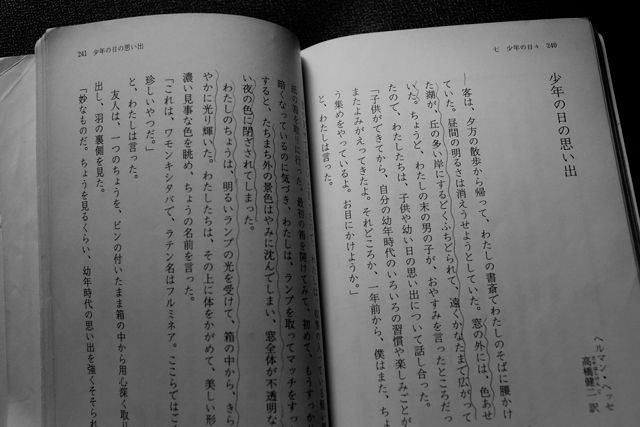
コメント