 |
| 【グレース・バンブリーによる歌劇「カルメン」】 |
私のカルメン狂、カルメン愛――。
先日、東京・上野駅の不忍口を出てすぐのスペイン料理店Vinuls(アトレ上野1階)を訪れようとしたところ、あいにく手持ちの“時間”の余裕がなく、入ることができずに午後の空腹を満たせず去ったのは、まことに嘆かわしい悲劇だと自ら思った。ああ、カルメン!闘牛場前のドン・ホセの最後の場面を思い浮かべる。次回は必ずあそこで食事を…と心に誓う。血の通ったスペイン料理を堪能したい。そうして一瞬、上野の空がブルーではなく真っ赤な薔薇色に染まって見えたのは、気のせいであろうか。
シャルル・デュトワ指揮NHK交響楽団の歌劇「カルメン」(昨年12月本公演のテレビ放送)を鑑賞したのは、ついこの前のこと。何故私が似合わずも情熱の男・カルメン狂となったのか、ここまでの経緯については、当ブログ「歌劇『カルメン』とその女」及び「N響の歌劇『カルメン』」を読んでいただければ幸いである。
それはそうと、ソーシャル・ネットワーキング・サービスとは、実にセンシティヴなものだとつくづく思った。実は先週、そのN響カルメンでドン・ホセ役だったマルセロ・プエンテさんご本人に、拙著のブログ記事を紹介したら、畏れ多い鄭重なメッセージをいただいた。あなたのブログを英語に翻訳して読んだとのこと。本当に有り難い。これ以上の至福はないだろう。こうした嬉しいことがたびたび起こるから、書く方もいっさい気が抜けないのだ。
§
幼少期に親しく接した百科事典の中のクラシック音楽解説本と付録レコード(『原色学習図解百科』第9巻[楽しい音楽と鑑賞]とレコード集「名曲鑑賞レコード」EP盤全6枚、全30曲)によって、ビゼーの歌劇「カルメン」は私の記憶にしかと、とどまっていた。解説本の中のあの写真――第1幕の縄で縛られた悲愴なカルメン――がとても印象強く、いかなる理由においても歌劇「カルメン」と言えば、この女性しかいない、とさえ思っていたその神秘なる謎の女性。彼女がアメリカ出身のメゾ・ソプラノ歌手、グレース・バンブリーであると知ったのはごく最近のことで、しかも私はあの写真の印象から、きっと“しゃがれた”太い声の女性であろうと信じて疑わなかった。
しかし冷静に考えれば、メゾ・ソプラノ歌手がそんな“しゃがれた”声であるわけがない。まだこの時は、グレース・バンブリーの艶のある研ぎ澄まされたブレスを聴いていないのだから無理はない。少なくとも幼少期、あるいはもっと先の少年期において、この記憶にとどめられた悲愴なるカルメンを、まさか“動く映像”として将来見ることになろうとは、一分たりとも思ったことはなかったのである。
そうしてようやく、グレース・バンブリーによる歌劇「カルメン」(1967年、カラヤン指揮ウィーン・フィル、映画編集版)のDVDを入手した私は、じっくりとその160分間を鑑賞した――。
昔、私の専門学校時代の講師をしていただいた、オーディオ評論家・斎藤宏嗣先生の著書の優秀録音盤音楽CDに関する本では、1982年グラモフォンでカラヤン指揮ベルリン・フィルの歌劇「カルメン」(主演はアグネス・バルツァ、ホセ・カレーラス)のCDを、優れた録音盤の一つとして挙げていた。確かに、今以てそのカラヤン指揮ベルリン・フィルのカルメンは、一般的に高評価を得ていると思われる。翻ってこのグレース・バンブリーによるカルメンは、少なくとも国内においてどのように評価されているのか、私はまったく窺い知ることができなかった。したがって、以下の私のこのバンブリー=カルメン評は、極私的な、個人的な思い入れの深いものとして受け取っていただきたい。
私は、ジャズのドラマーで言えばアート・ブレイキーやエルヴィン・ジョーンズが好きで、ああいった骨太でメリハリのきいた叩き方をして生み出されるリズムが、すこぶる心地良いと感じる。そしてこれを一概に“男性的”と評するのにはやや抵抗を感じていて、それを述べるなら尚、彼らの打ち方には、そこはかとない可憐で“女性的”なタッチの繊細さも兼ね備えているわけであり、音の表現性云々を男性か女性かで区別することは今の時代、もはやそぐわなくなってきていると感じている。
アート・ブレイキーやエルヴィン・ジョーンズに対する評価は、そうした意味で今一度再評価すべきだ、と私は認識しているのだけれど、彼らの表現性とヘルベルト・フォン・カラヤンという人の采配するフィルの音も、どこかそれに似ていて高水準なハイブリッドである。メリハリがあり、抑揚の繊細さが実に美しくエロティックだ。
グレース・バンブリーの話に引き戻す。DVDでは、まず前奏曲におけるカラヤンの表情が大写しになって、時折長回しになるのだが、第1幕でカルメンが登場するまでが、実に長いと感じる。それは良い意味でのwaitingである。やがて赤い服を着たカルメンが奥から登場し、一瞬にしてその歌声と美貌に魅了される。この一瞬はまことに言わば、黄泉の国に一歩踏み入れた畏怖の感であった。諸々の感動を簡約すれば、グレース・バンブリーには人を惹きつけて離さない不思議な魔力がある、ということ。共鳴する身体が震えて已まない「大地の歌声」の魔力。そうして彼女が歌う「セギディーリャの歌」で、私自身の、そのグレース・バンブリーへの視線の度合いは、いっそう深刻化していく。
§
この時私は、はたと気がついた。あの写真の彼女ではない、と――。無論、どちらもグレース・バンブリーに違いない。が、写真ではそれが、ずぼらな髪と薄汚れた灰白色のドレスであったのに対し、映像の中の彼女はまったく違うのだった。整然とした赤いドレスで髪も整えられ、カルメンの美貌を率直に際立たせるものであった。
カラヤン指揮の歌劇「カルメン」は、おそらく徐々に部分的に改良されていったのだ。美しいカルメンの姿のみが、必要であると…。そうなるとあの舞台スティールは、まったく別の、おそらく60年代初期のいずれかの公演のものとなるわけだが、そうして場数を踏んだ彼女とカラヤンは、いかにこの歌劇を愛し、美しい舞台となるよう推敲していったかの努力を見せ、我々にその美の豊饒を示しているか。1967年のこの映画版はその最たるものであったと断言しても、決して間違いではないのではないか。
第2幕の酒場にて、カルメンが歌う「ジプシーの歌」、その他の女性達による舞踊、あるいはちょっとしたフラメンコ・シーンなどを観ていると、もはやここに世俗的なポピュラー・ミュージックの原形的なものを感じ、崇高なフィル・ハーモニーとの対比がなされていることに驚きを隠せない。
単にそれは音楽的裾野の話ではない。そこに女と男がいて、彼らが仲睦まじく語り合い愛し合うという、ありふれた日常の瑣末の「歓喜」として、あるいは「憂い」として、共に楽器があり音楽があるのだということに気づかされる。歌劇「カルメン」が叙情劇と称される所以は、こうした市民生活を実に豊かに浮かび上がらせ、個々の男女の感情を歌の旋律の中に卓抜と表現している点にある。そこが観る側の心を打ち、荘厳とした《美》と《情愛》の機微の調和を思わせるのだ。
カルメンを通じて、歌手グレース・バンブリーを愛する。
ああ、私の思いの言葉など、まったく無力である。酒を飲もう――。
ところでグレース・バンブリーについてだが、ごく最近、非常に奇遇なことに、彼女の歌劇における長年のキャリアの数々と、このカラヤン指揮カルメンを思う存分めっぽう収録したボックス・セットなるものが、海外で発売されたらしい。
私としてはこれは、まだ秘密にしておきたいところなのだけれど、いずれ私はこのボックス・セットを入手して、グレース・バンブリー三昧とやらを愉しみたい。もちろん、その時にまた、彼女の歌について書き記してみたい。
さらには、このカルメンの第3幕への間奏曲に因んで、ビゼーの「アルルの女」の組曲についても、いずれ書いてみたくなった。今回書くことができなかったフランス歌劇の歴史に関しては、そちらで附することにしよう。
ともかくその時まで。hasta luego!!
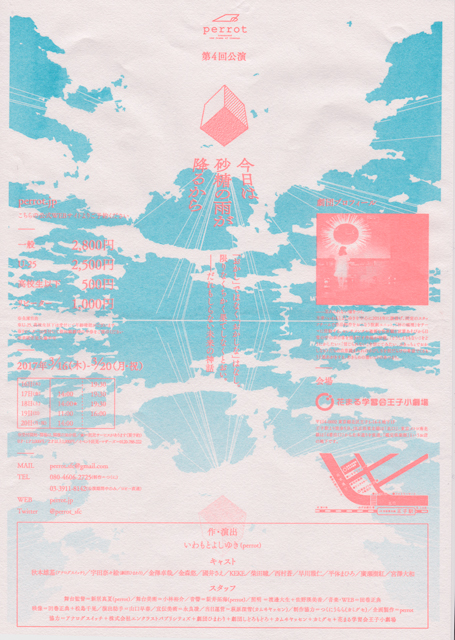
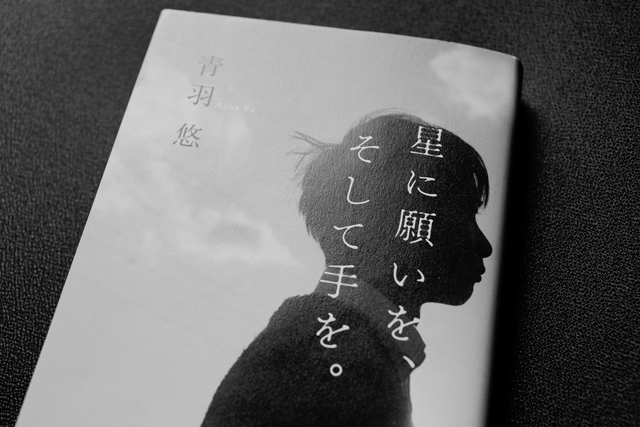
コメント