 |
| 【編集人・寺山修司+芥正彦の演劇理論誌『地下演劇』第3号】 |
自宅の室内にて、溢れかえって高く積み上げられていた書籍群の底部から、ある一冊の本――これは以前、古書店で何の気なしに買った昭和のカルト雑誌――が掘り起こされ、それを開いてパラパラとページをめくっているうちに、私はあるページを発見し、思わず感激した。その雑誌は、季刊『地下演劇』の第3号である。
第3号の特集は、「エロスと演劇」。ここにも《70年代のサブカル》のエッセンスが必然として、あるいは不用意に充満していることに改めて歓喜した私は、今頃(21世紀のこの時代)になってようやくこれを貪り読んだ――ということになる。残念ながら、個人的には遅きに失した発見でもあった。
1970年12月1日刊。発行所は地下演劇社。印刷は宝印刷K.K。編集人は寺山修司、芥正彦。表紙・目次・本文構成・イラストは波羅多平吉。編集スタッフは大場みつえ、吉成定美、波羅多平吉。
もしこの本を、もっと若い頃に、できうるなら学生時代に発見し読まれていたならば、私の人生に違った側面が与えられていただろうことは、推測できる。影響力はすこぶる大きい。しかしながら、そうした邂逅は、やはり荒唐無稽な想像の産物なのであって、1970年のカルト雑誌である『地下演劇』を、少なくとも90年代までに目視して発見するには、よほどの奇跡の連続がなければならなかったはずだ。
したがって、もうそのことは言うまい――。
➤カルト演劇と文芸の貴重な資料
『地下演劇』第3号の精読に係わるモチベーションとしては、寺山修司の「人力飛行機ソロモン」だとか、「トマトケチャップ皇帝」がここに――まさしくここぞとばかりに――収斂されている点で極みなのであり、この本の価値はその一点にあるとさえ思われる。
だが、個人的にはそれよりも、芥正彦氏の「形態都市」が超然と収まっていることに稀有な価値を見出して、さらには、「停滞国家 芸術の復権」と題された、“1970.MAY.5th. THEATRE TABLE・III”の“シンポジウムとしてのテーブル演劇”が掲載されていることにも、奇妙なる感動を覚えてならない。
テーマは2つ。「街路と文学…エロスの『屠殺』・街路は蜂起したか?」と「演劇の街路…烽火の『進路』で季節の撲滅はなされたか?」。ここに参加した6名(作家の秋山駿、詩人の帷子耀、舞踊家の笠井叡、作家の芝山幹郎、同じく作家の夏際敏生、俳優の芥正彦、演出家の佐藤信、カメラリポーターの金坂健二)の発言が克明に収録されていることに、この本の呪縛的な価値が秘められていると思われる。
これを今、自由気ままに凝視している私の肉体は、はるか到達し得なかったArchaeologyの極みなのだと実感した。これらの内容の仔細については、また別の機会に譲ることにしよう。
目配りする人物を限定し、寺山修司の活動の経歴をまさぐれば、そこに彼の文芸的桃源郷とおぼしき“演劇理論誌”季刊『地下演劇』の存在が鈍い光を放っていることに、異論を唱える者はいないであろう。
昭和44年の春、つまり1969年の3月に、寺山氏率いる天井桟敷の劇場「天井桟敷館」が、渋谷の並木橋にて開館。彼の演劇的表現活動はここを拠点とし、70年代以降、さらに活発化していく。
私は一旦、この本の中の寺山修司から遠ざかり、それ以外の中味を敢えて眺めてみるわけである。するとそこには、演劇における「エロス」――と銘打った、ミュージカル『ヘアー』の論説にぶち当たるのだった。
《70年代のサブカル》のなんたるかを探る上で、ミュージカル『ヘアー』は欠かすことのできない、かなり大きな道標であり、プロパガンダである。
私はここで、主題をミュージカル『ヘアー』に転換しようとしているが、季刊『地下演劇』第3号の奇態があまりにも――なかなかくせ者なのであって、そのカルトの毒々しい存在感に少々今、主題の核心がブレそうになって困っている。そうとは言え、繰り返し述べるけれども、ここでの主題は、あくまでミュージカル『ヘアー』であるとし、「演劇とエロス」がまさにその要諦なのである。
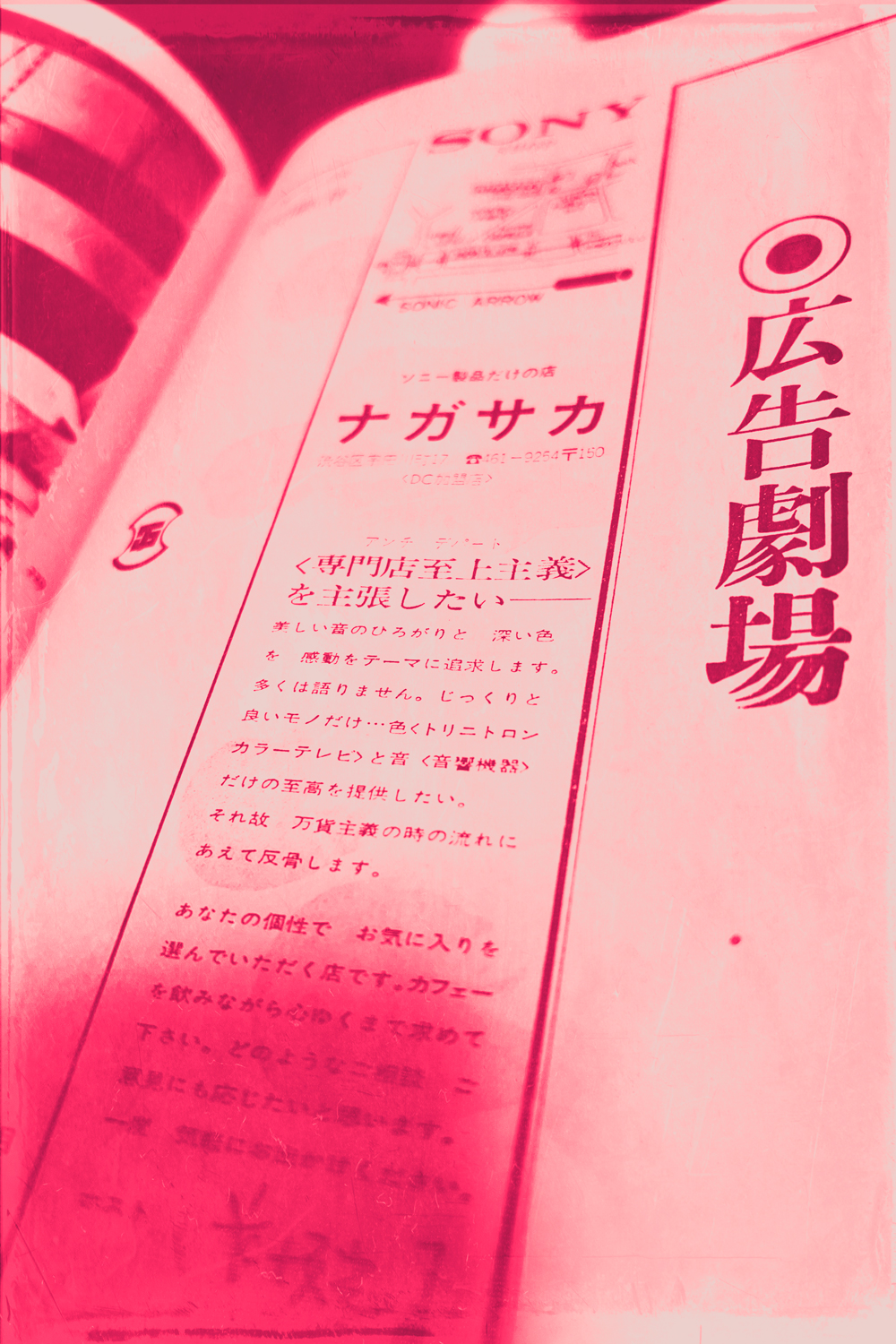 |
| 【第3号の異色の広告欄となっている「広告劇場」】 |
➤『地下演劇』の広告劇場
さて、本題に入る前に、敢えて蛇足する。
かえすがえす、自分が幸運だと思えるのは、今まさに本物の季刊『地下演劇』第3号を読んでいるということなのであった。この目は今、いったい何を目撃したか――。そういう実録的な意味合いで、敢えて寄り道をし、この本の中の「広告劇場」と題された2ページについて触れておきたいと思った。
《◉広告劇場》と記された右側のページには、渋谷・宇田川町のソニー製品専門の店「ナガサカ」と、この本の印刷所ともなっている東京・港区芝の「宝印刷」の広告。「宝印刷」の広告は、ロゴマークのみのシンプルなものだが、「ナガサカ」の広告は、文章に気品が溢れ、流暢で教養主義的な香りを放っている。以下、その文章を引用する。
《〈専門店至上主義を主張したい――〉美しい音の広がりと 深い色を 感動をテーマに追求します。多くは語りません。じっくりと良いモノだけ…色〈トリニトロンカラーテレビ〉と音〈音響機器〉だけの至高を提供したい。それ故 万貨主義の時の流れにあえて反骨します。
あなたの個性で お気に入りを選んでいただく店です。カフェーを飲みながら心ゆくまで求めて下さい。どのようなご相談 ご意見にも応じたいと思います。一度 気軽にお出かけ下さい。ホスト 長坂圭司》
最後のホスト名は、ジェントルマンらしさを醸し出した達筆な自筆署名となっており、私はその字を判別して、“長坂圭司”とご芳名を記したのだけれど、もしかすると“圭司”は、私の読み間違いの可能性もある。もし、正しいご芳名をご存じの方がいれば、ぜひ指摘していただきたい。残念ながら私の拙い調べでは、当時の「ナガサカ」についてのショップ情報を見つけることはできなかった。ともかく、落ち着いた広告文で好感が持てる。
 |
| 【ディス・イズ・ファッション・ワールド「カベ」の広告】 |
左側の広告、“THIS IS THE FASHION WORLD”「カベ」は、赤坂六本木のアパレル系(?)のショップなのであろうか。こちらも以下、広告文を全文引用する。
《なにもできないから寝るひまもなく動き回っているのですかそれともより重いことのためになにかする暇がないのかしら 知ってしまったのですもの 誓って 拒まれるかしらシモン光合成マタイ 帰ってくるんだわ
エミリアへの伝言
――ビルナンバーX2-003994Eあなたはもうその人に会っている 空屋の見取り図
灰となった書物
ベニヤおよびラワン材多少
工業用ミシン 2台 ジンタイ 7台
レンガ又はコンクリートの床
染色されたレザー
臨月の腹に凭れて眠る幼児とその笑顔
――あなたはもうその人に会っている》
この文章は何を意味しているのだろうか。ほとんど理解不能に陥る。が、芥正彦氏の「形態都市」と地続き(字続き)のような気が――しないでもない。文章がどことなく、似ている気がするのである。広告としての効果もどれほどのものか判断しづらいが、麻布台1丁目のサンマンションは1962年に建てられたビルで、今現在、その面影は無いようである。
このような広告が、『地下演劇』の本に掲載され、それ自体が奇天烈であり、60年代後半から70年代にかけての都会人の、独特の息づかいとその文化が滲み出ていて面白い。
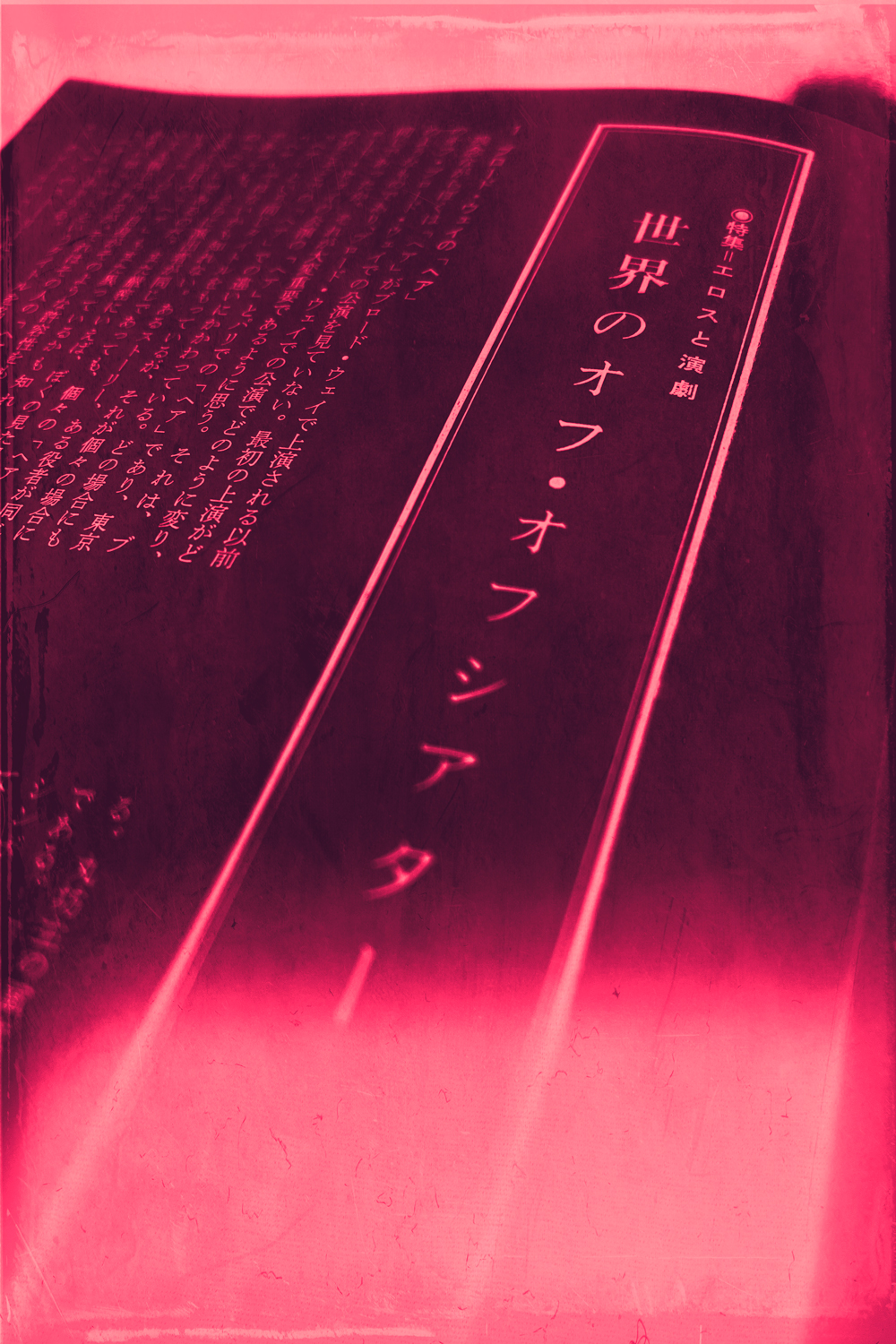 |
| 【飯村隆彦氏の「世界のオフ・オフシアター」】 |
➤話題を呼んだミュージカル『ヘアー』
脚本を手掛けたジェームズ・ラドとジェローム・ラグニによるミュージカル『ヘアー』は、1967年にニューヨークのワシントン・スクエア公園の東、ラファイエット通りにあるザ・パブリック・シアター(The Public Theater)で初上演された。
――泥沼化したベトナム戦争に関し反戦運動がアメリカ国内で高まる中、当局からの召集令状が届いた主人公の青年クロードと、ニューヨークの街にたむろするヒッピーの若者達との破天荒な交遊――それは主として、若者達とのあいだで広がる反戦ムードや人種問題、政治、性の解放、フェミニズム、親子間のジェネレーション・ギャップなどをモチーフにした――をミュージカルとして描いた傑作中の傑作。オフ・ブロードウェイ(オフ・シアター)で人気が高まり、翌年にブロードウェイに進出。その後約4年間、ロングラン公演となる。
69年には、音楽プロデューサー川添象郞氏らの手によって日本語版に翻訳され、12月に渋谷の東横劇場で初演。大いに話題となる。79年には、チェコ出身の映画監督ミロス・フォアマン(Miloš Forman)によって映画化され、こちらの作品は、DVD又はブルーレイで鑑賞可能である。この映画版は、実際にニューヨークの街などでリアリスティックにストーリーが展開されるため、舞台のそれとは趣が異なるが、同じガルト・マクダーモット(Galt MacDermot)の楽曲を踏襲し、歌と踊りの完成度はミュージカルのそれと引けを取らないものと思われる。ちなみに、当時のブロードウェイ公演とロンドン公演のレコードも稀少ながら出回っており、入手は可能である。東京公演の方はかなりマイナーであるが、CDで入手可能。レコード自体はかなり入手しづらいレア盤になっているようだ。
➤『ヘアー』の新裸体主義
『地下演劇』第3号の特集「エロスと演劇」では、映像作家・飯村隆彦氏による「世界のオフ・オフシアター」の稿がある。冒頭に小見出し「ブロード・ウェイの『ヘア』」を付しての随筆が掲載されており、私はこれに刮目した。飯村氏は当時30代前半で、舞踏家・土方巽の暗黒舞踏を映像に収めたことなどでも知られている。
冒頭で飯村氏は、オフ・ブロードウェイ版の『ヘアー』は、“見ていない”と述べる。すなわちザ・パブリック・シアターでの上演がどのようなものであり、ブロードウェイでの公演がどのように変わり、同じであったかについて、《大変重要》というのだ。ブロードウェイでの公演、パリでの公演、そして東京の『ヘアー』は同じタイトルであっても、それぞれ違うのではないか。違うとすれば、どう違うのかが重要という意味だろう。
『ヘアー』におけるミュージカルの特性が、《そのような許容性をもっている》と直観した飯村氏は、今日明日明後日の上演が違っていてもおかしくないということに、ひどく関心があるようだ。ブロードウェイでの『ヘアー』が、《ヒッピーの真実よりもショウの真実》があったとし、自分が見たそれは、《きわめてコマーシャルなもの》だったと述べるのは、そういうことからである。
ここで飯村氏は、『ヘアー』における《裸》――に言及している。残念ながら私は、1968年のブロードウェイでの『ヘアー』でどのような《裸》のパフォーマンスが展開されたのか、具体的に記した資料に出合っていないため、飯村氏の言うブロードウェイでのそれは、《ガクブチ化》したもの――という表現に対して、是非の批評をすることができない。
《全裸のシーンにしても、それまで明るい普通照明によっていたものを、そこだけサイケデリックな照明を使うという特別な扱いによって、むしろカモフラージュした。おそらく、オリジナルな演出では特別な照明ではなしに普通の照明で全部が見えたであろう。裸というものを日常的に扱うのが、ヒッピーの感覚である》
(『地下演劇』第3号・飯村隆彦「世界のオフ・オフシアター」より引用)
アンナ・ハルプリン(Anna Halprin)のモダンダンスを例に、全照明の中でずらり並んだダンサーが着物を脱いで《裸》で佇立している当たり前さを、《日本ではむしろそういう演出を考えた方がいい》と述べる。《裸》は《裸》であり、そこには毛があって、顔もあって、ペニスもあるというのが人間だ――という当たり前さの表現。飯村氏は、『ヘアー』であるなら、最初から最後まで《裸》でやれ、と新しい演出――新裸体主義をぶちまけている。
このミュージカルにおいて長髪をかつらでやるとすれば、それは全く『ヘアー』の精神に反するものだ、という指摘は、私も素直に同意できる。長髪はヒッピーの象徴であり、髪を長く伸ばし、ショートにカッティングしないという態度が、ベトナム戦争への徴兵の痛烈な批判であり、抵抗戦略だからである。『ヘアー』の真のテーマは、そのResistanceの精神の謳歌であって、それをかつらで代用してしまっては、台無しになるというのはもっともな指摘だ。
 |
| 【飯村氏撮影による『ヘアー』公演のデモ行進“BURN HAIR”とは?】 |
ただ、飯村氏の言う、最初から最後まで《裸》でやれ――というのは、理想的人間主義の極端な表現であって、『ヘアー』の反ベトナム戦争のテーマも、ヒッピーの存在意義についても台無しにする可能性があり、この意見には賛同できない。
アンナ・ハルプリンの場合は、プリミティヴな動態としての人間像を発端に、モダンダンスの定義を見つめ直そうとした活動であり、裸体の表層的構造こそが重要であった。しかし、『ヘアー』の場合は、むしろプリミティヴな人間像=《裸》を想起すればするほど、戦争という暴力的な、無頼的手段を用いる古代の人間像に肉薄し、それを肯定しかねない面がある。ヒッピーの自由気ままさは、時に暴力的な破壊行為をおこなうための自由ではなく、自己のアイデンティティーを失わない程度の、おおらかな「その日暮らし」に即したものであり、都会と田舎の絶妙なバランス感覚に秀でた理知的な生活態度である。つまり、ひたすら《裸》である必要もないのだ。
オフ・ブロードウェイという暗黙の立場が、コマーシャル化された都市生活やアメリカ連邦式のポストモダン主義に抗えて表現主義を打ち出すことはある。しかし、そのヒットによって、皮肉にもブロードウェイという本格的な商業ビジネスに乗っかっていくことも、これまた暗黙のステータスになってしまっている。一概にこれを否定することはできない。
少なくとも『ヘアー』がブロードウェイ化されなければならなかった理由として、大衆に訴える政治へのResistanceの度合い、つまりその市民同感覚のうねりのエネルギーの需要が、商業演劇として採算の見込みありと踏まなければ、当時まだアメリカ占領下の沖縄の本土復帰の夢が朦朧としていた頃の日本国内において、そのミュージカルの上陸上演が果たせなかったであろうことは、想像がつく話なのである。
あえて《裸》へのこだわりを幾分か捨て、ブロードウェイで良くも悪くも《ガクブチ化》されたことは、私たち日本人の芸術志向や表現主義を開化する上で、たいへん重要であったと、私は思うのだ。
飯村氏が掲載しているルポルタージュ的写真=「<ヘアー>のブロードウェイ公演」とキャプションに記したデモ行進の風景の中には、“BURN HAIR”と書かれたプラカードがあったりして面白い。それはブロードウェイ化されたことへのResistance(=オリジナルの『ヘアー』を返せ)なのか、逆にResistanceへの逆風(=アメリカ式のやり方に従え)なのか、ある一つのミュージカルが抱えていたテーマに対して、大衆のアジテーションの多様性は、極東の小さな列島にいる日本人にとっては、なかなか理解しづらいものである。
あの時代の「エロスと演劇」の考察については、澁澤龍彦の“現代エロス論”を照会してみたかったのだが、長くなってしまうので、また別の機会に譲ることする。


コメント