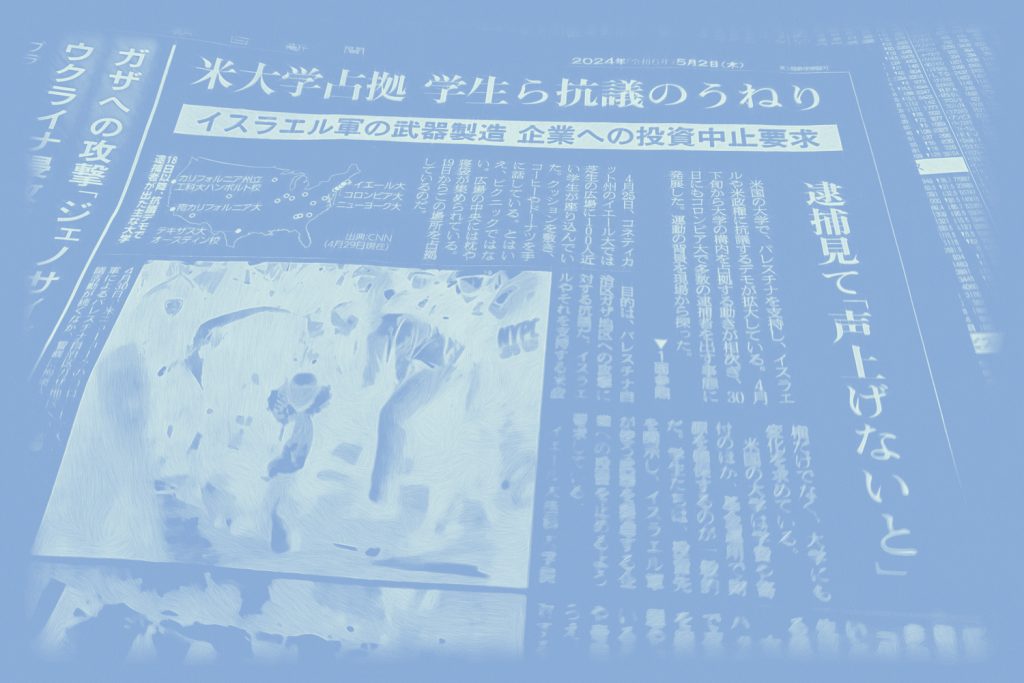
先日の「小説すばる新人賞」の例に倣って、ここでは「新潮新人賞」の応募規定を備忘録とする。
『新潮』(新潮社)2024年7月号に掲載されていた「第57回 新潮新人賞応募規定」を以下、要約して記した。
- 未発表の小説であること。400字詰め原稿用紙(ワープロの場合は400字詰め換算)50枚以上250枚以内。同人雑誌発表作や他の新人賞に応募済みの作品は対象外とする。
- 当選作の出版権は小社に帰属。
- 当選作の正賞は「特製記念ブロンズ楯」、副賞は50万円。
- 選考委員は5名。上田岳弘、大澤信亮、小山田浩子、金原ひとみ、又吉直樹。
幾分か、緊張感が走る。背筋がゾクゾクとする。なんだか、オロナミンCが飲みたくなってきた。
この『新潮』の広告面には、『ドナルド・キーン著作集』(全15巻別巻1)が高潔な雰囲気でビジュアル化されており、まことに麗しいと感心した。と同時に、それを眺めていて、さらに背筋が伸びる思いがしたのだった。
一方では、『トマス・ピンチョン全小説』(全12巻)の広告もあり、しかるに、文学研究の道筋の層状的にその螺旋階段を昇ろうが降りようが、容赦なくそこは、《無限回廊》なのだということを指し示しているかのようで、鳥肌が立つ思いがした。
断捨離の最中にて
とにかく本をいっぱい捨てないといけなくなった。
新たなことを決意した企て――。しかしながら、家の中の諸々の書棚が苛烈にいっぱいで、それだけでは到底収まらない分量の本が、そこかしこに溢れかえってしまっている。
そうならば、古い児童書を処分しよう。楽譜系の書籍も処分しよう。それから、90年代くらいにせっせと買い込んだプロレス本も、処分しよう――。
なに? 『週刊プロレス』?
ああ、大変懐かしい…。
1992年の、あの頃の“読者観戦記”なんていうのは、FAXで編集部に送っていたりしていたのだね。おおむね、ワープロ専用機で文章を作成し、それをプリントアウトして、FAXでベースボールマガジン社の週プロ編集部に送るといった手練手管の時代…。あの頃はまだ、〈観戦記くらい、ワープロなんて使わないで手書きで書けよ〉――みたいな読者の古めかしい批判も一部あったりはしたのだけれど、テレホンサービスで各団体の大試合の速報を入手していた…なんて、たぶん今の若い人には当然、理解不能だろう。
そんなこんなで、捨てようとしていた直前で古雑誌を読み始めてしまい、ついにまるごと、全部舐め回して読み通してしまったり。おいおい、これこそ時間の浪費だ。
浪費ついでにいうと、その雑誌の中の、某プロレスショップの広告(東京・台東区上野の雑居ビルに在ったショップ)では、村田善則先生謹製の「アントニオ猪木ブロンズ像」が販売されていた。
これは懐かしい。
30センチの堅固な造形で、プロレスファンなら誰でも知っている名アイテム。価格は15,450円と記されていた。
ちなみに断っておくけれど、この製作者は、同姓同名の元プロ野球選手の“村田善則”さんではない。熊本出身で、飲食店も経営する「MANスポーツ」のブロンズ像の達人。“ミスターブロンズ狂”とも称したい人。
あの頃の私は思いもしなかったが、日本海の向こうの半島の文化圏では、強者に憧れるエネルギーが凄まじかったことを想像してしまう。
強者の偉人的栄光を称賛するべく、「アントニオ猪木ブロンズ像」のような、そういう立体的な造形物をこしらえて、その偉人伝説を継承することは、しばし常識の範疇にあるようである。かの力道山だって…いやいや、それよりもそう、もう一人偉大な人物がいるではないか。それは、誰もが眼にしたことのある人…あの角張った髪型と恰幅のいい青年君子――だってそうではないか。彼を偶像化した、巨大なブロンズ像のモニュメントね。あれは、巨大すぎて、家の中には置いておけない。
そんなことよりも、“ミスターブロンズ狂”の村田さんこそ、最も称えるべき人物なのではないだろうか。強者をブロンズにして「ずっと見ていたい」という欲求は、まことに人間的な、根源的な精神のような気がするからである。
思いを馳せ、その本を閉じ、存分に満腹感を味わったところで、断捨離の所作に移行した。こうしてすべからく、物は目の前から消えていく。「反実存」である。皮肉にもこれは、ブロンズ像の欲求とは真逆だ。断捨離とは、予期せぬ波乱に身を擲(なげう)つことを意味するのだった。
蛇足。こういうのもある。
ぽろりと書棚からこぼれ落ちたのは、ごく最近の新聞記事のスクラップだ。見出しは「米大学占拠 学生ら抗議のうねり」。
イスラエル軍の武器製造に関わる企業に対し、アメリカのコロンビア大学の学生らが、構内を占拠した旨の報道――。同大学では、イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃をやめろと抗議活動を継続し、警察に拘束される学生もいた。同じく、カリフォルニアのスタンフォード大学でも、学生の抗議活動が活発である云々が記事に記してあった。この報道の記憶は強烈で、なかなか消えそうにない。
「下着小説」こそ天下泰平?
物を片付けて処分したりするのは、なにかと疲労感を伴うものだ。徒労に終わることは少ないが、骨が折れる作業には違いない。だから、やたらと一息のコーヒーブレイクが冗長ぎみになる。
うっかりすれば、コーヒーを飲み始めた途端に、またもや目の前の本に釘付けになり、読み更けてしまうことがある。
アメリカの作家ディーン・レイ・クーンツ(Dean Ray Koontz)氏の名著『ベストセラー小説の書き方』(大出健訳/朝日文庫)が面白くて、毎晩読んでいる。コーヒーブレイクにも最適な本だ。
ここで刮目してしまった文章がある。
“悪貨は良貨を駆逐する”という経済原則(グレシャムの法則)。
これをクーンツ氏は、出版業界になぞらえ、その“悪貨”といっていいのかどうかわからないが、一時期、本屋が抱える本の半分が「下着小説」に占領されたこともあった――などという記述になっていて、思わず感心した。
クーンツ氏の「下着小説」という括り方が、いい得て妙で、私はこの表現がなかなかどうして笑ってしまうくらいに好きなのだ。偶然ながら、グレシャムの法則を用いて私も同じようなことを過去に書いてしまっている(「伴田良輔の『眼の楽園』―最後尾の美学」)。
恐縮の極みなのだけれど、そこでの仮説では、我が敬愛する作家・伴田良輔氏の著作物が、いうなれば「下着小説」なのであった。実際に伴田氏が、下着フェチの人である――という意味では決してない。しかし、それにしても、あまりにも的を射ていると思ったのは事実である。
長い間私も、伴田氏の本を舐め回してきた影響も小さくなく、最近ではパンツ(下着)のことなどを書きまくっている(「人新世のパンツ論」)。むろん、あれはおふざけで書いているのではない。いたって真面目である。そういう意味でいうと、その方面の強者である伴田氏の「ブロンズ像」なるものが、この世に堅固に存在してもいいはずだ。私はそれを、こっそりタンスの隅にしまっておきたいので、どなたか村田氏に発注お願いします。

懐かしい「島田屋」さん
話はコロコロと変わる。断捨離の作業は佳境と思えてきた。いや、書棚をひっくり返せば、どんどん古いものが湧き出てくる。写真である。断捨離は尽きそうもない。
ん? これは本当に懐かしい写真だ。
我が母校(千代田工科芸術専門学校)の近隣に存在した、ある文房具店を写したものである。
たぶん、ライカのコンパクトフィルムカメラ、Leica miniluxで撮ったのだと思う。今から22年前の、2002年8月。学生時代(91~93年)が懐かしくなり、台東区上野の下谷と入谷界隈を歩き回った際の一写真。この写真のほぼ中央、緑色の公衆電話が設置してある店…。そこが、「文具の島田屋」さんなのだ(「入学式回想録」)。
学生だったその当時、何度かここの「島田屋」さんで、不足した文房具を買ったこともあった。
千代田工科芸術専門学校は、ビジネス校であり、マスメディアを専門とした学業に関して、たいへん厳しい指導方針だったので、入学時の学生の約半数が、期末試験で篩(ふるい)にかけられ、2年目には学生の在籍者数が半分となって断捨離されたりした。とはいえ、団塊ジュニアの学生期というのは、ことあるごとに篩にかけられ、ドロップ・アウトしていくのが宿命的な時代の趨勢だったのだ。
ともかく、その都度出される課題は、締切を守るのが鉄則だった。出した後もダメ出しをよくされたし、私が書いた創作台本には、担当の先生による赤ペンチェックがめいっぱい書き加えられ、ぐうの音も出ない、ということもしばしばあった。
文房具は、勉学の善き友と思うしかなかった。昼休み中に「島田屋」さんに行き、ペンを買う。消しゴムを買う。ノートを買う…。生き残るために。生きながらえるために。多くの学生にとって、この文房具店は、いわば、小中学校の“ほけん室”に近い存在だったのかもしれなかった。

そんな「島田屋」さんを撮った写真を、懐かしく眺める――。
2002年当時、店は現役ばりばりで営業していたのだ。しかしそれ以後、この界隈を訪れた際に見たのは、シャッターが下ろされた状態の「島田屋」さんであり、既に閉業してしまっているといって差し支えないと思われるが、少なくとも最新のGoogleマップを見た限りにおいては、まだ店舗自体は残存しているようなのだ。
あの頃、ひょんなことで伴田氏の本――河出書房新社の文庫本『愛の千里眼』――を初めて買うことになった時の書肆は、この「島田屋」さんが在った小道を、さらに北へ歩き、交差点を突き抜けた先である。しかし、それも今は無い。
引き裂かれるような思いで、写真を断捨離した。
学校の界隈をふらふらしていたからこその、それぞれの出合い。
伴田氏の本は、まさに運命的な、奇妙な出合いであり、それがなかったならば、いま私はクーンツ氏の本を読んだりして、「下着小説」云々であらためて伴田氏を師と仰ぐことさえなかったのだから。この縁は、全く不思議なものである。
§
やたらとコーヒーブレイクが長くなった。仕方がないことかもしれない。新たなことを決意した企ての、その準備としての断捨離は、あちこち個人的な思い出との寄り道を経由して成就する。そうして愛玩してきたモノたちの供養をしたのだ、というとらえ方もできるだろう。
それにしても、書きなぐった備忘録は、始末が悪い。私を文筆家気取りに仕立て上げようとしている。
ただ、それはちょっと違うのだった。誰のせいでもなく、70年代に生まれた後の、重し軽しの人生のドロップアウトの連続で疲弊したがゆえに、これ以上、己の心身が篩にかけられる心配がないのだ。かけられた後の、残滓だからだ。
いわば、怖いもの知らずなのだ。それがまた逆に恐ろしい。その物書き家さんへのお膳立てのように仕向けている自分自身が、恐ろしい。全く荒唐無稽な話なのだけれど。
荒唐無稽ではある――。けれども、無理難題であるともいいきれないではないか。
え? いったいなんだなんだ、これは。
起きたことを否定せず、全て肯定してしまっていい。何かが私を掻き立てているのだった。焚き付けているともいえる。私はそれに、じっと耳を欹(そばだ)てるしかないのだ。人生はここからようやく始まるのである。


コメント